
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
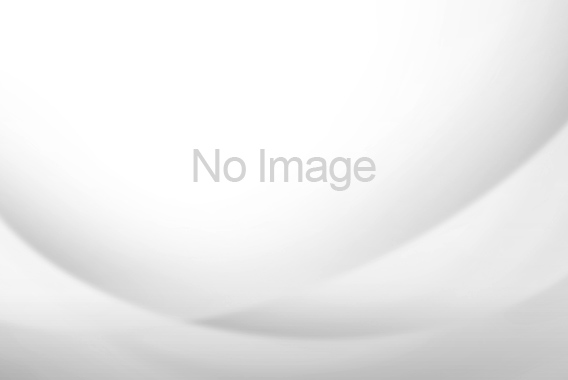
米ラスベガスで年の初めに開催される世界最大のテクノロジー見本市「CES」は、毎回、大手企業がハイテク機器の新製品を発表・展示する。今年のCES 2023は、3年ぶりの本格的なリアル開催となり世界中から3200社以上が出展した。
近年、CESで注目されるものの一つとして挙げられるのがロボットだ。CESは、大企業はもちろん小規模な新興企業が最先端のロボティクス技術を披露する場でもある。今回も多くのロボットが出展され注目を浴びていた。その中でも多くの人が集まっていたのが米アマゾンのブースだ。
アマゾンは、2021年に音声アシスタント「Alexa」を搭載して動く家庭用初のロボット「Astro」を発表、家庭内を歩き回れる車輪を搭載した「動くAlexa」として話題を呼んだ。Astroは、潜望鏡型カメラや荷台などを備え、家庭やオフィスの監視、ペットや高齢者の見守りや遠隔監視、人とのコミュニケーションのほか、飲み物を運んだりもできる。
アマゾンは、「The 9 best things Amazon announced at CES 2023」の一つに「Amazon Astro meets CES」としてAstroを挙げている。今年、アマゾンは初めてAstroをCESに持ち込み、ライブデモで実物およびその強化された機能を紹介する、と述べていた。
実はこのAstro、米国内の限られたユーザーのみの販売にとどまり、商品としては試験的な位置づけで一般販売は行われていない。コロナ禍で見本市がリアル開催されなかったこともあり、リアルで行われる初のAstroのデモに多くの人が集まった、というわけだ。Astro販売後も、例えば、昨年、ペットの認識機能を追加するなどアップデートを重ね、意欲的に開発を進めている。アマゾンはAstroをユーザーの生活や習慣を理解し手助けする家庭用パートナーとして進化させようしており、今後の注目だ。
今年2月には、日本のプリファードロボティクスが人の指示で家具の自動運転を行う家庭用自律移動ロボット「カチャカ」および専用家具「カチャカシェルフ」を発表し、これも大きく話題を呼んだ。
カチャカは、カチャカ本体とカチャカファニチャー(棚)がセットとなり、「人の指示通りに自動で動く家具」つまり「スマートファニチャー」として作られている。ロボット掃除機のようなカチャカ本体に話しかけて家具を思い通りに動かすのだ。イメージビデオでその様子がつかめる。さまざまな深層学習技術や音声認識テクノロジーを活用、アプリや呼びかけでスムーズに動く。スケジュールも覚えられるので、習慣化や忘れ物防止など、使い方は自分次第という。
ちなみに、プリファードロボティクスの母体であるプリファードネットワークスは、2018年の「CEATEC JAPAN 2018」で、トヨタ自動車の生活支援ロボット「Human Support Robot(HSR)」を用いた「全自動お片付けロボットシステム」を初公開、従来のロボットシステムでは実現困難だった部屋の全自動片付けを実用レベルで実現して話題を呼んだ。
従来の家庭用ロボットは、アマゾンのエコーやGoogleのネストなどのスマートスピーカーのように、主に対話で情報提供やコミュニケーションなどを行う「対話型」がある。この他、ソニーのAIBOなどに始まるペットや小さなロボットの形をした「ペット型」、ルンバをはじめとするロボット掃除機のように床を掃除するなどの「単機能型」のものが多かった。
近年においては、これらの機能を総合し、AIを搭載し多機能で気が利く家庭生活のよきパートナー・よき補助者となり得る存在としてのロボットを作ろうという流れが見られる。Astroやカチャカは、そうしたベクトルのもと設計されていると感じる。
スマートスピーカーなどの家庭用ロボットを愛用する立場からいえば、「言うだけで物を持ってきてほしい」「読み終えた本や使い終えた道具を元あったところに戻してほしい」「宅配便や来客の応対を行ってほしい」「掃除や窓掃除などを行ってほしい」「夜間や留守宅の警備をしてほしい」「ペットや家族などの見守りや声掛けを行ってほしい」など要望はたくさんある。
しかし、家庭用ロボットには多くの課題がある。家庭内のあるあらゆる物をつかんだり運んだりするためには、かなり高度なアームが必要だろう。更に、家の中から言われたものを見つけ出すことができるのかなど、人間が行うにはさほど苦労しないこともロボットには難しい場面がたくさんある。階段を昇り降りできるのか。家の間取りや様子をどこまで把握できるのかなど思い付くだけでも課題は山積みだ。
また、家庭用を前提にするなら一般家庭が維持できるコストで提供する必要もある。生活全般を支援でき、人間レベルで手伝いが可能な実用家庭ロボの登場にはまだ時間が必要とも感じるが、AIの進歩もめざましい今、それは近い将来のことなのではないかと期待している。
2021年の発表後、Astroがいつ日本で発売されるのかと期待していた人は多いと思う。現状としては、前述のようにまだ一般販売には至ってない。しかし、ユーザーのさまざまなフィードバックを開発に役立てながら、その進化は続いている。「開発中」のAstro、今後の機能強化と一般販売に期待だ。
また、トヨタ自動車の生活支援ロボットHSRも気になるところだ。2012年に発表、ロボットとの共存社会の実現を目指し、日々研究に取り組んでいる。トヨタおよび世界中の多くの研究者がHSRの研究を行っているが、研究成果は、論文やオープンソースソフトウエア、ロボット競技会などで公開し、知識を共有している。今回のCESには、ソニーグループやウーブン・プラネット・ホールディングス(トヨタ自動車の子会社)も、生活支援ロボットを出展している。こちらも今後に期待したい。
家庭用生活支援ロボットの技術は、ビジネスにも生かしていけるだろう。家庭用途で実用レベルの熟成した技術なら、業務に生かすことはさほど難しくはない。この点、アマゾンはAstroを家庭用の他、ビジネス用セキュリティロボットとしての活用も模索している。「Astroのインテリジェントで自律的なモビリティと革新的な監視機能が、中小企業でも家庭と同じように役立つと信じている」と述べている(「How Amazon is enhancing Astro for the home and beyond」)。
こうしたロボット全般、AIなど先端技術をどんどん活用して、さまざまな用途で大きく発展していくのが楽しみだ。家庭でも仕事でも、頼りになる「支援ロボット」、今後を明るく見守っていこう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」