
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府は、2020年の東京オリンピックの開会式に当たる7月24日を「テレワーク・デイ」と名付けた。交通機関や道路が混雑する始業から10時半までの間、一斉にテレワークを実施する企業・団体を募集する。テレワークとは、「離れた」+「仕事」という言葉通りの意味で、ICTを利用して自宅やモバイルなど職場外から働くこと。テレワーク・デイは「働く、を変える日」というキャッチフレーズの下、テレワークという柔軟な働き方スタイルを取り入れ、業務を改革する国民運動を展開しようというものだ。
そもそも2012年のロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会のときに、話は遡る。交通混雑によりロンドン市内での移動に支障が生じることへの対策から、市内の企業にテレワークを呼び掛けた。すると、約8割が導入した。この成功例にならい、東京大会の開会式に相当する7月24日に、このテレワーク・デイを設定したのだ。
テレワーク・デイによるテレワーク導入の最初の第一歩は、来る7月24日の始業から10時半までに行う「一斉テレワーク」の実施だ。7月24日の始業から10時30分までテレワークの実施またはトライアルを行う「テレワーク実施団体」として341件が、効果測定が可能で100人以上の大規模テレワークを実施する「特別協力団体」として78件が名乗りを上げている(2017年7月時点)。
テレワーク・デイについては、公式サイトや動画、報道資料などが公開されている。4月18日のプロジェクト開始から、総務省は新聞広告やポスターなどで広報を行っているので、何かと目に触れているだろう。
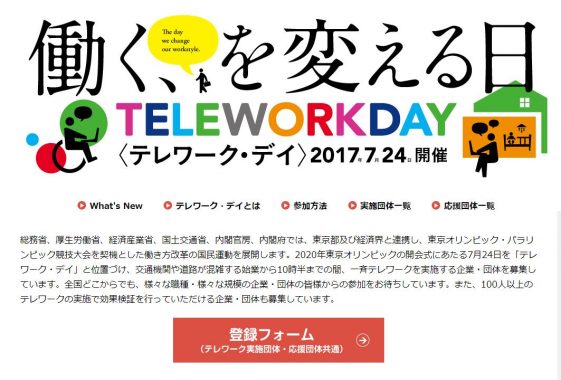
「テレワーク・デイ」公式サイトのトップページ
インターネットやノートパソコン、スマートフォンやタブレットなど、情報通信機器を利用し、時間や場所の制約を受けずに働くテレワークの光景。発祥は1970年代の米国といわれ、ICTの普及とともに全世界的に広まった。
テレワークはそもそも、企業に勤務する被雇用者が在宅勤務などを行う「雇用型」と、個人事業者・小規模事業者が行う「非雇用型」(自営型)の2つに区分される。
雇用型は、自宅を就業場所とする「在宅勤務」、施設に依存せずいつでもどこでも仕事が可能な「モバイルワーク」、サテライトオフィスやテレワークセンターなどをテレワーク専用の施設を就業場所とする「施設利用型勤務」の3つに分けられる。
さらに、すべての業務をテレワークで行う「常時テレワーク」と、普段はオフィスに拠点を持ちつつ、時々出先で作業を行う、または一部の日に自宅で作業を行うなど、部分的にテレワークを行う「随時テレワーク」という、実施頻度による区分もある。
自営型は、個人事業や法人として主に専業性が高い仕事を行い独立自営の度合いが強いSOHOと、あっせんを受け、空いた時間などにデータ入力やホームページ作成などを行う「内職副業(在宅ワーク)型」に二分される。
テレワークを推進する日本テレワーク協会によれば、テレワークの効果は7つの項目に集約できるという。
1つ目が「雇用創出と労働力創造」。退職した高齢者、通勤が困難な障がい者、遠方居住者などの雇用がテレワークで実現できる。決められた時間に出社することが弊害となっていた人材を雇用できれば、人材側、企業側共にメリットを得られる。
2つ目が「オフィスコストの削減」。オフィススペース、オフィス用品などのコスト、通勤にかかっていたコストなどを削減できる。
3つ目が「優秀な社員の確保」。今まで育児や介護など、さまざまな事情で離職せざるを得なかった社員をテレワークにより継続雇用できる。企業側は社員が身に付けたノウハウや、もともと持っている優秀な才能をムダにせずに済む。社員側も育児・介護離職などを避けられて助かる。
4つ目が「ワーク・ライフ・バランスの実現」。テレワークで家族と過ごす時間や自己啓発、趣味などに費やせる時間が増える。仕事と生活の調和が取れて精神的にも安定し、より意欲的に仕事や生活に取り組める。
5つ目が「生産性の向上」。インターネットとICT機器があれば、いつでもどこでも居場所がオフィスになる。営業や打ち合わせなどの合間、乗り物の中やカフェ、オフィススペースなどでも作業が行えて時間をムダにせず効率アップ。より迅速・機敏に顧客や取引先からの要望に対応できるのもメリットだ。
6つ目が「環境負荷の軽減」。テレワークによる通勤減少、オフィスの省力化により、電力消費量やCO2排出量、ゴミなどが削減できて環境にも優しい。
7つ目が「事業継続性の確保(BCP)」。2011年3月の東日本大震災による首都圏の交通機関運休や停電などに際し、テレワークがより円滑な業務と事業継続に効果的だと実証された。災害だけでなく、インフルエンザなどのパンデミックに対しても、生産性の維持、被害拡大の防止などの効果が望める。
働く側も雇う側も大きな効果が望めるテレワーク。来るテレワーク・デイを機会に、導入を検討してみてはいかがだろうか。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」