
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
Microsoftが提供する表計算ソフト「Excel」。仕事でパソコンを利用する人ならば、触れたことのない人はいないほど広く普及したソフトだ。実際、多くの企業や組織での業務に欠かせない存在になっている。Excelで作成したファイルが、集計や経理などの業務で中核的な役割を果たすケースも少なくない。重宝するツールだが、近年は「脱Excel」の話題も耳にするようになってきた。企業環境やIT環境の変化に伴い、Excelだけに頼るデータ活用のスタイルがそぐわなくなってきているためだ。
現在のクラウド活用の広がりは、Excelの限界を改めて浮き彫りにしつつあることも指摘され始めている。例えば、社内外のメンバーがクラウドなどでつながり、同時に作業を進めながらリアルタイムでデータ更新する業務が増えると、ローカル保存型のExcelには対応ができなくなってくる。また、メール添付やローカル保存を前提とした運用では、同時編集が難しくなりがちで更新型の共同作業には適さない側面もある。
また、Excelファイルをメールに添付したりファイルサーバーから読み出したりして、各自が更新する業務スタイルだと、ファイルの最新版がわからなくなりがちだ。基幹業務でExcelを使っていると、データ量の増大に伴って処理速度が低下する影響も懸念される。そもそも、Excelは個人ベースでデータ処理やグラフ描画をするために最適化された業務支援ツールであって、組織の業務を担わせるのは荷が重いと感じる部分もある。
その他にもExcel活用で発生しやすい課題は、多々ある。例えば属人化だ。企業や組織に"Excelの使い手"として名をはせたメンバーがいることは少なくない。お願いすると、業務に役立つExcelファイルを作ってくれる。関数やマクロ、ピボットテーブルなどを駆使して、業務効率を向上させる頼もしい存在だ。しかし、こうしたExcelの使い手が高度に編集したExcelファイルは、作成者以外には内容が理解できないことが多い。更新・修正のたびに余計な工数やリスクが増えることもある。使い手が異動したり、退職したりすると、ブラックボックス化したExcelファイルだけが残ることになる。
前述したように、バージョン管理に悩まされるのもExcelの現場の通例だ。ファイルが更新されるたびに最新版が出来上がり、どれが最新版だかの判別がつかなくなる。セキュリティ面でもリスクを抱える。重要なデータを保存したExcelファイルは、誤って外部に送信したり悪意を持って持ち出されたりした場合には情報漏えいに直結する。その他にも、Excelファイルに外部のシステムから大量のデータを手作業でコピー&ペーストして、月報などを作る業務は今でも多くの企業で残っている。デジタル化されたデータを人間が手作業で転記して、Excelでグラフを作る業務は、DXの時代に似つかわしくない。
これらはExcelそのものに問題があるわけではなく、Excelという優秀なツールの利用範囲を超えて「活用しすぎ」てしまっているからこそ起こる課題だ。Excelの機能を超える業務には、適したツールを活用する。それが脱Excelの1つの方向性になる。
脱Excelが求められるシーンごとに、どのようなツールが活用できるのかを整理してみよう。リアルタイム共有が求められるシーンでは、クラウド型ツールが有効だ。複数人がリアルタイムで共同作業でき、常に最新版に更新されることで意思決定のスピードも上がるクラウド版のExcelとして使えるMicrosoft 365の「Excel for the web」やGoogleの「Googleスプレッドシート」が有力候補だろう。ToDo管理やタスク管理も複数人で共有できるのでお勧めだ。データの可視化・高度分析には、BIツールを活用してみよう。グラフやダッシュボードが自動生成され、管理者は俯瞰的に状況を把握できる。自動更新機能により、人手による集計作業そのものを不要にできる。
業務プロセスの標準化では、業務特化型アプリの導入で効果が期待できる。経費精算や販売管理など、多くの業務に向けてクラウドサービス(SaaS)が提供されている。こうした専用システムに任せれば、入力や集計が効率化され、承認フローもシステム化される。ノーコード/ローコードツールを使って、これまでExcelで作成していた業務アプリを自前で開発すれば、SaaSでは手が届かないきめ細かい業務対応が可能になる。Excelに依存した属人的な業務アプリの運用から脱却できる。ローカルのExcel活用から、クラウドサービスやノーコード/ローコードツールで開発した自社専用アプリなどへの移行で、アクセスの権限管理やログ取得などが可能になり、セキュリティ対策も高まる。監査対応やコンプライアンスの強化にもつながる。
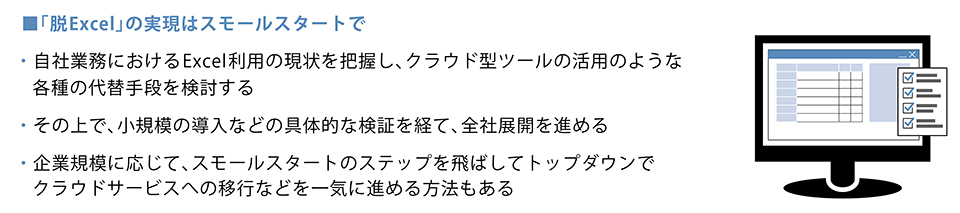
こうした脱Excelは、ステップを踏んで実現すると良い。まずは自社の業務へのExcel利用の現状を把握し、上記のような代替手段を検討する。その上で、小規模導入による検証を経て、全社展開を進めるというものだ。企業規模によっては、スモールスタートのステップを飛ばしてトップダウンでクラウドサービスへの移行などを一気に進める方法も採れる。ただし、ツールを活用するには通信環境を見直す必要がある。ツールを快適に使うためには、高速な回線やビジネスWi-Fiが重要だ。
Excelは優れたツールであり、「脱Excel」はExcelの利用を完全に排除するものではない。小規模な作業や個人用途では、Excelが今後も活躍するだろう。大切なのは、業務の目的や規模に応じて最適なツールを選び、組織としての生産性と安全性を高めていくことだ。Excelと他の仕組みをどう使い分けるかを見直すことが、「脱Excel」の本質なのだ。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=岩元 直久
【MT】
強い会社の着眼点