
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
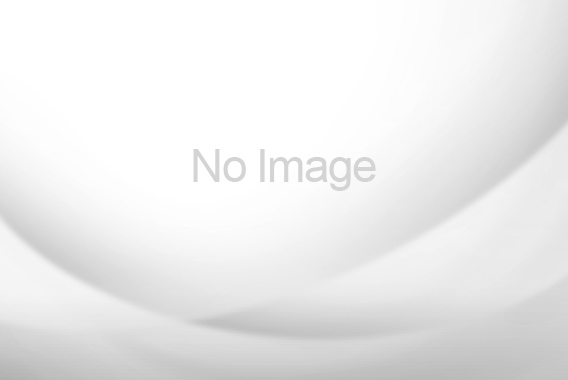
10月13日の河野デジタル大臣の記者会見が話題となっている。主な内容はマイナンバーカード(以下「マイナカード」)について、健康保険証との一体化を前倒し、2024年度秋に現在の健康保険証の廃止を目指すもの。運転免許証との一体化も2024年度末の予定について、その前倒しを警察庁と検討する。また、マイナカードの電子証明書機能をスマホに搭載、マイナカードで可能となるオンライン申請やマイナポータルへのログイン、コンビニでの各種証明書交付をスマホでできるようにし、まずはAndroidスマホによるサービスを来年5月に開始するという。
職業柄、筆者はマイナカードを早々に作った。前回記事で触れたインボイスの登録申請および経過や結果の確認もマイナカードとスマホで行った。スマホの「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」では、マイナカードの読み取りで接種記録が表示、すぐに証明書が発行できた。健康保険証としての利用登録も早々に行った。改めて制度の全体像については、総務省の「マイナンバー制度とマイナンバーカード」が、その利点などは同サイト「マイナンバーカードのメリット」に分かりやすくまとめられているので、ぜひ参考にしてほしい。
今後、マイナカードの便利さが広がるのはよいことではあるが、気がかりはマイナンバーとマイナカードの扱いだ。総務省の「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!」のとおり、マイナンバーは重要な個人情報だ。人に知られないように注意する必要がある。この点、厚生労働省の「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」には、マイナンバーを悪用できない仕組みや、マイナカードを他人が使ったり個人情報を調べたりすることはできない仕組みなどがまとめられており、むやみに恐れる必要はないものの、マイナカードは使い道が広がるほど持ち出す機会も増えるので、十分な気遣いが必要だ。
今年6月から行われているキャンペーン「マイナポイント事業」第2弾では、マイナカードの新規取得と健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録を行うことで最大2万円分のポイントがもらえる。大盤振る舞いともいえるこのキャンペーン、実はカードの申請期限が2022年9月末から12月末に、健康保険証と公金受取も12月末に変更されるなど、当初予定の期間を延長して行われている。
その背景には、総務省統計「マイナンバーカード交付状況について」にある、全国のマイナカード交付枚数率51.1%(10月末時点)という、決して高いとはいえない状況があると思われる。これは、キャンペーン開始時の6月末の45.3%から6%弱しか増えていない。「デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及」として推し進めるマイナンバー制度においては、カードの所有率がほぼ100%、最低でも8~9割程度にならなければとも感じ、少しもどかしさを覚える。
今後、見込まれているマイナカードの健康保険証としての利用(「マイナ保険証」とも呼ばれる)については、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」を参照しよう。マイナカードを病院や薬局の読み取り機で読み取り、認証を行うことで、健康保険証として利用できる。それ以外にも、限度額適用認定証や特定疾病療養受療証など各種証明書の持参を省けるのはメリットだ。
しかし、マイナ保険証は「2023年3月末にはおおむね全ての医療機関等での導入を目指す」が、現状ではすべての医療機関・薬局で使えるわけではない点はデメリットともいえる。マイナ保険証を利用できる医療機関は、マイナ受付のステッカーとポスターを目印にするとよいだろう。リストは、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」から取得できる。
スマホの機能搭載については総務省の「マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載 第2次とりまとめ」が参考になる。今まで紹介したサービスの他、子育て支援や確定申告などのオンライン行政手続き、銀行口座開設、携帯電話やキャッシュレス決済の申し込み、住宅ローン契約などの各種民間サービスが挙げられている。
ここで浮かんでくるのが「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」というデジタル庁のスローガンだ。今年の1~2月に行われたデジタル庁の「業種別マイナンバーカード取得状況等調査」によると「マイナンバーカードの未取得理由」は、「情報流出が怖いから」が35.2%、「申請方法が面倒だから」が31.4%、「マイナンバーカードにメリットを感じないから」が31.3%であった。
統計からは、国民のデジタル化への懸念が感じられる。まずはこうした国民の気持ちの解決に努めるべきではないかとも感じる。今回のキャンペーンで取得率がどれだけ伸びるかも気になるが、セキュリティの充実や利便性、安全性を正しく分かりやすく伝えること、機能を使いやすく整備する、使い方講座や相談窓口の開設などの啓発活動にも力を入れるべきだろう。
今回の大臣発言で「従来の健康保険証がなくなっちゃうの?」とショックに思った人も多いだろう。デジタル化を勇み足で進めるよりも、普及率や状況を鑑みつつ、猶予期間を長く設ける、指導・相談の機会を設ける、などの対応策をとらないと国民の心とスキルはついてこない。ITが苦手な人が「取り残されない」ことが大切だ。私たちとしては、正しい情報の取得と理解が必要なのは言うまでもない。疑問や意見は、総務省のサイトにある「マイナンバー総合フリーダイヤル」などで一つずつ解決していくのがよいだろう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」