
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
日本時間2017年1月1日午前8時59分に挿入される「うるう秒」。影響を受けやすいのがコンピューターシステムだ。常時稼働させているサーバー類や企業のITシステムで、障害やトラブルが発生する可能性がある。特に今回、うるう秒が元旦に実施される。もし障害やトラブルが生じたら、休みで対処する要員が不足するのは目に見えている。
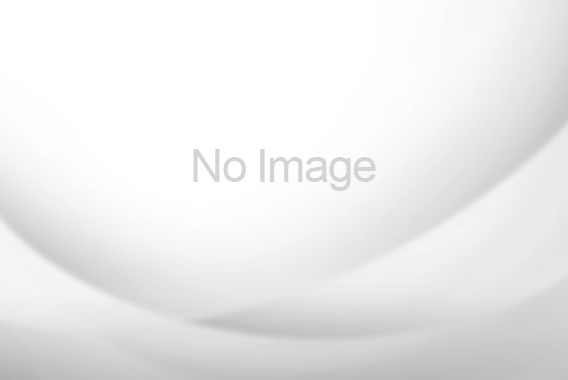 うるう秒とは、原子時計の刻む正確な時刻(原子時)と、地球など天体の動きに基づく(天体時)のずれを調整するために、タイミングを決めて1秒の追加もしくは削除が行われる制度だ。NICT・情報通信研究機構「うるう秒挿入のお知らせ」によれば、時刻はかつて地球の公転・自転に基づく「天文時」から決められていたが、1958年から原子の振動を利用した原子時計に基づく国際原子時が開始され、1秒の長さが非常に高精度なものとなった。その結果、原子時計に基づく時刻と天文時に基づく時刻との間でずれが生じるようになったという。
うるう秒とは、原子時計の刻む正確な時刻(原子時)と、地球など天体の動きに基づく(天体時)のずれを調整するために、タイミングを決めて1秒の追加もしくは削除が行われる制度だ。NICT・情報通信研究機構「うるう秒挿入のお知らせ」によれば、時刻はかつて地球の公転・自転に基づく「天文時」から決められていたが、1958年から原子の振動を利用した原子時計に基づく国際原子時が開始され、1秒の長さが非常に高精度なものとなった。その結果、原子時計に基づく時刻と天文時に基づく時刻との間でずれが生じるようになったという。
そこで、両者のずれが0.9秒以内に収まるように調整を行った時刻を、世界の標準時(協定世界時)として使うことになり、その調整としてうるう秒の挿入が数年に1回行われるようになった。
調整は、地球の回転の観測を行う国際機関である「国際地球回転・基準系事業(IERS)」が決定している。日本では、総務省およびNICTが法令に基づき標準時の通報に関わる事務を行っており、IERSの決定に基づいて日本標準時にうるう秒の挿入を実施する。
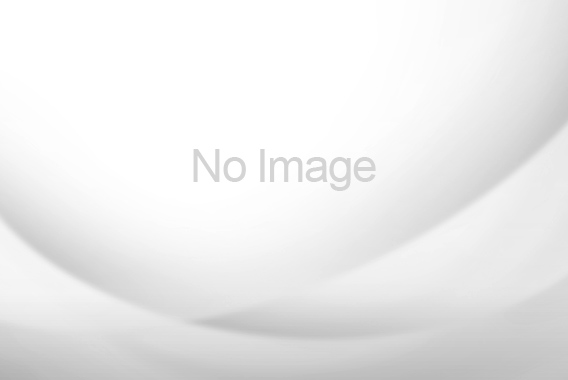 過去には1972年7月1日の第1回から、7月1日もしくは1月1日に26回のうるう秒(すべて1秒の追加)が実施された。元旦に行われるのは2009年以来、8年ぶり。この日、「8時59分60秒」が挿入され、1日の長さが1秒長くなる。
過去には1972年7月1日の第1回から、7月1日もしくは1月1日に26回のうるう秒(すべて1秒の追加)が実施された。元旦に行われるのは2009年以来、8年ぶり。この日、「8時59分60秒」が挿入され、1日の長さが1秒長くなる。
今回の場合、「2017年1月1日午前8時59分60秒」が挿入される。この普段あり得ない時刻が存在することで、各種コンピューターシステムにシステム障害やトラブルが発生する可能性がある。
基本原理は、コンピューターがあり得ない時刻を書き込もうとして、または探しにいって、帰ってこなくなる。人間なら「あり得ないからやめよう」と思ってやめることもできるが、機械は果てしなく処理を続けてしまう可能性がある。結果、高負荷になり熱暴走、システム停止、ハードウエアの破損をはじめ、思いもよらない障害につながる。
2012年7月1日に行われたうるう秒では、主にLinux OSを積んだサーバーに障害が発生し、au、mixi(ミクシィ)をはじめ、世界中のインターネットサービスで障害が発生した。前回の2015年7月1日は、うるう秒対策でエンジニアやSEなどが待機していたため、大きなトラブルは発生しなかったといわれている。
ところが今回、久しぶりの元旦のうるう秒。さらに、インターネットやスマートフォンの普及で、さまざまな情報処理をクラウドサービスに頼る世の中、1つのサーバー、1つのサービスの小さなトラブルが、大人数を巻き込んだ一大事につながる可能性もなくはない。NICTでも11月1日に「うるう秒実施に関する説明会」を行い、理解と正しい運用促進を目的に、改めて注意喚起を促した。
4年に一度、2月末に挿入される定期的な「うるう年」とは異なり、うるう秒は天文観測結果を見ながら不規則に挿入される。それ故、システムの設計や構築段階からの対応は難しい。対症療法的にならざるを得ず、トラブルも生じやすい。
余計なトラブルを増やさないため、止めても支障のないサーバーや社員のパソコンなどのIT機器は、できる限りシャットダウンしておく。あと、スマートフォンなどのモバイル機器にもトラブルが波及する可能性がある。注意しよう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」