
脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)
"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り
公開日:2025.07.16
文書作成や表計算、プレゼン資料の作成など、ビジネスにもプライベートにも必須、ともいえるMicrosoft「Office」。最近はサブスクリプション形式の「Microsoft 365」に移行しているユーザーも多いが、なお買い切り版を使い続けている人は少なくない。ここで一度確認してほしい。あなたのOffice、いったいどのバージョンだろうか。
というのも、Office 2016とOffice 2019のサポートが、2025年10月14日に終了する(リリース記事「Office 2016とOffice 2019のサポート終了」)からだ。「まだ数カ月ある」といった見方もできるが、すべてのパソコンを確認して、適宜対応を行うことを考えると、安全第一、早めの対策が吉と思う。
現実的な対応策はふたつ。最新版の買い切り版「Office 2024」に乗り換えるか、サブスク版の「Microsoft 365」に切り替える。なお、他社製でOfficeと互換性があるアプリに乗り換える手もあるが、互換性や操作性の違いを考えると、かなりの手間とリスクが伴うので、あまりおすすめはできない。
バージョンの確認方法は、Officeを開き、「ファイル」→「Officeアカウント」と進むと「製品情報」に記載されている。筆者のパソコンにインストールされているのは「Office 2021」だったが、これも発売から5年後の2026年10月にはサポートが終了する運命。つまり、買い切り版はいずれにせよ"その日"は確実にやって来るので、それ以前に対策が必要、ということだ。
また、パソコンにプリインストールされていたOfficeが今回の対象である場合、パソコン自体がWindows 10である可能性も高いので、ついでにWindowsのバージョンも確認しておこう。ご存じの通り、Windows 10も2025年10月にサポート終了予定。これに関しては本連載「Windows 10が2025年10月14日にサービス終了、今できる対策は?」で触れているので参考にしてほしい。もし、パソコンがWindows 11にアップデート済みなら、Officeだけ買い換える選択もありだが、単体購入は高コスト(例えば、先ほど触れた「Office Home & Business 2024」なら4万円台)。それならばいっそ、Windows 11+Office 2024を搭載した新パソコンへの買い替えのほうが、周辺環境の設定や各種の調整なども考えると結果的にコスパがいい可能性もある。
このあたりの判断は、次に紹介する買い替え以外の代替案も踏まえて、じっくり検討するのが賢明だろう。特に、パソコンやソフトウエアをまとめて導入している企業や団体の場合は、コストも手間も跳ね上がるため、間際で慌てて選択を間違ってしまっては大変だ。そうなる前に、OSとOfficeのバージョン確認から、始めておくのが得策だ。
サポートが切れたOSやアプリは、例えばかつてのInternet Explorerのように突然起動不能になるといったことが起こるわけではない。見た目は変わらず動作し続ける。ただし「動く=安全」ではないのが落とし穴。Microsoftの告知ページにも明記されているとおり、「Office 2016アプリとOffice 2019アプリはすべて引き続き機能します。ただし、深刻な問題を引き起こす可能性のあるセキュリティリスクにさらされる可能性があります」「脆弱性に関するテクニカルサポート、バグ修正、またはセキュリティ修正プログラムを提供しなくなり、その後報告または検出される可能性があります」。つまり、今後新たに発見された脆弱性が放置され、ウイルスやマルウエアの標的にもなりやすくなる、というわけだ。
ランサムウエアなどの攻撃は、決して大企業だけの話ではない。最近は中小企業や地方の医療機関が狙われるケースもある。無防備な状態で放置されたソフトは、言ってしまえば格好の"踏み台"だ。さらに、告知ページには「電話やチャットによるテクニカルサポートは受けられなくなる」「ヘルプコンテンツも更新されず、順次削除される」とあり、更新プログラムが提供されるだけでなく、いざというときに頼れる手段を失う、そんな孤立無援の状態に追い込まれる。これはゆゆしき状況だ。
こうした背景から、サポート終了後のソフトは"使える"とわかっていても、"使ってはいけない"ととらえるべきだろう。会社や団体で多くのパソコンを管理している場合、「誰が、どのパソコンで、どんなソフトのどのバージョンを使っているのか」を正確に把握し、適切にアップデートを行っていくのがセキュリティ管理上の1つのカギともなる。しかも、ソフトウエアだけでなく、ハードウエアのサポート期限なども常にチェックしておく必要がある。安全対策上、どこにどんなリスクが潜んでいるか、常に監視する必要があるからだ。それには手間もコストもかかる。でも今は便利な管理ツールもある。次に、それらの活用法について紹介しよう。
IT資産管理の強化を図るうえで、心強いのが「IT資産管理ツール」といわれる。Web検索をしてみるとさまざまな製品が見つかるが、一般的には「IT Asset Management Tool(ITAMツール)」と呼ばれ、企業や団体が保有・利用するIT資産(ハードウエア、ソフトウエア、ライセンスなど)を一元的に管理・最適化するシステムをさしている。
具体的には、ハードウエアやソフトウエアの更新時期の管理、ライセンスの適正数の把握、余剰や不足の防止によるコスト最適化などが可能になる。また、操作ログやアクセスログを収集して内部監査などに活用したり、無許可デバイスの接続を検知・遮断したりするなど、セキュリティ機能を統合している製品も多い。
導入したら、まずはIT資産管理台帳を作成して資産状況の「見える化」を行う。どの資産がどこにあり、いつ購入して何年経過したものか、いつどんな更新が必要かを明確に把握できるようになる。加えて、更新プログラムやセキュリティパッチ、ファームウエア、ドライバーなどの管理機能を活用して、セキュリティ上のリスクを軽減しつつ、必要なアップデートを適切なタイミングで実施する。ネットワーク機器の一元管理が可能なのも注目点だ。プリンターや複合機、NAS、ルーター、ハブなどの稼働状況の可視化、トラブルの早期発見、対応にもつながる。こうした適切なIT資産管理は、コスト面だけでなく、セキュリティ確保にも大いに貢献する。
IT資産管理ツールの提供形態は大きく分けて「クラウド型(SaaS)」と「オンプレミス型(自社導入)」の2種類がある。クラウド型は導入が迅速で初期コストが低く、常に最新機能が利用可能。リモート管理との相性も良く、メンテナンス不要といった利点がある。その反面、ネット環境に依存するため、通信障害時の管理が困難、ベンダー依存のため、情報漏えいなどセキュリティが懸念される、長期的なサブスクリプションでコストが膨らむ可能性がある、などのデメリットも。この一方、オンプレミス型は高いカスタマイズ性とセキュリティの自主管理が可能で、長期的にはコスト面で有利となる可能性が高い。しかし、初期導入時のコストや時間・手間がかかる、自社での保守・運用負担が重い、リモート管理が難しい、などの課題もある。
一刻も早く導入したい状況や、テレワークの多い環境、社内にITインフラが少ない場合はクラウド型、セキュリティ重視で独自業務の多い企業ではオンプレミス型が向いている。いずれにせよ「IT資産管理ツール」の導入により、サポート終了済みのソフトウエアやハードウエアの放置、違法なIT資産の使用などのリスクを未然に防げる。未導入の企業は、トラブルや信頼損失を防ぐうえでも、早めの導入を検討したいところだ。
Office 2016のサポート終了に代表されるように、ITシステムの保守切れは、企業にとってセキュリティリスクとなり、ランサムウエア被害など、重大な問題を引き起こすリスクがある。対策としては、自社内で先述の「IT資産管理ツール」を導入・活用するのが基本だが、実際にはその運用を担える人材が足りず、管理が行き届かないケースも少なくない。
そんなときに有効なのが、IT資産の管理業務そのものを外部の専門家にアウトソーシングする方法だ。近年では、パソコンをはじめとするIT機器一式をリースやレンタルにし、資産管理、セキュリティ管理、システム保守までを含めたトータルサポートを外部に委託するスタイルも注目を集めている。
具体的には「IT機器のフルアウトソーシング(導入・管理・更新のすべてを委託)」「マネージドサービス(MSP。システムの運用・保守・監視を委託)」「ITアセットマネジメント(IT資産管理業務を委託)」「デバイス・アズ・ア・サービス(DaaS)」「IT機器のレンタル・リース契約」など、さまざまな形態がある。これらを活用することで、初期投資不要、IT部門の負担軽減、最新機器の安定利用、セキュリティの一元管理、安全な廃棄処理などのメリットが得られるだろう。
もちろん、長期的なコスト増の懸念、外部業者依存による柔軟性の欠如、トラブル対応の遅れ、セキュリティ責任の曖昧化、などといった懸念もあるが、自社の規模や体制、目的に応じて適切なサービスを選ぶことで、リスクを抑えながら安定的なIT運用が可能になることと思う。
その中でも近年注目を集めているのがデバイスのライフサイクル全般をサービスとして提供する「デバイス・アズ・ア・サービス(DaaS)」だ。企業がデバイスを所有することなく、サブスクリプションで利用でき、デバイス導入から保守・管理、修理対応・代替機貸し出しサービス、セキュリティ対策、設定・インストール・更新、データのバックアップ・移行、AI分析によるIT支出管理などが可能、それに加えてヘルプデスクやサポートなど幅広いサービスを受けられる場合が多い。最近では、大手ITベンダーやサービスベンダーによる包括的なサービス提供が進み、品質や利便性も高まっている。内容はサービスごとに異なるので、よく確認する必要がある。IT資産管理ツールの導入とあわせて検討するとよい。最寄りのベンダーやWeb検索、公的な相談機関の活用などを通じて、自社に合った管理体制の構築を検討したい。
今回のテーマはOfficeのサポート終了だが、これらのアップデートはもちろん、これを機にソフトウエアの更新だけでなく、IT資産全体の所有と運用のあり方を見直す機会としてとらえよう。効率と安全を両立する新たなスタイル、明るい未来のためにぜひ今こそ見据えておきたい。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
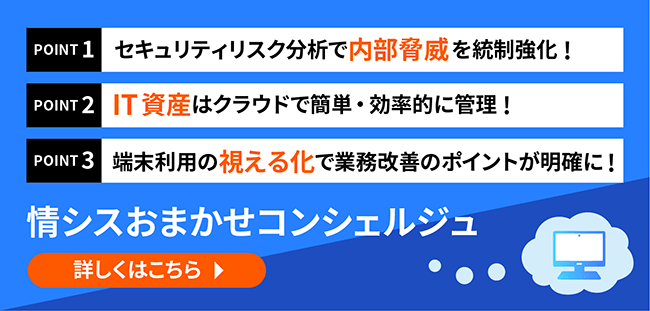
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」