
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
米グーグルが10月23日(現地時間)、量子コンピューターの「量子超越性」を実証したと発表。論文は英ネイチャー誌に掲載された。世界最高のスーパーコンピューターで1万年かかる計算を、たったの200秒で解いたという。量子超越性とは、量子コンピューターが従来型のコンピューターを追い越し、成り代わるニュアンスだ。
このニュースで世界は騒然となり、IBMの反論(後述)も話題になった。中でも大きく取り上げられたのは、ビットコインの価格の急落だ。以前から量子コンピューターがビットコインを滅ぼす、といわれていた。実際、グーグルの発表を受けて、ビットコインは約5カ月半ぶりの低水準となった。
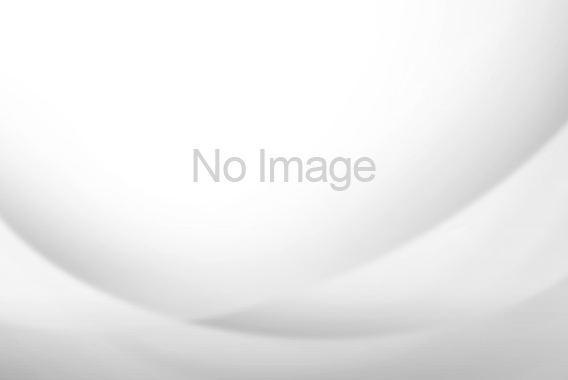 従来のコンピューターは、情報をオン(1)とオフ(0)のいずれかを表す「ビット」を基本単位とし、0と1で構成された2進数ですべての計算をする。これは電圧のオン・オフを切り替えて行われる。現在、コンピューターで扱うテキストも写真も音声も動画も、すべてのデータが0と1でできている。
従来のコンピューターは、情報をオン(1)とオフ(0)のいずれかを表す「ビット」を基本単位とし、0と1で構成された2進数ですべての計算をする。これは電圧のオン・オフを切り替えて行われる。現在、コンピューターで扱うテキストも写真も音声も動画も、すべてのデータが0と1でできている。
こうした従来のコンピューターは一度に0か1、どちらかの値1つしか示せない。だが量子コンピューターは、量子力学という物理の力を利用し、値を「重ね合わせ」、同時に2つ以上の値を表せる。飛躍的にポテンシャルの高い計算が可能となるというのだ。
かつてスーパーコンピューターで行っていた計算が、今はスマホでできてしまう。ただし、0と1のビットで表す基本原理には変わりはない。量子コンピューターの登場で、とんでもない革新が起きる。
今回、最先端の従来型スーパーコンピューターで1万年かかる計算を、グーグルが開発した53量子ビットを持つ「Sycamore」(シカモア)プロセッサーは、200秒で計算した。この計算力は天文学的というか、想像を絶する値だ。
例えばこのところ、社会に普及しつつあるAI。囲碁やオセロで人間を打ち負かすが、ビッグデータを分析して未来を描き出したり、近々起こる災害を予測して被害を未然に防いだり、学習や経験を積み人間の代わりになったりするには、今のコンピューターでは追い付かないといわれている。さらに、IoT、高精細・高ビットレート方向のメディアの現況を考えるに、従来のコンピューターでは性能が頭打ちな面もある。
そこで注目されるのが量子コンピューターだ。理論が発表された80年代以降、米国、中国、EU、日本などがこぞって開発を行ってきた。今回のグーグルの発表に期待が高まらないわけはない。
そもそもビットコインをはじめとする仮想通貨は、ブロックチェーンという全取引が記録されたデータベースで管理されている。これらのデータは、公開鍵と秘密鍵で暗号化され、現在のコンピューターではめったなことでは破れない、とされていた。ところが量子コンピューターの計算力をもってすれば、仮想通貨の暗号鍵はあっという間に破られる。その懸念が暴落につながったと思われる。
一方、グーグルの発表にIBMは、「1万年かかる計算」は大げさで、IBMが最先端のスーパーコンピューターで行ったシミュレーションでは「2日半」とし、量子超越性とまではいかない、とブログで述べた。
そもそも量子コンピューターは、n量子ビットなら2のn乗の状態が同時に計算され、2のn乗個の重ね合わせた結果が得られる。ただしこれだけではランダムに選ばれた結果が1つ得られるだけ。欲しい答えを求めるには、答えを高確率で求める工夫を施した、量子コンピューター専用のアルゴリズムが必要だという。
たとえ1万年かかる計算が200秒でできたとしても、量子コンピューターはアルゴリズムを与えた上での決まった問題を高速に解くマシンにすぎない。例えばビットコインの暗号鍵を解くならば、それに特化したアルゴリズムを与えなくてはならない。こうしたアルゴリズムの開発には、膨大な手間がかかる。今回のグーグルの発表が、すぐに量子コンピューターの実用化にはつながらない、とみる人も多い。
量子コンピューターはグーグル以外でも開発が行われている。用途に特化したアルゴリズムのチップも、開発されつつある。だが、まだまだ実用的なレベルではない。
IBMのブログでは、量子コンピューターが社会にプラスの影響を与えるには、アルゴリズムやプログラムを確実に実装できるシステムの構築と作成を、勢いを維持しつつ継続するのが大切だと書かれている。今後の発展が望まれるところだ。
グーグルの発表があったものの、現時点では量子コンピューターが従来型を駆逐する可能性はなさそうだ。量子コンピューターは、性能は飛躍的でも、専門性の高いものだからだ。
汎用性の高い従来型のコンピューターは、パソコンやスマホ、ウエアラブルデバイスやスマート家電といった生活に欠かせないインターフェースとして、人々に使い続けられていく。汎用的なWebサイトやサーバーも、従来型のコンピューターで継続していく。そこに、機械学習やAI、未来予測や災害予測、医療のための計算などに特化した専用の量子コンピューターを動かして、従来型と量子型のハイブリッドになると筆者は考える。量子コンピューターの今後に注目したい。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」