
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
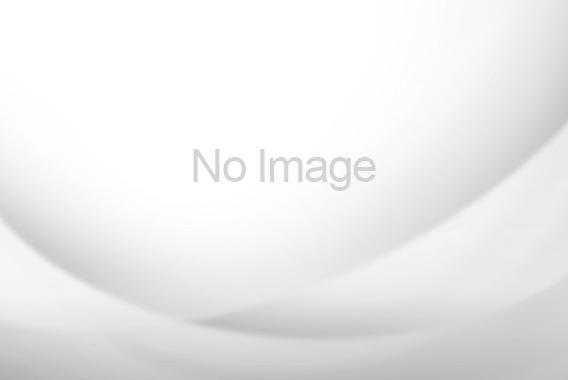
2022年6月7日、デジタル庁の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定された。この計画は「デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策等を定めるもの」および「デジタル社会の実現の司令塔であるデジタル庁のみならず各省庁の取組も含め工程表などスケジュールとあわせて明らかにするもの」とされている。
2021年9月1日、日本のデジタル社会実現の司令塔として発足したデジタル庁だが、今回の重点計画は、2021年12月24日に策定した重点計画をアップデートしたもので、「目指すべきデジタル社会の実現に向けて構造改革や施策に取り組むとともに、それを世界に発信・提言するための羅針盤となるもの」という。
デジタル庁が発足して10カ月を迎える現状、マイナンバー制度やガバメントクラウド、ワクチン接種記録システムなど、デジタル庁が行ってきた政策は、デジタル庁「政策」ページから一覧できる。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の全体を眺めるには、「資料」の「概要」がおすすめだ。計画では、我が国がめざすデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を掲げ、デジタル庁発足時からの「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」につなげる。
「目指す社会の姿」を実現するため、「デジタル化による成長戦略」「医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化」「デジタル化による地域の活性化」「誰一人取り残されないデジタル社会」「デジタル人材の育成・確保」「DFFT(Data Free Flow with Trust)の推進を始めとする国際戦略」の6つを求める。これらの進捗は、国民や民間企業の満足度や利用率などを定期的に把握し、国民に提示することで、デジタル化を着実に推進していく方針だ。
デジタル庁が司令塔となり、国・地方公共団体・事業者と連携・協力しながら、デジタル社会の実現に向けた構造改革、サイバーセキュリティ等の安全・安心の確保、国民に対する行政サービスのデジタル化、暮らしのデジタル化、産業のデジタル化などの取り組みを行っていく。その計画の具体的な工程と施策は、「工程表」や「施策集」に詳しく示されている。
なお、この計画において、「『誰一人取り残されないデジタル社会』の実現に向けては、どのようなことを期待しますか?」「日本でスタートアップ企業が創出され、成長していくためには、どのようなことが必要だと思いますか?」などのテーマであらかじめ意見を広く募集し、寄せられたのべ800件の意見が取り入れられているという。こうして国民の声を政策に取り入れる姿勢は、なかなか好感触でもある。
2022年4月26日、自民党の「デジタル社会推進本部」による「デジタル・ニッポン 2022~デジタルによる新しい資本主義への挑戦~」がリリースされた。「デジタル・ニッポン」とは、2010年から毎年、民間から幅広く知見を集めながら、自民党がデジタル施策に関して具体的な提言をしてきたものだ。
「デジタル・ニッポン2022」は、岸田内閣がめざす「新しい資本主義」に対して、デジタルの側面からアプローチし、必要な施策を提言するものと位置付けている。提言は、「足元を固める」「変化を捉える」という2つの方策から「誰もが成長と幸せを実感できる持続可能な社会」というゴールに向かう構造となっている。
「足元を固める」アプローチでは、2022年4月に700人体制となったデジタル庁に対し、同様の機能を担う欧米の組織では少なくとも2~3000人は備えているとし、今後、司令塔として膨大な数のプロジェクトを同時進行でこなすために、ピラミッド型組織を超えた管理手法の導入や官庁の仕組みを超えた人材育成手法を導入すべき、と提言する。
なお、連載でも取り上げた、米国メガクラウド企業のパブリッククラウドをベースとする「ガバメントクラウド」について、情報の機密性の高いデータは「セキュリティを強化したクラウド」で扱うなどの対応を行うべきとし、国産サービスの積極採用を提言。これに対してデジタル庁の牧島大臣は「マルチクラウド」という言葉を使い、どのようなレベルの情報をどのようなクラウドで管理すべきか検討していく、と発言している。
しかし、政府発表の計画を眺めるにつけ、「多様な幸せが実現できる社会」に向けてはいくつも課題がありそうだ。なぜなら、残念なことに、デジタル関連の不祥事も相次いでいるからだ。その多くは、基本的なITリテラシーと注意深さがあれば防げたのではないだろうかと感じる部分も大きい。
国民の側にも、ITスキルの格差が存在している。ちまたでは「テクハラ」(「テクノロジーハラスメント」)なる言葉が生まれ、職場などでITの知識が乏しい人や、パソコンやスマートフォンなどのIT機器を苦手とする人への嫌がらせ等が問題となっている。逆にITが苦手な人が得意とする人に、IT関連の仕事を押し付ける「逆テクハラ」が問題となるケースもある。
以前の記事でも触れたが、昨年の「デジタルの日」に公開された「DX白書2021」は、「日米比較調査にみるDXの戦略、人材、技術」という内容で、我が国のDXの遅れを浮き彫りにしている。だが、欧米諸国に追い付こうと焦るよりも「急がば回れ」の精神で、一人ひとりのITリテラシー向上とセキュリティ意識の醸成を図っていくことも必要だろう。各種の計画が”絵にかいた餅”にならないよう、デジタル庁の今後に注目したい。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」