
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
スマートフォン(スマホ)の爆発的な普及で、ほとんどの人がスマホなしでは考えられない生活を送る昨今、タブレットに元気がない。スマホと組み合わせる機器といえばタブレット、という常識が崩れてきた。一方、仕事や趣味での込み入った作業は相変わらずパソコンが根強い。スマホと組み合わせて使う、第二の機器は何にすべきか。イマドキの選択術を解説しよう。
スマホはコンパクトでどこでも持っていける半面、コンパクト故に画面表示できる情報が限られる。指で操作する作業にも限度がある。バッテリーも小さく電池が持たない。そんなスマホの欠点を補う端末、ということでタブレットは脚光を浴びてきた。筆者も居間でくつろいで多くの情報をチェックしたいとき、カフェなどでゆっくり情報を読みたいときのためにタブレットを入手した。一時期は、スマホとタブレットがあればもう何も要らないと思っていたほどだ。

少し前の小さめタイプのスマホなら、ミニタブレットとのサイズ差が大きく、タブレットはスマホの小ささを十分に補えた(写真はNexus 7とiPhone 4s)
これまで筆者が所有し愛用してきたiPad miniやNexus 7となど液晶画面が7~8インチサイズのミニタブレットは、以前ほど注目されなくなってきている。
2014年後半あたり、iPhoneのメーン機種のサイズが5sまでの4インチサイズから、6以降、4.7インチ/5.5インチ(現行でいけば7/7 Plus)という、大きめサイズに変わった。ちまたを眺めると、その頃を境にiPhoneもAndroidも5~6インチのサイズが主流になった。
4インチ以下の小さいスマホを使っていたときは、スマホとタブレットのサイズ差が大きかったが故に、持ちやすく画面が見やすいミニタブレットを併用する意味は大いにあった。ところが大きめサイズのスマホだと、7~8インチのタブレットとサイズ差がなく、ミニタブレットで補う意味がなくなってしまったともいえる。
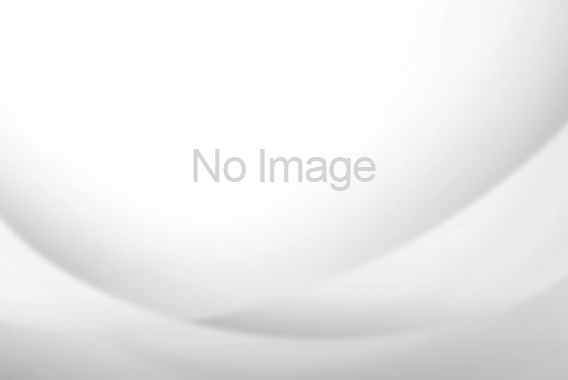
最近のスマホとミニタブレット。こうなるとサイズ差はほとんど感じられない(写真はNexus 7とg07)
ならばもっと大きい9インチ以上のタブレットなら、スマホの弱点を補えて趣味や仕事もはかどるか、と誰しも考える。確かに12.7インチのiPad Proなどは、大いに魅力を感じる。ここまで大きいと差別化は十分図れるし、ペンデバイスも使えるので、いろいろ使いようはありそうだ。ところがそのアップルさえも、タブレットの売り上げがガクンと落ちているという。
2つ目の持つべき端末を思案するにつけ、自分がやりたいこと、実現したいことは何なのかをよく考えたい。スマホはおおむね、情報チェックや身近な情報管理とコミュニケーションが一般的な用途だが、それ以外の「やりたいこと」は人それぞれだ。
例えば、オフィスソフトで書類を作りたい、設計図やプログラムを書きたい、イラストを描きたい、写真を加工したい、Webページを作りたい、文章を書きたい、ビデオや映画、音楽を作りたい、ハイスペックゲームを楽しみたい、と多岐にわたる。
利用シーンも考えたい。自分の部屋のみで腰を据えて使いたい、家の中のあちこちで使いたい、通勤中に使いたい、いつでもどこでもあらゆる場所で使いたい、などいろいろある。そんなふうに考えていくと、スマホが大画面&高性能になってきた今、スマホと組み合わせるべきは「スマホに毛が生えた程度の端末」ではダメだ。
やりたいことを実現する端末には、それなりの装備が必要だ。文章作成にはキーボードがほしい。高度な作業には大画面・高精細なモニターが欠かせない。絵を描くなら筆圧対応パネルとペンデバイスが考えられる。さらに、対応アプリがあるか、複数のウインドーを開いての作業が可能か、複雑な作業や重い処理に耐えうるスペックを備えているか、などもポイントになる。
今注目なのは、デタッチャブル、コンバーティブル、2-in-1などと呼ばれる、必要に応じてキーボードを備えたノートになったり、タブレット方式でも使えたりというフレキシブルに形を変えられる端末だ。スマホに比べ、画面が大きく、バッテリーも大型。処理能力も高めで、使い分けもしやすい。例えばレノボのYOGA BOOKとASUSのTransBookシリーズが挙げられる。両者ともAndroidとWindowsタイプを備えているが、高度な作業を行いたいなら、やはりモバイルOSよりもパソコンOSかな、と思う。
ほかに筆者が注目するのは、Chromebookだ。動きが軽く、電池の持ちが抜群で価格が安いのが特徴だ。昨年からAndroidアプリも動くようになり、静かな人気を博す。
ネットでおおよその当たりを付け、店舗で端末を実際に見たり、店員さんに相談したりしてみよう。あなたに合った最良の端末を入手できるはずだ。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」