
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
最近よく聞くのは「AI面接」という言葉。とある大手企業が一次選考に「AI面接」を採用する、というニュースが昨年、話題にもなったのは記憶に新しい。調べてみると、最近の採用システムにおいては、AIが面接官としてパソコンやスマホなどの画面を通して、応募者とやり取りを行うことも多いそうだ。
これらは基本的に、採用担当などの「人間」が画面越しや傍らなどでAIとのやり取りを聞いて判断を行うわけではなく、あくまで応募者とAI(が装った人物)が対話して応募者とAIのコミュニケーションで面接が完結する、という話である。
これまで、「面接」といえば今までは「人間同士」で行ってきた。大抵の場合、面接室に入ると、人事担当や役員など会社側が数人、顔を並べていて、応募望者はその前に置かれた椅子に座り、自己紹介したり、質疑を受けたりする姿を想像する読者も多いはず。もちろん履歴書などの書類はすでに提出され、場合によっては試験なども行われていて、いわば最終決定するための手段、という認識であることも考えられるだろう。
人間相手ゆえ、面接時には相手の表情や顔色などをよく見る必要があるし、応募者も態度や見た目を整えて臨む必要がある。最初は互いに緊張しているが、ある一言で緊張がとけて話が盛り上がったり、深い話にもなったりする。こうした中で、やはり面接のやり取りがうまくいかないと採用には至らない、というイメージがあるだろう。そんな会社側の人材確保にも、応募側も人生や生活にも、その多くを左右する重要な「面接」が、いまや「AI相手」に行われる、という話だ。
少し見聞きしただけでは「そんな重要なことをAIまかせにしていいの?」という気持ちにもなる。ちなみに、面接を行うAIを「AI面接官」と呼ぶというが、その言葉もよく耳にするので、試しに「AI面接官」で画像検索すると、ロボット相手の面接だったり、AIっぽい人物を映す画面上で面接を行う画面が表示されたりで、まるでSF映画の一場面のようだ。
とはいえ、採用側と応募側の将来を大きく左右する最終段階の面接までを「AI面接官」が行うわけではない、というのは容易に想像がつく。AIとの面接のデータをもとに、人間が最終選考や最終面接を行うのは、生成AIが発展途上である今のところ、当然ではあろう(ただし、選考の初期や中途の段階でAIとの面接を行い、生成AIの高い分析力により候補者を絞ることができれば、人事・採用担当の手間やコストが省けそうだ)。
Web検索してみると、AI搭載の「採用管理システム」がたくさん見つかり、中には数百社の採用実績を誇るものもある。さらにはこれらのサービスの機能を比較するサイトがいくつもあったりするので、注目のジャンルであることがわかる。
こうしたAI搭載システムでは主に「応募者とのマッチング」「書類選考の効率化」「初期段階の面接」をAIが行うという。「応募者とのマッチング」とは、応募者の情報から必要事項をピックアップし、採用条件に合致しているものを選別する初期段階の作業だ。「書類選考の効率化」とは、条件に合致した応募者の履歴書など応募書類の情報や採用試験の結果などのデータを分析し次の段階に進む応募者を絞り込む作業、「初期段階の面接」とは、AIを用いたビデオ面接を行うことにより、応募者のコミュニケーション能力や性格などの分析を行う、といった具合らしい。
AI搭載の採用管理システムでここまで行っておければ、あとはほぼ最終面接や最終判断のみ、となり、人事担当者の負担を大幅に減らせるのは一目瞭然だ。さらには、先述の人間の目や価値判断による偏りを減らし、公平公正な評価基準による選考を行える。また、自社としてほしいスキルや資格を有した応募者情報を簡単に見渡すことができ、面接などの日程調整が自動化できる。さらに、選考の進捗状況がリアルタイムで確認できるなどの利点もあり、人材不足の今の世の中にはかなり助かるシステムとも言えて、盛んに開発、導入されている理由も大いに納得でき、なかなか興味深い話ではある。
「AI面接官」は、最終選考ではなく初期・中途段階での面接に使われるらしい、ということが調査を進める中でわかってくる。一般に、AI面接には2種類あるとされる。1つめは「AIが自ら面接を行い、その結果を分析するタイプ」だ。AIが面接官として応募者の回答に応じて質問やアプローチを変えつつヒアリングを行い、応募者の資質を見極める、というもの。生成AIとリアルタイムで会話をしつつ、知りたいことを知る、推論させる、提案させる、文章などを作る、などが当たり前になってきている今日このごろでは、AIが初期段階の面接ぐらいには十分対応できそうなのは容易に想像できる。
2つめは、「AIが面接データを分析するタイプ」。AIで作成したアバターなどを相手として、事前に決められた質問に答えた対面での会話内容を録画し、その動画データや会話内容をAIが分析して公平公正に評価を行う方法だ。動画やテキストの詳細なる分析はAIにとっては得意分野である。というわけで、2つの形式、どちらも甲乙つけがたくはあるが、今どきの流れとしては、前者がタイムリーかもしれない。
多くの採用管理システムでは、書類選考から一次面接の日程調整、実施、評価などのほとんどをAIが対応できるという。2タイプのどちらでも、面接後、社会人としての基礎力、コミュニケーション能力など多数の項目を分析して評価、リポートを生成することなどで、効率的に行程が進められる。そして、人間はそれらのデータを見渡して判断し、最終面接を行い決断する、などの手順となるケースが多いだろう。
こうした「AI面接」を使うメリットは、効率的な採用活動の実現や、採用担当者の負担軽減の他、先述のように「担当者の感情や偏見に左右されず客観的で公平な評価が行える」「人間では聞き出しにくい部分まで深堀りした質問を行うことによる面接の質や精度の向上」「応募から面接までをオンラインで応募者の好きな時間に行えるため広いジャンル、環境、場所からの採用が可能」などがある。そのうえ、回数を重ねるにつれ、採用活動のデータも蓄積し、さらなる分析による精度向上も可能だ。場合によっては、内定辞退や早期離職などのリスクも軽減できるという。
デメリットとしては、AIの評価基準やミスに対する懸念が一番大きいだろう。これはAI利用につきものだが、「AIの誤りを人間がどう見分けるか」という問題は常につきまとう。さらには、応募者のほとんどがAI相手にやり取りを行うため、会社側の人間とのコミュニケーション不足や、ITベースゆえのシステムトラブルやセキュリティのリスク、AIとのやり取りにおける倫理的な問題(個人情報の扱い、差別の可能性など)などが想定される。
なお、近頃ではAI面接官対策ツールが普及し、応募者がAI面接に対する対策や練習を当たり前に行ってくる状況である点も見過ごせない。応募者側が「AI面接」対策としての「技」を身につけ一律にレベルが上がってしまうと、それらへの対策も行わないと、本当に欲しい人材を見つけにくくなる事態も想定される。応募者はITネーティブ世代が増加し、今後、システムと応募者の「いたちごっこ」が繰り広げられる可能性もある。こうした懸念も頭に入れておこう。
ただ、「AI面接」システムは、先述のリスクを考えても、導入する利点は大きいだろう。Web検索での表示件数などで分かる「勢い」が、それを物語っている。人材不足に悩む企業担当者の負担軽減や、採用コストの軽減はもちろん、今後のデータの蓄積や学習、生成AIのさらなる発展などで「AI面接官」がさらに進化し、熟練の採用担当者のような働きぶりが期待されるからだ。
システム導入においては、最終的には「自社で必要とする人材が末永く確保できるか」という目的を忘れずに心にとどめておきたい。そして、便利なツールに振り回されることなく、譲れない部分はあくまで人の力で行う、などの強い意志と姿勢が大切だ。企業も応募者も、あくまで「人間」であることを忘れず、互いを尊重しなくてはならない。
先ほど触れた、「AIの評価基準やミスに対する懸念」に対しても気を緩めてはいけない。最先端の「Deep Reserch」や「Deep Thinking」システムに至っても、ひょんなところで、どこから引いてきたか分からない虚偽のデータが出力される事実を筆者は時たま目にする。情報源や考えの道筋が分かればまだ正せるものの、AIの「ハルシネーション」(AIが学習データに含まれていない情報を生成したり、事実と異なる出力を行ったりすること)問題もいまだ解決していない。
AIのハルシネーションに対しては現状、決定的な対策もない状態なのが困りものだ。AIの答えは100%正しいものではない、と常に認識し、結果だけでなく、書類や面接の記録などの元データにも一通り人間が目を通し、最終的には人間が判断するよう、心がける他ない。
ちなみに、最先端のAIに「AIの間違いはAIが見つけられるか」と質問したところ、現時点ではそうした技術はなく、あくまで人間が行うべき、という答えが返ってきた。さらに「AI はあくまでも人間の作業や生活をサポートするツールの1つとして捉え、人間によるチェックと修正を組み合わせて活用することが重要」と、AI自身が語ってきた。便利なツールは積極的に活用すべきだが、道具に「使われて」はいけない。業務を見える化してAIなどで効率化できないか分析し、あくまで導入の際は、ベンダーなどとよく話し合って、想定されるあらゆる事態にあらかじめ対策のもと、本来の目的を忘れず、明るい未来を実現していこう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
【TP】
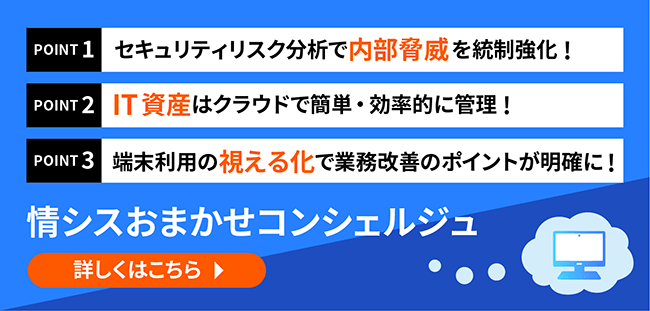
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」