
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
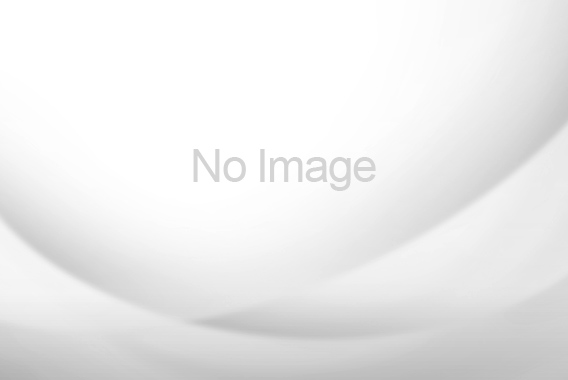
世界中で猛威を振るってきたコンピューターウイルス「エモテット」(Emotet)は1月27日、ユーロポールと欧米各国の共同作戦により制圧された。1月27日のテイクダウン(倒す、破壊する、という意味)によってサーバーを差し押さえ、メンバーは逮捕。感染端末は法執行機関が管理するサーバーとのみ通信を行うよう書き換えられた。
日本ではサイバー攻撃対策の民間団体「JPCERTコーディネーションセンター」(JPCERT/CC)が中心となり、捜査当局から提供された感染者のデータに基づき、1月下旬からISPなどと協力して、感染者への通知と対策の案内を行ってきた。
その後、エモテットは感染端末の時刻が4月25日正午の時点で停止する機能を加えた無害化ファイルで自動的に更新され、以降、感染がほぼ観測されなくなった。これが事実上のエモテットの完全制圧といえる(JPCERT/CC「マルウェアEmotetのテイクダウンと感染端末に対する通知」より)。
エモテットは2014年ごろから登場し2019年後半から猛威を振るった。偽メールを手段としたコンピューターウイルスだ。メールの添付ファイルを開くなどで、ウイルスに感染したコンピューターはマルウエアをインストールされ、情報を次々に送信したり他のウイルスの感染を広める踏み台にされたりしてしまう。
ここ最近のエモテットは日本語を巧みに使い、乗っ取ったコンピューターのアドレス帳まで盗み見て、リアルな偽メールを作成しターゲットを狙っていた。添付ファイルはそれらしい表題を付けたオフィス書類はもちろん、いわゆるPPAP(パスワード付きzipファイルをまず送り、別メールでパスワードを送るメール手法。少し前までセキュリティが高いとされ盛んに行われていた)で問題視されたZIPファイルも用いるなど、各国の世の中の流れを熟知し巧妙に利用していた。
エモテットの主たる目的は、メールをきっかけに盗んだ情報を公開すると企業を脅す「暴露型」としての活動だ(最近よく聞く「暴露型ウイルス」参照)。なお、エモテットの犯罪グループは、攻撃メールから情報の盗用までのエキスパートとして動き、その先は他の組織が担当というような、組織横断的な犯行にも絡んでいたといわれる。
サイバー攻撃とセキュリティ対策はよく「いたちごっこ」となぞらえられるが、エモテット制圧は朗報だ。ほくそえんでいる犯罪者も、明日は追い詰められる。ユーロポールとタッグを組み、徹底的に組織を追い詰め、根絶して無力化したことを現実で知らしめた。サイバー犯罪はIT機器を通じて遠隔で行うため、罪の意識は低い傾向がある。サイバー犯罪が麻薬や窃盗の犯罪組織と同様、「悪」として懲らしめられた事実を受け、その“能力”を世の中に生かすベクトルを向ける人が増えるとよい。
トレンドマイクロによれば、2019年1~6月の間に全世界で検出した脅威総数のうち、9割はメールによる脅威だった。サイバー攻撃の主な起点はメールと言っても過言ではない。そもそも偽メールは、2000年ごろから登場したサイバー犯罪の「入り口」の役割を果たす古典的な手法だ。エモテットは数ある偽メールを使ったウイルスの1つに過ぎず、エモテットの制圧後も他の偽メールの動きはとどまるとは考えにくいことを頭に入れておこう。
コロナ禍で、サイバー犯罪はさらなる増加と大規模化を呈している。国内企業では最近、富士フイルムがランサムウエア攻撃を受けた可能性で一部システムを停止したニュースが流れた。他にも世界最大級の食肉加工メーカーJBSがサイバー攻撃でライン停止、米石油移送パイプライン大手がサイバー攻撃でパイプラインが停止したのも話題を呼んだ。
この流れは、テレワークの普及でメールやコミュニケーションツールの利用増加や、コロナ禍に便乗した偽メールの台頭が原因といわれる。社員一人ひとりが自覚をもって対処していかないと、ついうっかりな操作で企業、果ては社会にまで大きな混乱や被害を招いてしまう。最近はテレワークで普及したVPNや各種ツールの脆弱性を狙う動きもある。さらに予断を許さぬ状況だ。
テレワークを導入したものの、感染対策と業務の継続に手一杯でセキュリティが後回しとなり不安を感じる企業も多い。総務省が2021年5月31日に公開した「テレワークセキュリティガイドライン第5版」は、テレワークのセキュリティ対策についてテレワークの形態別に詳しく解説している。総務省の取り組みについては「テレワークにおけるセキュリティ確保」を参照のこと。一般的なセキュリティ対策については「国民のための情報セキュリティサイト」を見るとよい。
IT機器に関しては、最新のセキュリティ対策を行い、新しい脅威の情報をいち早く入手して対処するのが一般的なやり方だ。対策に力を入れるとともに、情報の身代金を狙う組織犯罪の存在や、自分がターゲットや犯罪の入り口になる可能性を理解しよう。サイバー犯罪がターゲットにするのは「無知と無防備」だ。心強い「エモテット制圧」の現実を胸に、一層の心構えをしておこう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」