
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
Amazonは、年に一度のプライム会員大感謝祭「プライムデー」を2019年7月15~16日に行った。詳しい売上高は発表されていないものの、この2日間で注文された商品は世界で1億7500万点以上、日本でも、過去の「サイバーマンデー」および「プライムデー」と比較し、史上最大規模になったと発表した。
ネット通販は、もはや日常のものといって過言ではない。現物を手に取らないで購入する通販は、当初、抵抗のある人も多かった。ところが今は多くの人が抵抗を感じずに利用している。
通販の魅力は、いつでもどこでもあらゆるショップから物が買えて、購入物は数日で玄関まで届くところだ。筆者のように人や店の少ない地方に住む者にとっては、時間とコストの節約になる。地方では、欲しい物を散々探し回っても「ない」なんて事態も少なくないからだ。
Amazon以外に人気なのは、楽天やYahoo!ショッピングだ。ただし通販に送料は付きもの。Amazonでは年間5000円ほどの会費を払って会員になれば、基本的に送料が無料となり、動画や音楽などさまざまなサービスが利用できる。やはり一番の人気だ。
ただし、現物を手に取れない通販では、届いてから「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性がある。通販で「泣き」を見ない、よりおトクに、より目的に応じた商品を入手するにはどうしたらいいのだろうか。
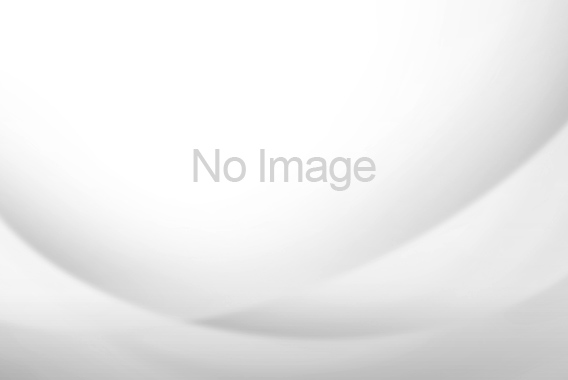 商品ページにある情報や、メーカーサイトの商品情報だけでは、商品を手に取れないデメリットは埋めにくい。デメリットを埋めるには、商品ページに記された、実際に買ったり使ったりしているユーザーの声、「レビュー」が役に立つ。
商品ページにある情報や、メーカーサイトの商品情報だけでは、商品を手に取れないデメリットは埋めにくい。デメリットを埋めるには、商品ページに記された、実際に買ったり使ったりしているユーザーの声、「レビュー」が役に立つ。
筆者も多くの物を通販で入手する。目的に応じた商品をよりおトクに入手するためには、類似の商品の比較などで十分に吟味する。ターゲットの商品は、商品情報やスペックシートに加え、商品ページに書かれたユーザーからのレビューを参考にして選ぶ。やはり実際に購入して使ってみたユーザーの意見は貴重だと思う。
だが、レビューを100%信じてはいけない。店側からお金をもらって書く「ステマレビュー」(サクラレビューなどとも呼ばれる)が横行しているからだ。筆者もついこうしたステマレビューを参考にして、商品を買ってしまったことがある。レビューの内容とは似ても似つかぬ品だった。
商品ページにずらりと並ぶレビューの中から本物の情報を見分け、より有効なチョイスを行わなくてはならない。ステマレビューの見分け方を箇条書きにまとめてみた。
(1)星5つ(最高評価)で称賛するレビュー
最高評価で称賛する内容のレビューは怪しい。最高評価ばかり並ぶ商品も気を付ける。ステマレビューが並び、そこに星1つの実際に使ったレビューが書かれると、極端に評価が分かれる。そのように評価の分布が不自然な商品にも気を付けよう。
(2)日本語がおかしい、片言なレビュー
外国の業者が、自分もしくは自国の人間を雇ってレビューを書いている可能性がある。片言な日本語のレビューは疑ってかかろう。名前が日本人のフルネーム、という場合もだ。レビューには本名を使わないケースも多く、疑ったほうがいい。
(3)ユーザーの信用度を調べる
通販サイトでは、レビュアーの名前をクリックすると、プロフィルや履歴が参照できる。履歴の評価(レビュー数や「参考になった」数など)や内容で、信頼できるレビュアーかどうか確認しよう。
(4)商品を購入していないユーザーのレビュー
例えばAmazonでは、「Amazonで購入」と表示されていれば、レビュアーがその商品を購入している。購入していないユーザーのレビューは、信頼度が落ちると見てよい。
(5)レビュー数が不自然
発売後間もないのにレビュー数が極端に多いと、ステマレビューの可能性が高い。商品の発売日とレビュー数を確認しよう。全体数があまりにも多い場合にも注意。
(6)写真付きのレビュー
写真や動画を挙げて詳しくレポートしているレビューは参考になることが多いが、写真さえ入れれば信用される、とステマレビューは考える。写真に限らず、最近はあらゆる手段で精巧に正当なレビューを装うものもある。
(7)感情的な文章のレビュー
感情的な文章には気を付けたい。ライバル商品に辛辣な内容を投稿する場合もあるが、一方的な内容の文章は信用度が低い。良い点と悪い点を冷静に説明したレビューが参考になる。
以上ざっくりと挙げてみたが、これに限らず、自分の頭と目で判断しよう。もし正当なレビューであったとしても、一個人の見方でしかない。よりたくさんのレビューを参考に、公平な判断で選ぶとよい。
なお、ステマレビューを信じて購入してしまった場合は、その旨を明記して商品を返品しよう。購入時に見分けられるに越したことはないが、ステマレビューはどんどん高度になっている。見抜く側とのイタチごっこはさらに続くだろう。
筆者の場合、辛辣なレビューに店やメーカーが誠意をもって対応し、レビュアーとのやり取りの履歴が残っていると好感を持つ。実際にそうしたレビューのやり取りを信じて商品を買ったら、親切で誠意ある対応に感激した経験もある。もしあなたが商品を提供する側だとしたら、人を雇ってレビュー欄を飾るより、どんなレビューも正直に受け入れて、誠意をもって対応してはどうだろうか。そうした正直さに、顧客はきっと付いてくる。
ステマレビューに泣くときもあれば、レビュアーの姿勢に感謝するときもある。レビューは、商品の使い心地を皆に知らせようという善意で成り立っている。ステマレビューに嘆いていても仕方ない。たくさんの玉石混交から「玉」を見分け、ネット通販をより便利なものにしていこう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」