
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
位置情報による拡張現実(AR)を活用することにより、現実世界そのものを舞台として、ポケモンを捕まえたり、バトルしたり、育成したりできる「Pokémon GO(ポケモンGO)」、任天堂の関連会社である株式会社ポケモンと、米国のナイアンティックが共同で開発したゲームだ。
スマートフォン(Android/iOS)でプレイする。基本的に無料だが、一部、課金が必要なアイテムもある。プレイにはGoogleアカウントかポケモントレーナークラブアカウントが必要。今のところ13歳未満はアカウントを取得できなくなっている。
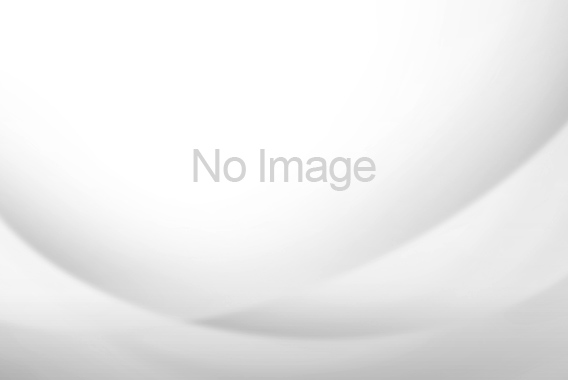
米国やオーストラリアなどでは7月6日、以後、ドイツ、英国、イタリアなどでサービスが開始され、たくさんの人々がスマートフォン片手にポケモンを探すフィーバーぶりが世界中で報道されている。
任天堂の本拠地およびポケモンの舞台でもある日本でのサービスが始まったのは7月22日の昼ごろ。心待ちにしていた人も多く、配信が始まるなり大量の人々が動き出した。政府の内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、ゲームをプレイする際の注意事項をまとめた「ポケモントレーナーのみんなへおねがい♪」を公開。一オンラインゲームに政府が動く異例の事態だ。
ポケモンGO開発元のナイアンティックは元Googleのプロジェクト。CEOはGoogleマップの参画者だ。筆者はポケモンGOと同じく位置情報を利用したナイアンティックの拡張現実ゲーム「Ingress(イングレス)」というゲームを好んでプレイしてきた(Ingressについて、筆者の記事はこちら)。
IngressはGoogleのサービスとして提供された。開発チームのナイアンティックは、もともとはGoogleの社内ベンチャーとしてつくられたナイアンティック・ラボが前身である。CEOのジョン・ハンケは、現Google EarthのKeyholeの共同設立者。GoogleストリートビューおよびGoogleマップへの参画でも有名だ。その後ナイアンティックは、2015年8月に企業として独立した。
ハンケは自分の子どもが家の中でゲームをしているのを見て、「せっかく外は晴れていて世界は素晴らしいのに、ずっと家の中にいるなんて」と思ったという。外へ連れ出すためにゲームを使うことを考え、Ingressを開発した。ポケモンGOのコンセプトもこれを継承している。
Ingressのサービス開始は2013年12月15日、緑と青に分かれたエージェント(プレーヤー)が、拡張現実世界に配置された「ポータル」を攻略して自分のチームの色に染める。目的はポータル3つを三角形としてリンク、その面積の合計を全世界で競う。
Ingressのプレーヤーが取り合うポータルは歴史的な建造物やモニュメントがあらかじめ指定されているが、プレーヤー自身がゲームアプリから申請して建立することもできる(現在、申請機能は停止、公式のコミュニティーのみが行っている)。
なぜこんなゲームの話をするかというと、ポケモンGOはIngressを応用して作られているからだ。ポケモンGOで使われる「ポケストップ」や「ジム」の場所は、Ingressの陣取り合戦で使われる「ポータル」と一致している。
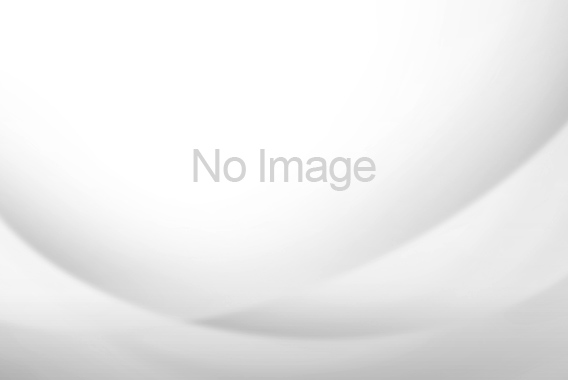
プレーヤーがアプリを起動し現実世界を歩いていくと、ポケモンに出くわす。そこでポケモンを捕まえる。それがポケモンGOだ。捕まえたポケモンは図鑑に登録され、自分のポケモン一覧にも入る。この図鑑のコンプリートがゲームの目的の1つだ。
何気ない生活空間にポケモンやポケストップの拡張現実が重なる。映画やパソコンでプレイするゲームなどでは味わえない、ARならではの楽しみがある。
地図上にはブルーのキューブが浮かぶ「ポケストップ」があり、ゲームを進める上で必要な、アイテムが入手できる。有料アイテムの「ルアーモジュール」をポケストップに使うと、30分間ポケモンを引き寄せることができ、ほかのプレーヤーも恩恵を受けられる。ルアーモジュールが有効となっているポケストップは、ピンクの花びらが舞っている。ルアーモジュールを商店などが効果的に使うことで集客効果を狙う、という効果も期待されているようだ。
ポケストップでゲットした卵は、持ち物一覧にあるふ卵器に入れてふ化させられる。卵には距離が設定されていて、設定された距離を歩くとふ化し、自分のポケモン一覧に入る仕組みだ。
このゲームを始めると、ポケモンやアイテムを集めたくて、もしくは卵をふ化させたくて、ついついたくさん歩き回ってしまう。普段の運動不足も解消できるといったところか。ポケストップで、地元の地理や歴史にも詳しくなる一面もある。ハンケの意図が世界中に伝わっていくようだ。
ポケモンを集めたり、ポケストップを訪れたりしているとレベルが上がる。レベルが「5」に上がったら、黄・青・赤からチームを選び、ジムバトルを行える。地図上に四角い舞台が表示されているのがジム。3つのチームが競って取り合いをする。ちなみに国内ではマクドナルドがこのゲームとコラボ、約2900の全店舗が、ジムやポケストップとなっている。
無所属のジム(白で表示)に、自分のポケモンを配置すると、自分のチーム(仲間チーム)のジムにできる。他チームのジムには、自分のポケモンを6匹選んでバトルを挑み、相手の名声とレベルを下げることができる。名声がゼロになるとジムは無所属になり、ポケモンを配置して自分のチームのものにできる。このように仲間のチームを強くし、ジムを攻略していくのがもう1つのポケモンGOの目的となる。
筆者はレベルが5になったので、バトルを挑んでみたが、まるきり歯が立たない。ポケモンは、強化や進化が可能。進化や強化にはポケモンの「アメ」と、ポケモンをゲットして得られる「ほしのすな」が必要となる。さらに歩いてポケモンやアイテムを集めたくなる。
以上がポケモンGOの概要と筆者によるファーストインプレッション。Google EarthやGoogleマップ、ストリートビューなどとも関連し、キャラクターの世界を拡張現実として実現するこのポケモンGO、なかなか興味深い。ブームは一過性のものか、はたまたビジネスのモデルを根底からくつがえすものになるか引き続きウオッチしていきたい。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年7月)のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」