
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
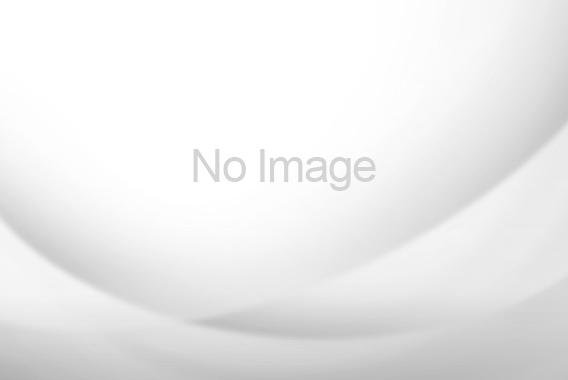
2023年1月に大手回転ずしチェーンで、少年がすしに唾液を付けるなどの迷惑行為をする場面を撮影した動画がSNS上に出回り、「もう回転ずしに行けない」などのコメントや迷惑行為への批判が相次いだ。運営会社側は、迷惑行為の動画がSNS上に掲載されていることが判明したと発表し、警察に相談。刑事・民事の両面から厳正に対処するとした。その後、当事者と保護者から謝罪を受けたものの、引き続き厳正に対処していく方針を明らかにしている。
このことで、回転ずしのイメージが低下し客足が遠のく、一時的に時価総額が下落する、などの損失を被った。他の回転ずしチェーンにおける迷惑行為動画にも波及、一連の騒動は「すしテロ」と呼ばれ、社会問題になりつつある。その後、うどん店や牛丼店など、さまざまな飲食チェーンにも広がり、外食産業全体の信頼関係を損ないかねない大きな問題へと発展している。
こうした迷惑動画の拡散は、迷惑行為や反社会的行為を撮影し「内輪ウケ」や「目立つ」ことを目的としてSNSなどに投稿するものの、あくまで身内で完結すると思い込み、不特定多数に広く拡散する可能性を自覚していないことが主な原因とされる。
2013年頃には「バカッター」「バイトテロ」などと呼ばれた、類似の迷惑行為が話題となった。飲食店やコンビニなどでアルバイトをする若者が、食品を収納する冷蔵庫に入る、食品材料の上に寝そべるなどの行為を撮影した写真をTwitterなどのSNSに投稿し広く拡散、コンビニや飲食チェーンに風評被害を与えた事例だ。
スマートフォンの普及により、写真を撮ってすぐSNSに投稿しやすくなった時代の流れがあった。身内で完結するつもりが、投稿が広く拡散してしまう性質は同様だ。その後、迷惑行為の投稿の炎上はしばしば見られたものの、コロナ禍などにより、話題からは遠ざかっていた。
最近の迷惑行為には、以前と異なる特徴がある。まずは、スマートフォンやインターネット網の高性能化、動画サイトやショート動画の流行により、投稿が画像から動画に変わった点だ。画像ならフェイクの可能性もあるが、動画は行為の一部始終がリアルに伝わる。また、以前はアルバイトという「店員」側での投稿が多かったが、最近は「客」側が多いのも特徴だ。
投稿の流れも変わっている。以前は迷惑行為を撮影した画像や動画を本人もしくは撮影者がSNSに投稿し炎上する流れであった。ところが最近は、本人や撮影者はLINEやInstagramのストーリーズなど、限定公開のSNSやメッセージアプリを利用するが、投稿を見ることができる誰かがSNSに投稿、拡散し炎上する場合が多い。最近の一連の騒動では、過去の迷惑動画が何者かに掘り起こされ、炎上したケースもある。
迷惑行為を撮影して内輪ウケを狙う行為も、限定公開の投稿を再投稿する行為も、動画を拡散する行為も、場所や主を特定する行為も、どれも軽い気持ちで行うものであれ、こうした行動の連鎖で、飲食店やチェーン、もしくは業界全体を不幸に陥れてしまうのは忍びない。投稿の当事者も、その場の思い付きが今後の人生に影を落とす可能性を考えると心が痛む。こうした現象は、事前に防ぐに越したことはない。
冒頭で紹介した大手回転ずしチェーンでは先日、「タッチパネルから注文を行いレーンでは注文商品のみを提供する」「食器や調味料は希望すれば交換」「席とレーンの間にアクリル板を設置する」など店舗運営方法の一時的な変更を発表した。やむを得ないことではあれ、好きな品を取れる、格安で食べられる、などの楽しみを半減させかねない。早めの解決を願うばかりだ。
筆者が一番有効と思うのが、以前、「セルフレジ万引きが深刻化~対策はあるのか?」でも紹介した「AIカメラ」だ。AIカメラは、防犯カメラの映像をAIがリアルタイムに解析、不審な行動や動きを判定、スタッフなどに通知を送る、といったシステムだ。実際、ある大手回転ずしチェーンでは、3月上旬にAIカメラを使った迷惑行為防止システムの導入を決定している。同社は利用者が取った商品を判別できるAIカメラをレーンの上部に設置ずみだが、このカメラを利用し、すし皿のカバーが複数回開閉されるなどの不審な動きを検知するという。
基本的にAIカメラは、AIに通常行動を学習させ、そこから逸脱した違和感行動を検知させる、もしくは異常行動を学習させ、合致する行動を検知させる仕組みで、用途や目的に応じてカスタマイズできる。迷惑行為防止を目的とするシステムも多く提供されているので、探してみるとよい。また、AIカメラは、迷惑行為や不審な行動の他、暴行や器物破損、転倒やふらつき、ごまかしや不正行為など、さまざまな検知に対応するものもある。
迷惑行為対策にはAIカメラが有効と述べたが、AIが異常を検知した場合の対処も大きなポイントだ。「実際に行為が行われたか判断すること」や「顧客に対してどのように対応するのか」という2点に関しては、現在のところ人間が知恵を絞る領域となるからだ。例えば、セルフレジの場合、AIカメラが異常を検知しスタッフに通知が来たら、セルフレジの故障と告げ、改めて有人レジで計算し直す、という対応例もある。
また、カメラが目立つ状況では迷惑行為の抑止に有効な面もあれど、顧客側が「監視されているようで落ち着かない」という感情を抱き、足が遠のくことにもなりかねない。そのあたりを加味して設置方法を工夫する必要がある。
さらに、AIカメラなど迷惑行為対策によりコストがかさみ、商品を値上げせざるを得ない状況も避けたい。格安な料金で楽しめる、好きな商品を自分で取れるなど、店舗や業種の個性などメリットを保つに越したことはない。今回、各チェーンや店舗の工夫、対策方法も話題となっている。今後、皆が快適に楽しめるよう心を尽くした工夫や気遣いが、未来を変えていくのかもしれない。そして、利用する私たち側の意識も変えていきたい。皆が楽しく過ごせるよう、いたずらや迷惑行為をしないのはもちろん、商品や備品、働くスタッフや他の顧客を尊重できる姿勢を皆が持ちたいものだ。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」