
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
公開日:2025.05.13
2024年6月に「Windows 10が2025年10月14日にサービス終了、今できる対策は?」という記事を書いた。この記事から10カ月程度が過ぎようとしているが、読者のみなさまの移行はお済みだろうか。Windows 10のサポート終了(End of Support、以下「EOS」と略)まで、あと半年。そろそろ期限的にもギリギリの状況であり、新たな措置の発表があったため、今回、再び記事をしたためた次第である。
先の記事にも書いたが、現在もWindows 10が使われているのは「使い勝手がよく長く親しまれてきた」ことが大きい。加えて「最新OSであるWindows 11のシステム要件が厳しい」という現状もある。実はWindows 10のライセンスに対しては、Windows 11への無償アップグレード・プログラムが提供されており、条件さえ整えばコストをかけることなく簡単に移行できる制度がWindows 11の発売時から継続して整っている、というありがたい状況ではある。ただ、Windows 11を使うための要件が足らずにWindows 10のままで使われているパソコンも多い現状だ。無償アップグレード・プログラムの「要件」でふるい落とされてしまったパソコンは、基本的にはWindows 11を搭載したパソコンにリプレイスするしかないが、まだまだ使い続けられているパソコンは多いという。
では、Windows 10のままのパソコンは、2025年10月14日のEOS以降、どうなってしまうのだろうか。以前マイクロソフトの旧ブラウザー「Internet Explorer」終了時には、IEが期日以降は起動しなくなる、という状況であった。
「Windows 10、Windows 8.1、Windows 7のサポート終了について」によれば、「2025年10月14日以降、Windows 10のセキュリティ更新プログラムやテクニカルサポートが、Microsoftから提供されなくなります。お使いのパソコンは引き続き機能しますが、OSをWindows 11に移行することをおすすめします」とある。
「よくあるご質問」の「サービス終了とはどういうものですか」という質問には、「Windows 10のテクニカルサポートとセキュリティ更新プログラムの終了」とあり、「Windows Updateからの無料ソフトウエア更新プログラム、テクニカルサポートまたはセキュリティ修正プログラムを取得しなくなります」「オンラインでの安全性を維持できる最新の需要な更新プログラムとサポートを取得」できなくなる、という。
これはつまり、EOS以降はセキュリティ更新プログラムやテクニカルサポートが提供されず、Windows 10のまま使い続けることは「安全ではない」ことを意味する。期限以降はWindows 11の、さらに最新バージョンで使うことが「オンラインの安全性」の不可欠条件となる。やはり安心して使うためにはWindows11への移行が必須なのだ。
実は2025年3月19日に新たな制度が発表された。「Windows 10の拡張セキュリティUpdatesプログラム(ESU)」だ。このプログラムに登録すると、登録されたパソコンに引き続き「重要なセキュリティ更新プログラムを受け取るオプション」が提供され、「2025年10月14日にサポートが終了した後もWindows 10を引き続き使用」できるというのだ。なお、このプログラムを利用するには、Windows 10の最終バージョン「22H2」での運用が必須となる。
ESUは有料のサブスクリプションで提供される。組織や企業向けには、1デバイスあたり1年61ドル(USドル、以下同様)、個人またはWindows 10 Homeは1デバイス当たり1年30ドル。年単位で提供され、最大3年間、料金は1年ごとに前年の2倍となる(例えば、組織・企業の場合、翌年は122ドル、翌々年は244ドル、という計算だ)。ESUプログラムは年単位で購入する必要がある他、2年目に購入する場合は、1年目のセキュリティ更新も累積されるため、前の1年分も支払う必要がある。
注意しなくてはならないのは、サブスクで提供されるのは「重要なセキュリティ更新」のみで、終了までに通常受け取れていた機能やドライバーのアップデート、通常レベルのセキュリティアップデート、さらには電話やメールなどのテクニカルサポートは含まれていないことだ。Microsoftは「ESUに関連する課題に遭遇したユーザーに対してのみサポートを提供」と述べており、最低限のセキュリティのみの確保であることは明らかだ。結論からすると、重要なセキュリティ以外のアップデートは提供されないこと、年々コストが増加するシステム、などから推測すると、これはあくまで「一時的な延命措置」といえる。
これらから考えると、いくらWindows 10を使い慣れている、といっても、ESUに高額を支払ってまで重要なセキュリティ更新のみのサポートを受け続けることは、賢いとはいいにくい選択となりそうだ。例えば、重要なセキュリティ更新は問題があれば早めに更新は来るが、更新までの間に攻撃されるリスクがある。さらにはテクニカルサポートがないためトラブルが起きた際に公式からの情報が得られない、機能のアップデートもないので、Windows 11対応のソフトや周辺機器などが正常に動かない、たとえ不具合が起きても手だても保証も得られない、などのリスクが考えられるためだ。やはり、ESUはあくまでもWindows 11をなかなか導入できない、導入予定だが時間がかかる、など、やむを得ない場合のためにのみ使うための一時的な措置、としてとらえるのが賢明だろう。
一般的にEOSを迎える2025年10月14日以降は、Windows 11を常に最新の状態で使うのが基本となりそうだ。先述のとおり、ESUプログラムに登録したWindows 10 パソコンは、最低ラインの安全性のみ、ということを忘れてはならない。
ならば安全上一番効率がよいのは、EOSまでにWindows 11への移行を終えることだ。無償アップグレードの利くパソコンはWindows 11へ。無償アップグレードの利かない(システム要件の足りない)パソコンは、Windows 11搭載パソコンへのリプレイスを考えよう。なお、リプレイスされたパソコンはLinuxやChrome OSなど他のOSに載せ換えて使える、生かせる部品もある、などの可能性があり有償で引き取ってもらえる可能性も高い。
筆者がこの期限を推奨するのは、Windows 10→11の無償アップグレードが2025年10月14日に終了するのでは、ともいわれているからだ。無償アップグレードは、常に終了がうわさされてきたが、マイクロソフト側も「いつ終了するかわからない」と述べており、今まで終了せずに行われているからといって継続される保証はない。ESU終了まで継続して提供される可能性も考えられるが、一方でいつ終了してもおかしくない現状もある。
パソコン入れ替えの予定が10月以降になる場合は、ESUプログラムを即契約し、入れ替え予定日まで最低ラインの安全性で「もたせる」しかないケースもあり得る。ESUプログラムはこうした利用が本来で、「サービス以降もWindow 10を使い続ける」という形は行わないことを強くおすすめする。なお、業務用のカスタマイズシステムなどは「Windows 10でなければ動かない」というソフトやプログラムも存在するだろう。その場合もESUでつなぎつつ、できる限り早めにWindows 11への対応を進めたほうがよいだろう。
無償アップグレード終了の可能性も視野に入れつつ、できれば期限内に無償アップグレードを行おう。繰り返しになるが、やむを得ずESUを利用する場合もできる限り早くWindows 11への移行を実施しよう。EOSに間に合わない場合は、ESUプログラムのコストが年単位であることと、年を重ねるにつれコストがかさむことを考えると、ESU契約から1年以内に移行を済ませたほうがよい。
Windows 10→11の移行について、筆者のようにパソコンの操作に慣れているユーザーはあまり抵抗を感じないが、主に仕事でのみパソコンを使う(プライベートではパソコンを利用しない)ユーザーは「Windows 11に慣れるのが大変だった」との声を聞く。新しいOSに慣れるためにも、まだWindows11へ対応できていない企業・組織は対応を急いだほうがよさそうだ。
パソコンの導入は、購入(買い替え)もいいが、リースやレンタルを利用する手もある。リースやレンタルなら、OSが変わる場合のパソコンのリプレイス費用やOSなどのライセンス費用の心配なく、契約の更新や契約替えなどで、所有するほどのコストはかからず、コスパよく維持できるだろう。この機会に所有形態も含めて検討するとよいだろう。
「コストがかさむ」などの理由で、移行のための一時措置以外の用途で、ESUプログラムに登録したWindow 10 パソコンを使うことはやめたほうがいい。ましてや、ESU未登録でセキュリティ対策が不十分な状態のWindows 10 のパソコンを使うことは絶対に避けるべきだ。なぜなら、最近の悪意あるものはターゲットを決めて狙ったり、中小の組織もかまわず狙ったりしてくる。AIなどの利用で手段はますます巧妙化している。無防備のデバイスは容易に侵入・攻略可能な獲物。ランサムウエアなどの被害に遭って高額な身代金を請求されたり、大事なデータをダークウェブに公開されたり、さらには会社全体の信用を失墜させる、などのリスクをてんびんにかけてよく考えよう。
そのあたりは、最寄りのベンダーに相談するか、Webなどで検索してソリューションを見つける、公共の相談窓口に相談する、などで「無償アップグレードできないWindows 10 パソコンがたくさんある」などの現状を正直に話して相談・対策するのがよい。先にも述べたように、IT機器の所有形態から見直すことによって、コストがぐんと下がる場合もある。パソコンやOSの管理をサービスに任せることで、長期的に効率化や省力化につながる可能性もある。あらゆる手段を検討して自社に合った対策を立てるのがよい。
そんな感じで、ESUプログラムの提供開始のニュースを「これでWindows 10がまだ使える」と思った場合は、考えを改めたほうがよい。さらには、コストがかさむからといってESUプログラムの登録もせずEOS以降もWindows 10 パソコンを使い続ける事態も避けたほうがよい。これらを頭に入れておかないと、致命的なことにもなりかねない。早めに相談しよう。繰り返しになるが、EOS以後、安全にパソコンを使用していくためにはWindows 11を活用するのがベターだ。併せて、Windows 11を使う場合であっても、Windows Updateなどで常に最新の状態にして、セキュリティ対策を充実させることが明るい未来につながる。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
【TP】
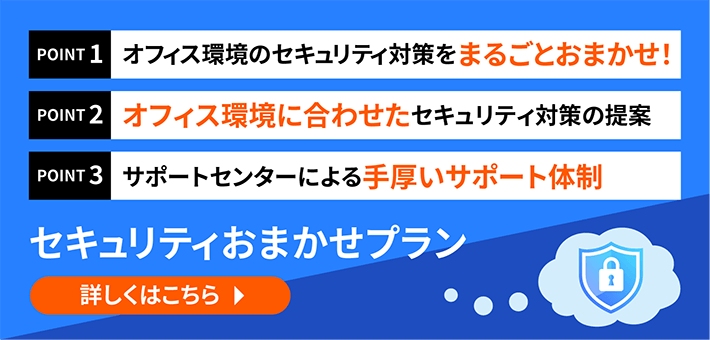
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」