
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
SNS投稿に関するITリテラシーについては、本連載でも何度か取り上げてきた。偽情報の拡散や人の尊厳を傷つける投稿、誤解を招く表現――どれもSNS上で避けるべき行為だ。とはいえ、センシティブな話題や、言いにくいことを投稿したいとき、「このテーマで、この表現で大丈夫か」と迷う場面は少なくない。その際、表現を事前にチェックしてくれるアプリやサービスがあれば......と思っていた。生成AIに投げて意見を聞くのも有効だが、事情説明などが案外手間だったりする。もっと気軽に使える専用ツールがほしいところだ。個人はもちろん、企業の公式アカウントなどでもこうしたチェックツールを導入することで、炎上のリスクを減らせるだろう。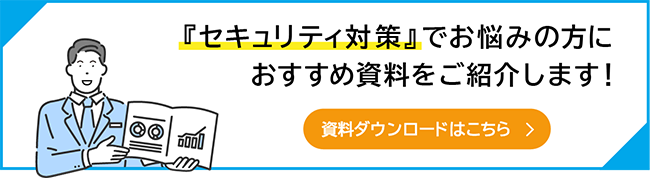
そんな中、ニュースでふと目に入ったのが、「弁護士ドットコム」が無料提供を始めた「AI炎上チェッカー」というスマホアプリ。7月4日にサービスを開始したばかりのツールだ。ちなみに「弁護士ドットコム」とは、日本で法律相談や弁護士検索ができるオンラインプラットフォーム。「そんな団体がスマホアプリを?」と思わなくもないが、サービスのリリース文である「弁護士ドットコム、誹謗中傷や炎上を未然に防ぐリスクチェックツール『AI炎上チェッカー』を7月4日より無料配信開始」によれば、キャッチコピーは「ネットで傷つく人、傷つける人を少しでも減らしたい」ということで、今の時代に、素直に心に響く言葉だ。
アプリの公式サイトには、「失言ひとつで人生終わる前に。」というさらなるキャッチや、「文章作成」→「リスクチェック」→「投稿する」という手順図も添えられている。これからは、この「リスクチェック」手順を「常識」にしていく姿勢も重要だろう。アプリの操作についても動画を見るだけで分かりやすく理解できるのでぜひ見ておこう。
リリース文では、さらにこう説明されている。「『AI炎上チェッカー』とは、自身がSNSをはじめとしたインターネットサービスに投稿する前に、その内容に誹謗中傷性や炎上リスクがないかを生成AIでチェックできるツールです。投稿内容は『攻撃性』『差別性』『誤解を招く表現』という3つの観点から評価され、リスクの程度を可視化します。さらに、アプリ内から各種SNSにシームレスに連携でき、安全性が確認された文章はそのまま投稿も可能です。なお本ツールは『発信を制限する』のではなく、『より良い発信のための選択肢を提示する』ことを主眼とし、多様な価値観への配慮を重視しています」。
「発信を制限する」のではなく「選択肢を提示する」という発想。これは今の時代にとてもフィットしていると感じる。では、実際に使ってみよう。
まず、アプリストアからダウンロードしてインストールを行う(公式サイトにもリンクがある)。「同意してはじめる」をタップすると、最初のサンプル投稿が表示されるので、「チェックする」をタップ。前述の3つの観点(攻撃性、差別性、誤解を招く表現)について、それぞれ5段階での評価と解説が表示される。画面下部には全体をまとめた「総評」も表示される。
表示内容を参考に、下部の「新規」「修正」「投稿する」のいずれかを選択する。「修正」を選べば、表示されたアドバイスに従って表現を直せるし、直した文章を再びチェックすることもできる。何度でも調整しながら、より伝わりやすく安全な投稿をめざせるわけだ。満足できる形になったら「投稿する」で投稿すればよい。
入力欄には「投稿のヒント」として、「投稿前に一呼吸して冷静になりましょう」「事実確認を忘れずに」「異なる意見を尊重しましょう」などの注意書きがあり、まるで親切な先生のように寄り添ってくれる。画面右上の「サポート」メニューでは、さらに踏み込んだ情報が用意されている。「一度ネットに出ると、永遠に残る可能性があります」「デジタルタトゥーって知っていますか?」「匿名でも安心できない理由」「進路や仕事に影響することがあります」「個人のSNSでも会社や学校に迷惑をかけます」といった注意喚起に加え、「炎上予防のチェックリスト」や「対処法」までそろっていて、情報の手厚さには感心する。
こうした内容を見ていると、筆者としては自分だけでなく若い世代や子どもたちにもこの「AI炎上チェッカー」をぜひ使わせたい、と思えてくる。たった1つの軽率な投稿が将来を閉ざすといった事例もよく耳に入るこの時代。学校や会社、あるいは大切な人に迷惑をかけたり、自分自身を傷つけたりする。そんなリスクを、投稿前に可視化できる点でも、使う価値はあると思う。
筆者は、企業のSNS公式アカウント担当者も率先してこの「AI炎上チェッカー」を使ってみてはどうだろうかと思う。例えば、投稿前に何度もチェックし、「攻撃性」「差別性」「誤解を招く表現」がほぼゼロになるまで調整してから公開する、といった使い方はどうだろうか。運用を業務フローの一環に組み込むのも1つの考え方だ。一案として投稿のたびにチェック結果のスクリーンショットを撮り、投稿内容とともに上司へ提出して許可を得てから投稿する─そんな手順を取り入れてもよいだろう。
さらに、特にニュースや情報拡散、リツイートなどを行うときは、元情報のファクトチェック(専門サービスによる確認)も忘れてはならない。現在は生成AIによるフェイク画像やフェイク動画による情報かく乱も珍しくない。投稿時には、元情報のURLやチェック結果のキャプチャを添付・共有して上司に提出するなどの対策もいいかもしれない。なぜここまでの手順が必要かといえば、今や不用意なSNS投稿1つで企業の信用を大きく損なう可能性があるからだ。
SNSの炎上およびファクトチェックに関しては、本連載の過去記事なども参考にしてほしい(「総務省と大手IT企業・団体がリテラシー向上の官民連携プロジェクトを開始」「事実なく『多摩川氾濫』がトレンド入り。SNSを混乱させる『インプレゾンビ』とは?」「総務省が『インターネットトラブル事例集』で注意喚起。その内容と目的は?」など)。
さらに、これらの記事中に掲出した総務省の「DIGITAL POSITIVE ACTION」や「インターネットトラブル事例集」もなかなか役に立つ。その他「理論から実践まで学べるJFCファクトチェック講座20本の動画と記事を一挙紹介」も参考になるだろう。
もちろん、こうした「AI炎上チェッカー」をはじめとするツールや教材を活用し、SNS担当者だけでなく、社員全体のICTリテラシーを高める勉強会を開くのも有効だ。SNSは「個人の発信でも会社や学校に波及する」からこそ、"全員で備える"姿勢が、企業全体のリスクマネジメントにつながるだろう。
現在、生成AIをはじめとしたAI技術が誰でも使えるようになり、SNS投稿の作成にも活用される時代となっている。すでに触れた通り、フェイク画像やフェイク動画はもちろん、文章自体にもまことしやかな「嘘」が含まれるケースも増え、現実との境界が非常に見えづらくなっている。こうした状況が、私たちの社会に混乱をもたらしているのは言うまでもない。
だからこそ今後は、「ファクトチェック」や「AI生成コンテンツの識別」、「AI利用の明示」などの仕組みを充実していくことが強く望まれる。自分でチェックするのは手間も時間もかかる。投稿前には、「AI炎上チェッカー」のような仕組みを使って効率的に文章をチェックし、情報そのものも信頼性の確認(ファクトチェック)を忘れずに行いたい。また、どんな影響が誰に及ぶかも考慮しよう。スマホからの何気ないX(旧Twitter)への投稿であっても、それが一瞬で世界中に拡散される可能性がある。
最近はハラスメントに厳しい世の中の流れがある。ハラスメントはするほうももちろんだが、全くそういうつもりでなくても相手がハラスメントと感じればハラスメント行為が成立してしまう。そのような事態を引き起こさないよう、SNSへの投稿や、相手への物言いは、十二分に気を配る必要がある。ハラスメントを引き起こすリスクのチェックのためにも、この「AI炎上チェッカー」は役に立つだろう。
さらに、LINEなどのメッセージツールが盛んな現在、トークなどクローズドな空間であっても、相手は生身の人間。表現に迷いがある場合には、今回紹介したような仕組みで確認してから送ると安心だ。万が一、SNS投稿が炎上してしまったり、LINEの一言が相手を傷つけてしまったりしたと感じたときには、ごまかさず、誠意ある対応を心がけよう。「AI炎上チェッカー」の「サポート」記事などもそんな場面で参考になる。
企業アカウントのSNS運用については、PR TIMESの「2025年の企業公式SNS運用戦略。歴史からわかる最新動向と運用ポイントを解説」が参考になる。さらにはSNSリスクのモニタリングやマーケティングに役立つソリューションも数多く存在する。また、社員向けにICTリテラシー教育を実施するプログラムも広まりつつある。これらはWebで検索する他、最寄りのベンダーや公共の相談窓口に問い合わせてみるとよい。
デジタル社会では、たった一言の投稿が予期せぬ形で拡散し、一生消えない"デジタルタトゥー"として残ってしまうリスクもある。時には人や組織に多大な迷惑をかけてしまうこともある。併せて、個人はもちろん企業はSNSの炎上リスクだけでなく常にセキュリティのリスクもさらされている。こうした多様なセキュリティリスクをよく理解しつつ、「AI炎上チェッカー」などの便利なツールを上手に活用し、SNSを安全かつ楽しく、そして効果的に使いこなしていこう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「自分流ブログ入門」「70歳からはじめるスマホとLINEで毎日が楽しくなる本」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」