
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

まだまだ続きそうなコロナ禍で、転職希望の人や転職を余儀なくされる人が増えている。新卒予定者の就職も厳しいものになりそうだ。コロナによる景気低迷で、職を探すのも企業が優秀な人材を探すのも困難を極めている。
「3密」や「ソーシャルディスタンス」が叫ばれる昨今、外出や対面はなるべく避けたい。そんな中で普及しつつあるのがオンライン面接(Web面接)だ。ビデオ通話アプリや会議アプリを使って、面接をオンラインで行うものだ。テレワークが常態化し、会議も打ち合わせもオンラインで行われる中、面接もオンライン化するのは当然の流れかもしれない。
「2020年8月実施 Web面接に関する21卒学生アンケート」によれば、現在の就職活動について「ほとんどWebで行っている」「Webの方が多い」という回答が62.4%に上った。やはりこのご時世での面接は、対面を避けオンラインで行う企業の増加が数字にも表れている。総務省の今年度の採用情報の1つにも、面接(文中では「官庁訪問」)をオンラインで行う旨が書かれている。公的機関でもオンライン面接を行っている。
オンライン面接を実施する企業への印象はおおむね良好だ。安全面を考慮している、安心して勤務できそう、志望者や社員を大切にしていそう、などという声が多い。「面接に来てください」と言われるよりも「まずはオンラインで」と言われたほうが好感度は高そうだ。今は、オンライン面接の有無が、志望度を左右しかねない状況ともいえる。
一方で調査によれば、すべてオンラインのみで就職先が決まってしまうのは、「とても不安」「やや不安」という声が61.9%に上る。遠隔ゆえに伝わり方が生よりも落ちる。1人でIT機器に向かうため、より緊張する人もいるだろう。オンラインゆえの、見栄えや聞きやすさ、回線の具合や適切な場所選びなどの課題もある。
ただし、面接にオンラインという選択肢が増えれば、その分面接する機会も増える。企業と志望者双方にとって望ましいのは間違いない。最終選考に近い段階で対面して、お互いにリアルな意思交換をしたうえで採用するのがよいだろう。
というわけで、説明会や初期段階はオンライン、最終選考などの重要な決定を行う際は対面、というのが現時点でのベストともいえよう。こうした現況に柔軟に対応する企業姿勢も、志望者を含めたステークホルダーへのアピールになるはずだ。
オンラインなら面接の間口が広がり、遠く離れた志望者や、忙しくて時間がなかなか空かない人とも面接できる。互いのコストや時間が省けて、空いた時間に気軽に行えるので、志望者・企業はより多くの接触が可能となり、広い範囲から人材を確保できる。選考がスピードアップできれば、優秀な人材の早期アプローチも可能となる。
テレワークなら、離れたままでも働ける。テレワーク前提のオンライン面接なら、さらに範囲は広がる。遠く離れた人はもちろん、忙しい人や、子育てや介護などで自宅を離れられない人、現役を引退した人なども確保できるだろう。
一方デメリットもある。通信環境の不具合や通信機器の不備などでうまくつながらず、コミュニケーションを取れなければ元も子もない。トラブルで効率を大きく下げるリスクもある。環境によっては映像が不鮮明、音が途切れる、ノイズが入る場合もある。トラブルを避けるには、複数の手段を用意しておく、事前に環境や設定を確認する、あらゆる環境を想定してテストを行っておくといった備えが必要だ。もちろん普段からITスキルを上げる意識も持っておきたい。
映像などで記録を残せるのはメリットになるが、面接の内容や機密情報が漏れる恐れはデメリットだ。機密に関しては志望者に録画・録音は控えてもらう、残しても他人に見せない、などの伝達・合意形成も必要だ。面接中はリアルタイムでほかの人に聞かれない対策もいる。企業側は社員の話し声や映したくない様子、志望者側は散らかった部屋、気を抜いた家族の様子などが映ってしまう恐れもある。そのあたりは注意を促したい。
オンライン面接の手段に関しては、スカイプやLINEなどの普及した手段以外にも、専用のシステムを導入する選択肢もある。相手は一般人ゆえ、普及している手段に軍配が上がりそうだが、セキュリティやクオリティーへの不安はつきまとう。いずれにせよ、システムや機器を整えテスト運用をし、志望者に必要機器の確認やアプリケーションのインストール、事前のアカウント登録、注意点やトラブルへの対応方法などを事前に連絡しておこう。
オンライン面接は企業のITスキルやコロナへの姿勢、トラブル時の応対など、企業姿勢が露見する。こうだったああだったとSNSで拡散されてしまうと取り返しがつかない。今後も増えていくのを見据え、メリットとデメリットをよく知ったうえで、柔軟に対応していくのがよい。テレワークやオンライン会議など、ワークスタイルの変化は悪くない方向と考える。オンライン面接もしかり。選択肢が増えるのはよいことだ。新常態にいち早く適応していきたい。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
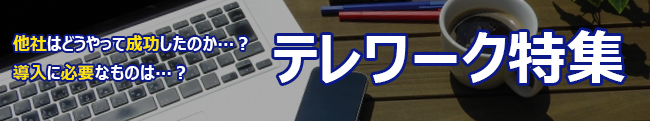
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」