
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
DXの実現が企業にとって大きな関心事となる中、現場ではデジタル化やIT化が目的になってしまうことも少なくない。DXは、事業や業務のトランスフォーメーションが最終的な目的であり、小手先のデジタル化で満足しては大きな目的が達成できない。このため、経営層には、変革後のビジョンやビジネスモデルを描くだけでなく、変革をやり遂げる覚悟も求められる。
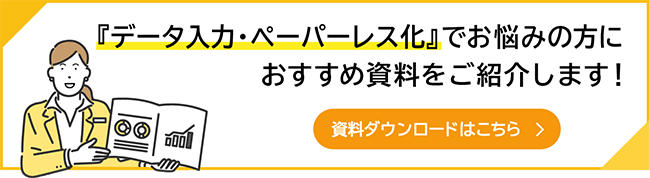
めざすビジョンやビジネスモデルの変革を実現するためには、まず従業員やステークホルダーに対して変革の意図とプロセスを浸透させる必要がある。その上で、企業が蓄積するさまざまなデータを用いて事業成長を図る「データドリブン経営」を実現するためのインフラを整える必要があるだろう。業務がアナログで属人的に回っている状態が継続していては、全社で共通化した変革に取り組み、完遂することができないからだ。
例えば、多くの紙を扱う業務をデジタル化して業務効率を向上させる取り組みを推進する企業があるとする。郵送やFAXで送られてきた請求書や見積書、納品書などは、これまで事務担当者がパソコンで情報をシステムに転記していた。この業務に、紙に書かれた文字をデジタル化するAI OCRシステムを導入すると、スキャナーで読み取ることでデジタルデータとして利用できるようになる。
最近ではFAX受信にも対応した複合機がある。受信したデータをそのままPDFなどのデジタルデータに変換する機能を備えていることもあり、AI OCRと組み合わせると人手をかけずにデータ化が可能になる。ところが、こうしたツールを活用しても、変わったのは紙の書類のデータを転記する業務だけ......。これでは投資が大きな効果につながらない。ペーパーレス化や、プロセスのデジタル化による進捗管理を進めるならば、その先の変革へのビジョンが社内に浸透していることが不可欠だ。書類の転記をAI OCRなどで自動化することで、請求データなどをリアルタイムで確認、分析できるようになる。データ化によって経営状態を迅速に可視化できれば、経営層が事業環境の変化にいち早く気づき次の一手を打つといった施策につながるだろう。より現場に近い部分でも、AI OCRの活用で事務担当者の業務負荷を軽減し、さらなる業務改善や新規事業のアイデア立案に振り分けられれば、ビジネスの価値を高められる可能性が広がる。
漫然と業務をデジタル化するだけでなく、"変革の先の姿"を小さいながらも想定して取り組みを進めれば、デジタル化が業務や事業の変革の第一歩につながる。AI OCRや複合機などをはじめ各種のツールを活用するとしても、得られる効果とその先の変革を見据えていることが、成果を得るために欠かせない――。
ケーススタディー(1):A社の場合(倉庫業)
倉庫業のA社では、生産性向上のために将来を見据えた新しい業務の在り方を社内プロジェクトで検討していた。めざすのは「お客さまに対して持続可能で豊かな社会を実現させる物流サービスの提供」であり、「収益力の強化」「高付加価値サービスの提供」「経営基盤の強化」が求められた。
そこで、A社では、ツールとして「ロボット」「AI」「BIツール」などを採用。「省力化・省人化の実現」「ステークホルダーとの協業体制」「新分野への参画」の実現に向けて歩みを進めた。併せて、集中的に社内システムや業務改善の仕組みを学ぶ研修を行い、人材育成に努めた。その結果、従業員のアイデアから進捗管理システムが実現した他、従業員のマインドチェンジができたことでデジタルを活用した業務改善プランを立案可能になった。
ケーススタディー(2):B社の場合(製造業)
製造業のB社は、10年ほど前にIT化が進んでいる他社を見学したことを契機に、「このまま井の中の蛙(かわず)でいるとうちの会社はなくなってしまうのでは?」という危機感を覚えた。同社が継続してきた「人の手を介するものづくり」を強みとしながら、デジタル技術を最大限に活用する変革にかじを切ることにした。
具体的な戦略としては、データドリブン経営を実践すると同時に、そのための足回りとして業務のIT化を進め生産性向上と情報のデータ化に取り組んだ。まずタブレットを全従業員に配布して積極的に利用することで、業務のデジタル化のインフラを整備。こうしたDXの取り組みにより、サプライチェーン全体でのEDI利用率が9割近くまで向上、タブレット導入による設計図面の電子化では社内のペーパーレス化60万枚/年を達成するような成果を生み出した。
ケーススタディー(3):C社の場合(運輸業)
運輸業のC社は、「企業基盤の強化」と「競争力・共創力の強化」を柱として「物流」×「テクノロジー」でデジタル時代の新たな物流イノベーションを創出することをビジョンに掲げた。ビジョンに向けた戦略として「スマート物流による全体最適化」「物流情報プラットフォームによる付加価値創出」「DX促進のための組織構築・人材育成」を展開した。
目標に向けてC社は、現場でのDXに取り組んでいる。AI OCRを利用した受注入力システムの導入により、FAXで受信した発注書の入力作業での属人化の解消と工数・ミスを削減した。また、紙出力をPDFでの運用に変更、FAX配信もデータのメール配信に切り替えるなど、デジタルありきの運用に移行した。複合機でスキャンした受領書をクラウド型文書管理システムに取り込み、業務の進捗管理の効率化も実現している。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=岩元 直久
【MT】
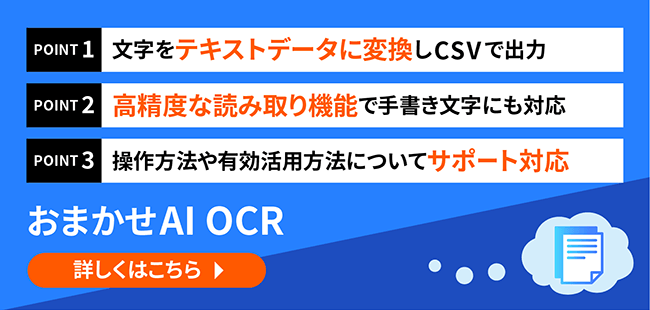
審査 24-S1007