
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
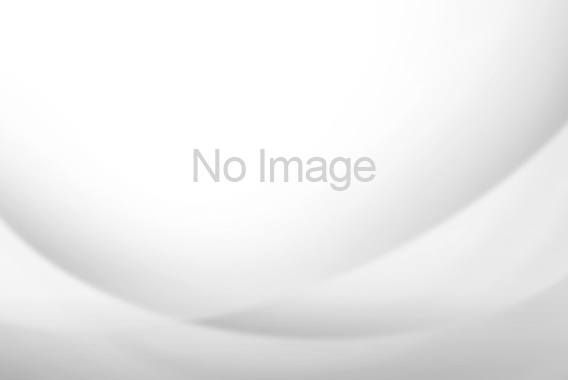
いつ人生の終末を迎えるかは分からない。親戚の祖母が亡くなったとき、いざというときには何をどうしてくれという指示が細かく書かれたノートが出てきて、家族が困らず助かった。だがこんなケースはまれな部類で、たいていの場合、誰それが急に亡くなって何をどうしたらいいか困った話のほうが多い。
万が一に備えて準備をしておくことを、最近は終活と呼ぶ。さらに、死後のために書き記しておくノートをエンディングノートと呼ぶ。近頃は項目が印刷され、書き込むだけで完成するエンディングノートなるものが文房具店で売られていたり、スマホやパソコンに書き記せるアプリもあったりする。
デジタル社会においては、IT機器内のデータやインターネット上のデータ「デジタル遺品」がたくさんある。もしもの際に、契約している回線、固定電話や携帯電話、モバイル通信、サブスクサービス、SNSやクラウドストレージの中身はどうなるのだろうか?
そんな中、三井住友信託銀行と日本IBMがクラウドで終活を支援するニュースが少し前に話題になった。サービスのページを見ると、「人生100年時代の終活を応援。おひとりさま信託、エンディングノートをデジタル化」というキャッチが目に入る。単身者や身寄りのない人、家族と離れて暮らす人向けに、万が一の際の身の回りの死後事務をトータルでサポートする“おひとりさま信託”だ。
おひとりさま信託では、エンディングノートで契約者の死後のさまざまな希望を実現する。エンディングノートは高いセキュリティを確保したクラウド上に置かれ、契約者はスマホやパソコンからマイページにログインして、いつでもエンディングノートを確認・更新できる。
それに加え、希望するタイミングで携帯端末へSMSを送り、安否確認を行うサービスも提供。死後はエンディングノートに従い、預けた資金を用いて葬儀・密葬、訃報連絡、デジタル遺品の消去、家財などの整理、ペットの終身管理などの死後事務を代行するシステムだ。
公的な遺書は訂正や撤回はできるものの、手続きにいちいち手間や時間がかかる。このサービスのエンディングノートは即時に改変が可能で、改変直後に何かあっても最新の内容に従って意思通りに事務が行われる。クラウドに置かれたノートは、自分だけが管理できる仕組みで、他者に見られない。死後の事後処理は身内や友人が行うとトラブルの可能性もあるが、本人の遺志に沿って専門業者が行う場合、信頼度も高い。
シニア世代のインターネット利用率は年々上がり続け、現時点では90%を超えるという(総務省「通信利用動向調査」)。モバイル端末所有者の77.0%がスマートフォンへシフト済みという統計(MMD研究所「2020年 シニアのスマートフォン・フィーチャーフォンの利用に関する調査」)もあり、想像以上にシニアのデジタル化が進んでいる。
総務省は5月18日、行政手続のオンライン化など社会全体のデジタル化が進められる中、デジタル技術を使いこなせる人とそうではない人の「デジタル格差」解消が重要な課題であるとし、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を基本方針に、6月から全国で主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を開始するという。
シニア層のフリマアプリ利用が増えているという話もある。メルカリの調査によると2020年4月から2021年3月の60代以上のメルカリ年間利用者数は前年比1.4倍。平均年間出品数も20代と比較して約2倍という結果が出ている。
終活や断捨離目的でも、不用品が処分できて小遣い稼ぎにもなって一石二鳥なフリマは有用だ。フリマアプリは結構多くの手順を要する。理解して使いこなすシニアがいるのは驚きだ。先日の年配者対象のコロナワクチン接種予約の際も、80歳過ぎた親がスマホで予約して驚いたなどの話もあった。
おひとりさま信託以外にも、IT利用の終活関連サービスがさらに増える傾向がある。そろそろ終活を考える世代のITスキル向上も、サービスが盛んになるゆえんかもしれない。クラウド上でエンディングノートを管理できる「メモリアルパラダイス」、デジタル遺品専用のエンディングノート作成支援サービスを行っている「日本デジタル終活協会」、生前整理をスマホひとつで解決できる「エンディングノート」アプリなどが興味深い。
デジタルのみならず終活全般をサポートするサービスも、Web上でたくさん見つかる。郵便局の「終活紹介サービス」、イオンの扱う「イオンの終活」、東急ベルの「終活サポートサービス」などだ。
自分はまだ老人ではない…という世代も、いつ何があるか分からない。そもそも使っていないクラウドサービスを支払い続けていたり、利用実態と合わないプランを選択していたりするのはよくあることだ。自身が利用するクラウドサービスの棚卸しを兼ねて、エンディングノートをまとめておくに越したことはない。
なお、クラウドサービスは、安全なクラウド上にデータが保管され、いつでもどこでもデータにアクセスできて便利だが、運営側の都合でサービスが終了してしまうことがある。一方、実物のエンディングノートは、いざというとき誰かに見つけてもらえなければ意味をなさない。
終活≒身辺整理を行う際には、自分に合った手段を選定しよう。デジタルで管理できるほか、あらかじめ項目が設定されていて選択・入力するだけのエンディングノートはお手軽だが、項目を実施するのが業者ではない場合は、定期的に印刷したりアクセス方法(URL、IDとパスワードなど)を示したりする工夫も必要だ。
デジタルな終活は死に対する備えというより、常日ごろ考えておくべき状況把握と捉えておいたほうがよい。誰しもに必要なもので、いつか考えようと先送りにしておくと、いつまでも放置することになってしまうだろう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」