
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
ビジネスにプライベートに、欠かせない自動車。自動車の運転は、神経と体力をすり減らし、責任も重い大変な操作だ。未来を描く映画のように、目的地を言うだけで自動的に目的地まで運んでくれる車や、無人で配送を行う車が実現したら、まさに夢のようである。全自動とはいかないが、自動運転システムや運転支援システムは、各メーカーが開発にしのぎを削っている。
ところが今年の5月、米国で自動運転車が初めての死亡事故が起きた。安全性を疑問視する声も上がっている。実際はどうだろう。
自動運転システムの開発は古くから進められている。専用の道路上を自動で走行する車は、1980年代には開発されていたとされる。筆者もかなり前に、道の中央に引かれたラインをたどる自動運転車の映像を見た記憶がある。
全自動とまではいかないが、運転の一部を補助して安全性を高める運転支援システムは、市販車にも普通に搭載されるようになってきた。こうした運転支援システムには、自動で車間距離を保つ「ACC(Adaptive Cruise Control)」、障害物を検知してブレーキの補助操作を行う「衝突被害軽減ブレーキ」、ハンドルを自動操作する「レーンキープアシスト」などがある(国土交通省「現在実現している運転支援システムの概要」)。
スバル車を所有する筆者であるが、運転支援システム「アイサイト」を体験する機会があった。係員の指導で、障害物に向かって思い切りアクセルを踏んだら、いきなり障害物直前で大きくブレーキがかかって車が停止。機能のすごさを実感した。
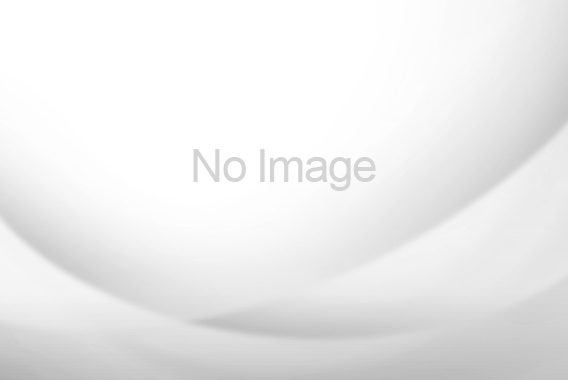
こうしたシステムにより、信号無視で交差点に侵入してきた車と衝突せずに済んだ、という話も聞くし、実際の映像もYouTubeなどで見ることができる。こうした支援システムを社用車に搭載すれば、運転者の負担の軽減、安全性の向上など多くのメリットがありそうだ。
ただし、アイサイトの体験の際、メリットを大きく感じた一方で、もし後続車がぴったりついてきていたら…、障害物ではないものを誤認識したら…といった危惧も感じた。「運転支援システム 誤作動」などでネット検索すると、多くの情報が見つかる。「自動ブレーキが対向車の排ガスの煙で止まる」「運転支援システム搭載車が誤作動を起こす謎の場所がある」など枚挙にいとまがない。
米テスラ社は「すべてのテスラの車両に、将来の完全自動運転に対応するハードウエアを搭載」すると宣言。実際の映像も公開した(オートパイロット技術の解説ページ)。8台のサラウンドカメラ、12個の超音波センサー、前世代の40倍以上の処理能力を持つ新型車載コンピューターなどにより、自動運転が実現するという。
実は、5月の死亡事故はテスラ社の自動運転システム搭載車で起きている。事故当日は、晴れて明るい天候だったため、侵入してきたトレーラーの白いサイド部分を認識できず、自動ブレーキが動作しなかった。また、乗用車のドライバーが自動運転を過信し注意を怠っていた。この2つの大きな原因が指摘されている。
国土交通省・警察庁は世論の影響が大きかったこの事故を踏まえ、「現在実用化されている『自動運転』機能は、完全な自動運転ではありません!!」というリリースを発表。ユーザーへの注意喚起を改めて徹底した。
リリースの添付資料にはこう記される。事故を起こしたテスラ社製の自動車に搭載された自動運転機能は「通常の車と同様、運転者が前方・周囲を監視しながら安全運転を行うことを前提に、車線維持支援、車線変更支援、自動ブレーキ等を行う機能に過ぎない」「安全運転支援システム・自動走行システムを4つのレベルに分け、事故が起きた5月のケースはレベル2で、責任はドライバーにあった」と説明している。
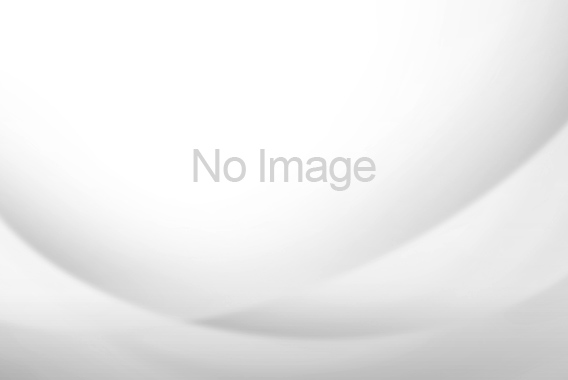
先述したテスラ社の自動運転の映像は、事故から半年後の2016年11月に発表されたもの。歩行者を感知して大きく減速するなど多少の違和感はあるが、その高度さには目を見張る。運転支援システムや自動走行システムが、ドライバーの負担を軽減し、安全性を高める方向をめざしているのは確かだ。ただし人間と同等か、それ以上にあらゆる状況に対処し100%に近い安全性が保証される“完全なる自動化”はまだまだ先かな、と、筆者は考えている。
なお、こうした運転支援システムや自動走行システムは、IoTとの連携が不可欠である。身近なところでは、スマートフォンと車の連携。スマホを車と接続することで、アプリなどを車載機器側の画面上で操作する「Android Auto」「Apple CarPlay」が話題となっている。そういえばアップルが独自の自動運転車を開発中、などの噂もあるが、真偽のほどは不明である。
自動運転も、IoTと車との連携も、今後ますます発展して便利になっていくだろう。運転には人の命が関わる。新技術とリスクヘッジ。そして法整備……。課題はまだ多いが、これからの進歩に対し、常にアンテナを張って見ていこうと思う。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」