
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
2018年11月23日(日本時間24日)、パリで開催された博覧会国際事務局(BIE)総会において、2025年国際博覧会(万博)の大阪開催が決定した。開催期間は2025年5月3日~11月3日、場所は大阪の夢洲(ゆめしま)。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だ。1971年の大阪万博以来、55年ぶりとなる。
この決定に関して、大阪万博の仕掛け人の1人、元大阪府知事の橋下徹氏は、テレビ番組で「万博は行きたいけど、並ぶのが嫌」という出演者の声に、「パビリオンに並ばせない」と語った。さらに、バーチャルで、会場に来てもらわなくても楽しめる旨も発言。ITを駆使した万博を匂わせた。
過去の万博やこれからのITを踏まえ、コラムニストである筆者が、「ITを駆使した並ばない万博」とはどんなものかを予想したい。
アジア初かつ日本で最初の国際博覧会だった1970年の前回の大阪万博は、動く歩道やテレビ電話、ワイヤレスホン(携帯電話)、電気自動車などの最先端技術を集めた。来場者は6400万人を超えた。愛知万博の来場者数が2200万人だったことからしても、その人気と経済効果の大きさがうかがえる。
政府は、25年の万博の経済効果を約1兆9千億円としている。りそな総合研究所によれば、大阪万博の開催による経済波及効果はさらに大きく、全国で2.2兆円と予測される(りそな研究所、プレスリリース『大阪万博の開催による経済波及効果』)。関西地区はもちろんだが、2020年の東京オリンピック後の全国的な景気浮上策としても、期待が大きい。
さらに今回の万博で注目されるのは、インバウンドの来場動向だ。訪日外国人が大きく増えている昨今、観光地としての関西地区の人気の高さも考えると、今回の来場は全体の10%前後と想定される。関西だけでなく、日本各地への波及も考えられ、その経済効果も大きい。
なお、会場となる夢洲は、大阪府大阪市此花区にある人工島だ。大阪府の松井一郎知事は、カジノを設置した統合型リゾート(IR)の誘致も進めており、正式に決定すれば2024年に第1期の開業が行われる予定。夢洲は、万博会場とIRとの一体的な開発となる見込みだ。
筆者、13年前の愛知万博(「愛・地球博」)に足を運んだが、駐車場、入場ゲート、各パビリオン、レストラン、グッズ売り場、トイレなど、とにかく「並んだ」「待った」印象が強い。各会場への移動も大変だった。暑い時期だったのもあり、子どもやお年寄り、体の不自由な人を連れての来場は難しそうだと感じた。実際、子ども連れの友人たちも「大変だった、もうこりごり」と口々に言っていた。
1970年の大阪万博の動画を見ても、大勢の人が殺到するさまが分かる。「万博=すごい人出で、とにかく並ぶ」、こうした印象が、人々の万博への来訪をちゅうちょさせることにもなりかねない。最終的に来場者数や経済効果を高めるカギはこの点の払拭で、「並ばない」だけでなく、あらゆる点において「快適さ」を提供し、来訪者に「行ってよかった」「また行きたい」と思わせる万博にすることが重要、と思う。
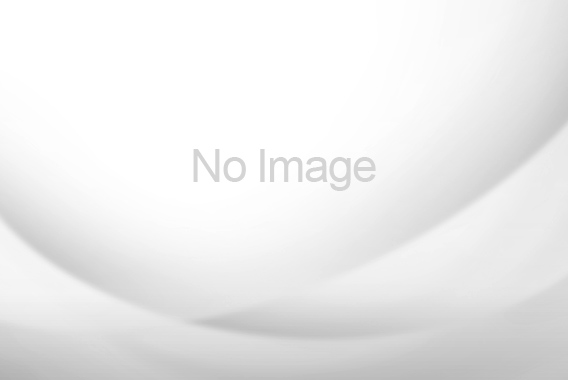
愛知万博のパビリオン前の待ち行列(筆者撮影)。1日にパビリオンを3つ見られたらよいほう、といわれるほどの混みよう。ただし、混雑=人気が高い、ともいえるわけで、知恵や技術を尽くし、来訪者に快適さを提供できるとよい
幸い、AIやIoTが発展し、個人のほとんどがスマホを持ち歩く昨今、ITを駆使すれば、「快適な万博」も不可能ではないと筆者は思う。
2005年に開催された愛知万博は、まだスマホ普及前だった。それでもパソコンや携帯電話から、パビリオンやイベントの観覧をインターネット予約できるシステムがあった。IT好きの筆者はもちろん活用した。1人1日最大2件まで、という限られた枠ではあったが、大いに助かった覚えがある。
場内の専用端末で、当日予約できるシステムもあった。現在はスマホがあるので、専用アプリで事前の予約はもちろん、当日の予約にも対応するはずだ。実際のパビリオンやイベント会場では、スマホを整理券のように使ったり、順番が来たタイミングを通知で知らせたりしてくれれば並ばなくてすむ。混雑の具合や事前予約状況、興味のあるジャンルをAIが分析し、その人に適した順路を提案する、などもよい。予約や順番待ちのシステムは、現在でもEPARKなどがあるが、万博開催の頃にはさらに発展していそうだ。
会場内はスマホアプリがナビになる。これで道に迷わない。食事やトイレ、休憩場所の空き具合をチェックできたり、空きの出そうな施設を予測したりして案内。IoTトイレについては、以前、「IoTとAIで“トイレソリューション”」でも触れた。さらに、会場への行き帰りのナビや、交通機関の乗り換え案内もサポートする。交通機関や駐車場、宿泊施設の空き具合チェック&予約にも対応。手荷物の預かりや車椅子といった補助機器の貸し出しも、事前予約やスマートロッカーなどで、待たずに受け渡しできるとよい。
スマホをセットして使う、簡易な組み立て式のゴーグルの提供があってもよい。パビリオン近くでは、その国やテーマで美しい風景や歴史、伝統芸能、テクノロジーの解説などがVRでリアルに楽しめれば、待ち時間も待ち時間でなくなる。前回の大阪万博のバーチャル体験も面白いだろう。バーチャルコンテンツの一部はインターネットでも公開すれば、行けない人、事前の下見をしたい人にも重宝されるはずだ。
会場の案内には、AI搭載のロボットが活躍しそうだ。問い合わせに答えるほか、行きたい場所に連れて行ってくれたり、子どもの相手をしてくれたりなど、あらゆる助けになってくれる。熱中症などで具合が悪くなったときは、スマホアプリでSOSするだけですぐに駆け付けて対応。手首に付けるスマートブレスやスマートウォッチ、ウエアラブルデバイスを貸し出して来訪者の体調をチェック。体調に応じてプランを提供したり、休憩時間の提案や休憩場所を案内したり、係員やロボットが声を掛けたりなどで、病人の発生を未然に防ぐといいな、と思う。
以上、「ITを駆使した並ばない万博」を自由に想像してみた。この想像を超えて発展してくれるのも楽しみだ。快適さの提供が、万博成功、さらなる統合型リゾートの継続運営のカギとなる。ITを駆使した誰しもが快適に楽しめる万博を期待したいと思う。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」