
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
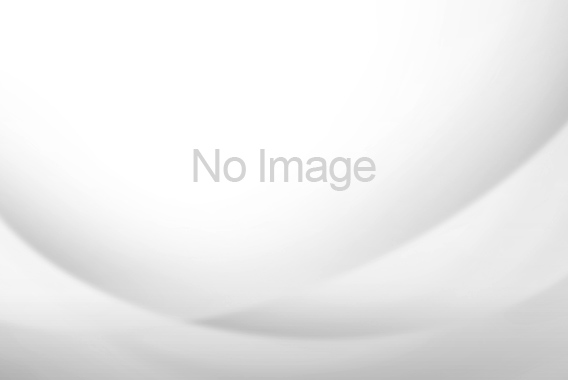
最近よく聞く「カーボンニュートラル」という言葉、環境省の「脱炭素ポータル」にある「カーボンニュートラルとは」を見ると、カーボンニュートラルとは、「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること」とある。
2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルをめざすと宣言した。「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味する。こうした長期目標の実現には、ICTの力が欠かせない。
ICTを駆使して迅速に集計、現状分析、将来予測、シミュレーションなどを行い効率化を図る。ノウハウやデータを共有して一丸となれるよう、Webページ、SNSなどでの広報や情報共有も重要だ。個人、企業、地域、国、地球規模での現状や経過、今後進むべき方向などを見える化して、取り組みをサポートするのもICTの得意分野だ。
経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」には、「情報の利活用、デジタル化が急速に進展する中、カーボンニュートラルは、製造・サービス・輸送・インフラなど、あらゆる分野で電化・デジタル化が進んだ社会によって実現される。したがって、デジタル化・電化の基盤である、半導体・情報通信産業は、グリーンとデジタルを同時に進める上での鍵である」と書かれている。ICTはカーボンニュートラルに重要な位置を占めることが分かる。
経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を策定しました」にある「カーボンニュートラルの産業イメージ」で産業全体のイメージがつかめる。
分野ごとの目標、現状の課題と今後の取り組みは、経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」から参照できる。この中の「半導体・情報通信産業」には、デジタル化によるエネルギー需要の効率化・省CO2化の促進(「グリーン by デジタル」)と、デジタル機器・情報通信産業自身の省エネ・グリーン化(「グリーン of デジタル」)という2つのアプローチを車の両輪として進めていく、とある。
企業システムをクラウド化して省エネを達成したり、テレワークやオンライン会議の導入で移動に伴うエネルギーを削減できたりするなど、デジタル化による省エネ効果は、あらゆる産業に大きく寄与する。DX推進は省エネ・省CO2化に加え、企業力の強化にもつながる。都市部・地方を問わず早急に進めていく必要がある。
高速光回線や5Gなどの情報通信インフラが整備されれば、高速大容量通信のみならず超低遅延や多数同時接続でリアルタイムな遠隔管理や操作など、今までできなかったことが実現。さらなる効率化やエネルギー削減につながる。
今後、デジタル化の進展、特にAIやビックデータの利用拡大で、より高い計算能力を備えたデータセンターが必要となる。データセンターの建設には、電力コストや環境など従来の条件に加え、再生可能エネルギーや脱炭素電源が利用可能な立地が求められる方向だ。政府は、2030年までに新設データセンターの30%以上の省エネ化をめざしている。
住宅や工場、自動車などの電化やデジタル化で、デジタル関連の消費電力が増加、CO2排出が飛躍的に増える予見もある。ICTにおいては、デジタル機器のハード・ソフト両面における省エネ化+高性能化が大きなカギとなる。省エネでなおかつ高性能なデジタル機器の開発が、ICT企業の新しい価値ともなっていくだろう。
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略によれば、半導体・情報通信産業においては、10年早い2040年のカーボンニュートラル実現をめざす、とある。カーボンニュートラルにおいては、ICT企業はもちろんICTに携わる人全般が、カーボンニュートラルの先導者という意識をもち、先立って歩んでいく必要がある。
カーボンニュートラルについて、まずは先述の環境省の脱炭素ポータルをチェックしよう。トップページ下には、「企業の皆さまができること」「地方自治体の皆さまができること」「国民の皆さまができること」として、それぞれに向けた情報が参照できる。メルマガで、新着情報を定期的に受け取るのもお勧めだ。
実際の温室効果ガス排出・吸収量算定の結果は、環境省の「温室効果ガス排出・吸収量等の算定と報告」から参照できる。「ひろがるカーボンニュートラル」では、脱炭素社会の実現に向けて取り組みを進める自治体・企業のトップが思いを語っており参考になる。
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略には、「発想の転換、変革といった言葉を並べるのは簡単だが、カーボンニュートラルを実行するのは、並大抵の努力ではできない」とある。脱炭素社会の実現は、一朝一夕にはなし得ない。今回はICT周りに絞って述べたが、カーボンニュートラルの実現にはあらゆる生活分野について、国民一人ひとりが取り組む必要があるのは言うまでもない。
最近よく聞かれる「サステナブル」「サステナビリティ」という言葉。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標「SDGs(Sustainable Development Goals)」が基となり、地球の環境を壊さず、限りある資源を未来の世代まで残し、豊かで平和な暮らしを続けていく姿勢として広がっている。カーボンニュートラルの実現にはライフスタイルをサステナブルなものに変えていくことが不可欠だ。まずは個人単位での意識変革から始め、明るい未来をめざしたい。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」