
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
IT(情報技術)は平成に入って大きく発展、人々の生活スタイルを変えた。この30年で一番変化を遂げたのはITだと言っても過言ではない。もはやIT機器もネットワークも、生活に欠かせないものとなった。平成から令和に変わろうとする今、平成30年間のITを振り返ってみたい。
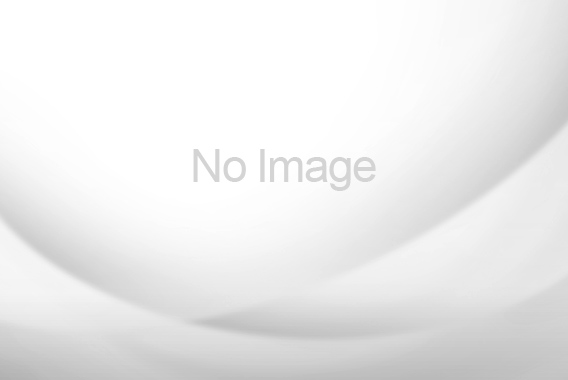 昭和の後期、筆者にとってパソコンは憧れの存在だった。平成はパソコンとともに始まったといえる。それまで大型で高価だったコンピューターが、小型・低価格化されて個人の手に届くようになった。国内で広く使われたのは、1982年に発売されたNECの「PC-9800シリーズ」だ。MS-DOSというコマンドタイプのOS、フロッピーディスクで動かした。
昭和の後期、筆者にとってパソコンは憧れの存在だった。平成はパソコンとともに始まったといえる。それまで大型で高価だったコンピューターが、小型・低価格化されて個人の手に届くようになった。国内で広く使われたのは、1982年に発売されたNECの「PC-9800シリーズ」だ。MS-DOSというコマンドタイプのOS、フロッピーディスクで動かした。
平成はパソコンの時代、と言ってもよい。パソコンを大きく変えたのは、マイクロソフトの「Windows」だ。平成に入ってすぐの90~91年に発売されたWindows3.0/3.1は、全世界で1億本以上、国内でも400万本以上が出荷され、パソコンの標準OSとなった。筆者が就職してためたお金で買ったパソコンは、Windows 3.1が搭載されていた。その後Windowsは、95/98/98SE/Me、XP/Vista、8/8.1、10と発展して今に至る。
PC-9800シリーズにもWindowsが搭載されたが、WindowsとともにPC/AT互換機が普及し、98シリーズは姿を消した。PC/AT互換機は、スロットやサイズなど規格が統一化され、パーツの取り換えや好きなパーツを組み合わせによる自作が可能。自由度や拡張性、コスパに優れ、主流となった。
パソコンのもう1つの流れが、アップルの「Macintosh(Mac)」だ。Macは洗練されたインターフェースと豊かなスペック、価格も比較的高めで、Windows系に比べれば高級な路線といえた。ラインアップはアップルが提供する製品のみだ。
パソコンが普及する一方、財務会計や販売管理などの事務処理に使われていたオフィスコンピューターは、Windowsや汎用ハードウエアの普及で廃れていった。
大きく変化を遂げたのは据え置き型が主流だった「電話」だ。昭和の終わりごろ、自動車搭載用の自動車電話が発売。その後の携帯電話の下地となった。大きなバッテリーを搭載し、肩に掛けて持ち歩くショルダーホンというタイプもあった。
90年代に入り、携帯電話の普及が進む。2007年の初代iPhoneから「スマートフォン」が登場。スマホは、スケジュール、ToDo、住所録、メモなどの情報を管理する携帯端末(PDA)に電話や通信機能を持たせたもので、その利便性から急速に浸透した。スマホは、2013年に携帯電話の普及率を上回り、現在に至る。
スマホと連携する時計型のウエアラブルデバイスも登場した。歩数や血圧を計測して体調管理に使えたり、電話やメッセージなどスマホのコミュニケーション機能が搭載されたりする。「Apple Watch」や「Android Wear」などの高度なスマートウオッチをはじめ、簡易なスマートブレスレットの人気も高い。
スマホやタブレットには、声で話しかけるとAIが答える「音声アシスタント」が搭載されるようになった。iOSの「Siri」、Androidの「Googleアシスタント」、アマゾンの「Alexa」などがポピュラーだ。さらに最近、こうした音声アシスタントが搭載されたスピーカータイプの機器「スマートスピーカー」が人気を博している。スマートスピーカーは音声ひとつで調べものや情報チェック、アラームやリマインダーを設定したり、ニュースや音楽を流したりなどが可能。それに加えて照明やエアコン、テレビなど家の家電類も操作でき、いわゆるIoTが実現するのが特徴だ。
平成に変わる頃、電話線にモデムでつながったパソコンが通信を行う“パソコン通信”が盛んに行われた。「ニフティサーブ」や「PC-VAN」などの有料サービスのほか、有志が回線や端末を提供して行う草の根ネットもあった。
世界を網の目のように結ぶインターネットは、教育機関や研究機関、企業から広がり、一般へは80年代後半から普及した。最初はパソコン通信同様、電話回線を使ってのダイヤルアップが主流だった。基本的に従量課金で、通信料金がかさむため、電話回線の利用が少なくなる夜から早朝の時間帯に使い放題になる定額サービスに人気が集まった。
2000年代には、インターネットに定額で接続し放題のブロードバンド回線が普及した。電話回線を使ったADSLの登場だ。最近はより高速な光回線に変わっている。ただし、スマホやタブレットが広まり、パソコンを必ずしも必要としない流れも出てきた。ブロードバンドを導入せず、モバイル契約のみで過ごすユーザーも増えているという。
家や会社内のIT機器を結ぶローカルネットワーク(LAN)。LANケーブルとハブでつなぐイーサネットが普及した。今や家でのノートパソコンやスマホの利用には、無線LANアダプターと無線LANルーターを用いたWi-Fiでの接続がスタンダードに。ホテルやカフェ、駅など、無料Wi-Fiを提供する店や施設も増えた。
3Gや4Gなどのモバイルネットワークは、スマホや携帯電話の本体とセットで契約する場合が多い。プランはデータ通信と通話の組み合わせがメインだが、データ通信専用のプランもある。サービスはNTTドコモやKDDI、ソフトバンクなどのキャリアからの提供が主となるが、キャリアの設備を借り受けてサービスを安価に提供する仮想移動体通信事業者(MVNO)も人気だ。なお、今後のIoTなどの用途も見込んで、新しい5G通信サービスが各地で実験され、現実化しつつある。
生活スタイルも大きく変化した。調べものは図書館などに行っていたはずだ。ところがITの普及で、いつでもどこでも好きな情報を得たり、ネットワークを通じて離れた場所の人々といつでも情報交換したり、コミュニケーションできる便利な世の中になった。本も紙の書籍に代わり、電子書籍をいつでも入手して好きな端末で読める。
買い物もITの普及で注文翌日には届くネット通販が盛んになった。ネット上での金銭取引や仮想通貨も登場。現金を使わずスマホなどの端末を用いて決済を行うキャッシュレス決済も普及しつつある。“お金”の概念が変わってきたのも、平成の特徴ではないだろうか。
IT機器やソフトウエア、企業のサポートにもAIが使われるようになった。ニュース記事をAIが書いたり、テレビのアナウンサーをAIが務めたり、AI搭載のロボットが店舗のアシスタントになったりするなど、AIが人間になり代わるケースも徐々に出始めた。前述のスマートスピーカーも、AIが生活をサポートする。
IoTもAIと並び期待が大きい。これまでインターネットに接続されていなかった「モノ」同士がつながり、連携する。離れた場所から状況を把握したり、家電の操作や家の管理を行ったり、あらゆる情報が一元化されたりなど、生活が飛躍的に便利になりそうな気配がする。ただしIoTには、セキュリティとプライバシーの問題が付きまとう。
ざっと平成30年間のITの動きを見てきた。ITで私たちの生活は大きく変わりつつある。ITの普及により、昔、SF映画に描かれていたような未来が現実化しつつある。令和にはどんな幸せな未来が待っているだろうか。楽しみだ。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」