
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
2018年4月から、パソコンやスマートフォンを使い、インターネットを通じて医師が患者を診察する「オンライン診療」に健康保険が適用されるようになった。これは実際のオンライン診療の実用化を意味するが、初診は対象外。また、同じ医師の下に6カ月以上通院する患者に限られる。対面診療と同一の医師がオンラインも担当し、3カ月に1回は対面診療を受ける、などの条件がある。
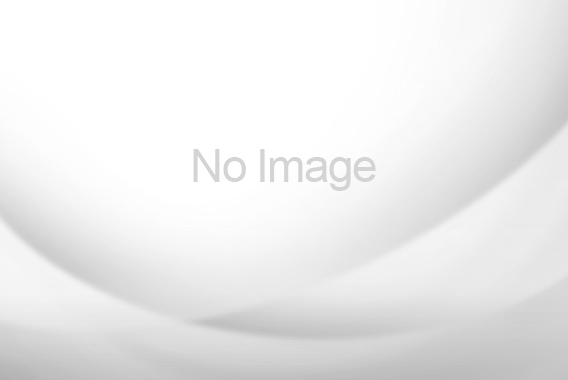
オンライン診療の流れは、医師がオンライン診療可能と判断しOKが出たら、スマートフォンアプリでユーザー登録してログイン、診療予約を行う。予約時間になったらアプリを起動、ビデオ通話で医師の診察を受ける。その後アプリに登録した決済方法で会計し、薬や処方箋は郵送で送られる。
オンライン診療があれば、高齢、多忙、遠隔地などが理由で容易に通院できない人にも、手軽に診察を受けられる環境が提供される。高齢化社会において通院への付き添いや、介護の負担も減る。これらのメリットは、割と誰しも想像がつくだろう。
実際、高血圧気味な筆者の通院に当てはめて考えても、前回からの状況を医師に伝え、血圧帳を見せ、現在の血圧や聴診器での診察を行い、いつもの薬をもらう。この流れなら、オンラインでもできそうだ。
ただ、実質の解禁から2年経過した現在、周りでオンライン診療を受けた話を聞いたことがない。筆者自身も、近くにオンライン診療対応の医療機関がなく、リアルで通院を続けている。聞くところによると、オンライン診療の普及率はわずか1%にも満たない(神奈川県保険医協会2019年4月調べ)という。
現在、新型コロナウイルス感染が急激拡大する危機的状況だ。7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)を対象に緊急事態宣言も出た。現在、各自治体から外出自粛要請が出される中、リスクの高い場所には出掛けるべきではない。生活必需品や食品の買い出しでさえ、ドキドキする。
さらにドキドキするのが医療機関への通院だ。筆者の通院する病院では、新型コロナへの感染が疑われる場合は直接出向かず、電話連絡してほしい旨、貼り紙がされている。それでも、感染者が駆け込む可能性はあるし、自覚症状のない感染者が紛れ込むかもしれない。高齢の母を連れている場合は、さらに不安は増す。これだけ外出を自粛する環境で、病気を治すために行く病院で感染したら、元も子もない。
実際、医療従事者の感染例や、医療施設でクラスター(感染者集団)となってしまった例も報道される。通院での感染を避けるには、オンライン診療が大きな助けになりそう、と誰しも考えるだろう。
問題は、オンライン診療に必要な条件が多過ぎることだ。ここまで条件が厳しくなければ、オンライン診療を行ってもよい、と考える医療機関は多いはずだ。普及には、条件の見直しが必要だ。オンライン診療の門戸を広げる署名運動も、現在行われている。
新型コロナウイルス対策として、加藤厚生労働相は3月31日の経済財政諮問会議で、オンライン診療を初診から認める検討に入ると表明。さらに厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」を3月11日と4月2日に開き、検討を行っている。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症が急速に拡大する現状を踏まえた期間限定の措置として、受診歴のある病院ならば、初診でもオンライン診療を認める解禁案を検討。さらに、受診歴のない病院での初診も含めた解禁も検討の範囲に入れる、との声明も発表した。安倍晋三首相は7日夜の記者会見で、「電話、オンラインでの診療も、初診も含めて解禁することとした。病院での感染リスクを恐れる皆さんに積極活用いただき、受診を我慢するといった事態が生じないようにする」と述べた。
なお、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」によれば、自宅療養などの軽症な感染者についても、オンラインで健康状態を把握していくとともに、オンライン診療を行う体制を整備する、とある。二次感染を防止する有効な対策だ。
ただし、オンライン診療はできることに限りがある。症状を正確に把握できない、患者の自覚症状以外の疾患を見逃す可能性や、急を要する場合に症状を重症化させる危険もある。なりすましや情報漏えいなどの問題も指摘される。
そのあたりは、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、対面診療を行わないリスクと、対面診療を行うリスクとを比較して、慎重に裁定すべきと思う。だが、緊急事態宣言が出るこの状況では、オンライン対応ができるところは早急に導入した方がいい。
ITスキルのない高齢者は置いてきぼりの状態で、敷居が高かったりもする。そんな場合は、電話診療で対応してもらえる場合もある(NTT東日本 関東病院の例)。かかりつけ医や近くの病院に問い合わせるとよい。実際に、感染を恐れて通院をためらい、持病が悪化する可能性のある高齢者に対し、電話診療で対応する事例もあるという。
なお、感染が疑われる場合は、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症について」の情報に基づいて問い合わせよう。新型コロナを含む健康不安については、LINEのトークで医師に無料相談できる「LINEヘルスケア」での相談をお勧めする。
オンライン診療、または電話などでの遠隔診療で、1人でも感染者を減らせればと思う。我々も日々変わる状況をよく見極め(厚生労働省の「オンライン診療に関するホームページ」の情報を参照)、正しい情報に基づき、良識ある行動で危機的状況を乗り切っていこう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」