
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
インターネットやSNSの普及で、偽・誤情報、誹謗(ひぼう)中傷などが拡散、社会に深刻な影響を与えているのは、この連載でも頻繁に触れているが、その状況は皆さんもよくご存じと思う。進化し続ける情報社会の中で、「間違った情報」は生活や個人、企業などに致命的なダメージを与える場合もある。そして、近年は生成AIの急速な普及・発展により、さらに判別が難しくなっている現状もある。この状況を受け、総務省はマイクロソフト、Google、ソフトバンクなど、19の企業・団体と連携した「DIGITAL POSITIVE ACTION」プロジェクトを1月22日に開始した。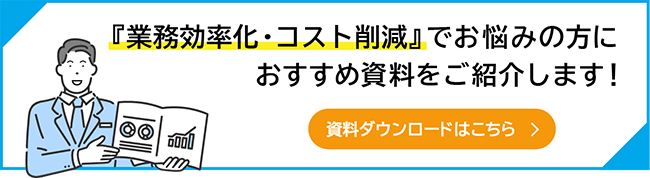
プロジェクトでは、ICTリテラシー向上のため、Webサイト開設や広報活動などを推進、国民が安全にデジタル技術を活用できる社会をめざす。プロジェクトのWebサイトには、「インターネットやSNSにおける利用者のICTリテラシー向上を目指し、プラットフォーム事業者や通信事業者、またステークホルダーとなるIT企業・団体等と共に官民連携プロジェクトとして"DIGITAL POSITIVE ACTION"を始動」とある。
「DIGITAL POSITIVE ACTION」という名称には、国や企業・団体、そして国民一人一人が「デジタル社会がポジティブな社会になるようなアクションを次々と起こしていく」という想いを伝える英語のスローガンに加え、想いに込められた意義を伝える「つくろう! 守ろう! 安心できる情報社会」という日本語のコピー、そして、安心で楽しめる情報社会になり、人が幸せになっていく状態を象徴的に描いたロゴマークの3点を掛け合わせたものを表現している、という。
総務省では、始動日の1月22日に「ICTリテラシー向上に関する新プロジェクト発表会」を開催した。冒頭に主催者として川崎総務大臣政務官が、「ICTリテラシーの向上にあたり、政府だけではなく、企業・団体のステークホルダーと共に官民で連携した取組を進め、社会的な機運を醸成する必要がある」とあいさつを述べ、「官民の取組を集約したWebサイトの開設」「多様な企業・団体によるセミナーやシンポジウム開催、普及啓発教材の作成」「各種広告媒体を活用した国民向け広報活動」という今後の3つの取組も発表された。
同日にサイトを公開し、2月12日には動画による「プロジェクト発表会 レポート」を掲載、参画団体・企業、関係省庁の取組を公開した。2月19日にはICTリテラシー向上に向けた参画団体・企業の取組にMetaと日本マイクロソフトが追加された。
発表会の動画は、「2024年は災害や選挙などにおいて、偽・誤情報が拡散し、国民の生活が脅かされた」、という一節からはじまる。
例えば、元旦の能登半島地震において、偽の助けを求める情報が拡散してしまったり、選挙においてSNS上の情報がメディアの情報よりも大きく拡散して票を集めた、などは記憶に新しい。続いて、官民すべてが、自主的に、一人一人の意識を変え、ポジティブな未来へとアクションを行うことが必要、というメッセージを発信している。まさにその通りではある。
「DIGITAL POSITIVE ACTION」サイトのトップページのロゴ右下の「ステートメントを見る+」をクリックして、内容をチェックしよう。ちなみに「ステートメント」とは「声明」「意見書」などの意味だ。
みんなの生活を楽しく便利にしてくれるネットの中に、
いつの間にかまぎれ込む、偽情報や誤情報、フェイク動画、
詐欺広告、SNS上の誹謗中傷、奪われる個人情報...。
正確な情報が手に入らないことも。
複雑に入り混じる情報に、惑わされてしまうことも。
さあ、今こそみんなで、
"つくろう!守ろう!安心できる情報社会"
ここにいる、あなたとともに。
情報社会を支える、企業・団体とともに。
DIGITAL POSITIVE ACTION、スタートです。
日常と隣り合わせになったデジタル空間を、
誰もが安心できる場所にするために。
人をつなぎ、社会を変えるデジタル技術で、
この世界の可能性がもっとゆたかに広がるために。
ポジティブな未来へ、アクションを。
いっしょに始めませんか?
この声明を、先に挙げたものをはじめとする昨年の偽・誤情報に関するさまざまな出来事を思い浮かべて読むと、なかなか心に染みてくる。発表会の動画のバックには「なぜ総合的なICTリテラシー対策が必要となるのか」というプレゼンテーション画面が見える。
「デジタル空間においては、誹謗中傷等の違法・有害情報や、人々の関心・注目の獲得が経済的価値となるアテンション・エコノミーの下での偽情報・誤情報の流通・拡散等、過激なタイトルや憶測だけで作成されたコンテンツの流通・拡散も社会問題化」しているとし、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」においての取りまとめで、こうした対策が必要となったという。
「アテンション・エコノミー」とは、現代社会、特に情報化社会において重要な概念で、人々の「注意・関心(アテンション)」が、お金や資源と同じように貴重な経済的資源として扱われる状況をいう。この状況では「情報の正確性・確実性」と「人々の関心・注目の高さ」が必ずしも一致しなくなるのが大きな問題となる。人々の注意を引きつけるため、扇情的な情報、フェイクニュース、誤情報などが拡散しやすくなり、情報の質の低下を招く。まさに昨年起きたような状況が、さらに激しくなるリスクが予想できる。
そこで「官民の幅広い関係者による推進体制を構築した上で、ICTリテラシーの向上のための取組を継続的に実施することによる社会的気運の醸成」が必要、となる。プロジェクトの方向性として、「官民の関係者が世代を超えて多様な普及啓発を行う」「利用者が安心安全にSNSを使えるよう、提供企業が自主的なサービス設計上の工夫を行う」「利用者が信頼性の高い情報にたどりつけるよう、事業者が自主的な表示上の工夫を行う」という3つが示される(ただし、あくまで「自主的な取組」とされているのが筆者としては気にかかるところではある)。
「DIGITAL POSITIVE ACTION」サイトには「ICTリテラシー向上に向けた参画団体・企業の取組」として、各団体・企業ごとに「イベント」「教材等」が示されている。
参画団体・企業の取組を見てみよう。「一般社団法人安心ネットづくり促進協議会」では、「みんなが安心して利用できる安全でグッドネットな利用環境を」や「こどもとネットのトリセツ」にといったリテラシー向上に向けた啓発ページが設けられている。また、「一般財団法人草の根サイバーセキュリティ推進協議会」では、「Grafsec第八回全国大会」というイベントや、「SPREAD情報セキュリティサポーター/マイスター能力検定(Grafsec)」という教材が提供されている。
Googleは、動画で学べる「偽・誤情報問題啓蒙キャンペーン (第二弾)"#ほんとかな?が、あなたを守る"」や「Grow with Google "インターネットの安心・安全について学ぶためのガイド"」、子どもがゲームでリテラシーを学べる「お子様向けインターネット リテラシー プログラム"Be Internet Awesome"」など、工夫を凝らした教材を公開している。
LINEヤフーは「LINEヤフー 情報空間の健全性確保のための取り組み」において、誹謗(ひぼう)中傷を防ぐ、偽・誤情報の拡散を防止する、詐欺行為などの犯罪を抑止する、情報リテラシー向上をサポートするための対策を公表している。そのほか、情報を読み解く力、見分ける力、発信する力を診断する「ニュース検診」も面白い。
Metaは「一緒に話そう!インスタANZENルール 保護者とティーンのための話し合いガイド」や「多様なコミュニティのためのInstagram & Facebook 安全ガイド」など、自社のサービスやネット全般に関する教材、話し合いのヒント、学びの場などを10項目にわたって提供している。
NTTドコモとソフトバンクでは、「スマホ・ネット安全教室」「親子のスマホデビュー安心ガイド "はじめて"の不安は、ここで解決」、店舗で開催しているスマホ教室を動画におさめた「いつでもどこでも学べる!スマホ教室動画」など、キャリアならではの教材を公開している。
ニュースサービス「スマートニュース」は、ニュース・情報サイトなりのノウハウを公開し、「"情報リテラシーを身につけるヒント"など、メディアリテラシー記事の公開」、「"オンライン防災訓練"家族で楽しく学べる、特別防災企画」などの教材を公開している。
日本マイクロソフトでは「Minecraftで生成AIを責任を持って使用するためのスキルを身につけよう(CyberSafe AI: Dig Deeper)」や「自分の道を切り開こう。今すぐAI学習を始めてみよう。」、教師と生徒向けとなる「デジタルセイフティを確保するために(4つの重要な行動)」にて4つの重要な行動を紹介する他、「検索コーチで情報リテラシーを教える」「ゲームを安全に楽しむために(Xbox ゲーム安全性ツールキット)」など、あらゆる世代や層に向けて自社サービスやネット全般のスキルやリテラシーを楽しく学べる教材を提供している。
偽情報や誤情報、デマやフェイクなどがまことしやかに流通する今の情報社会。それと知らずに悪意ある者の加担をし、社会をさらなる混乱に陥れたり、誰かを悲しませたりする事態はもちろん避けたい。企業の公式SNSアカウントや社員一人一人のアカウントでは特に、多くの人に迷惑をかけることはもちろん、会社としての信用に関わるリスクも大きいので、普段からITスキルとリテラシー強化を十分に行いたい。
先ほどの「ICTリテラシー向上に向けた参画団体・企業の取組」で提供されている教材はもちろん、その下に置かれた「ICTリテラシー向上に向けた関係省庁の取組」は、企業においても参考になるので活用したい。「内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」の「サイバーセキュリティ月間2025」や、こども家庭庁の「普及啓発リーフレット集」などがおすすめだ。
そして一番下にある総務省の教材が、日本においての最も基本となる教材となるので、個人の自主勉強にも、会社で行う勉強会などに大いに活用しよう。例えば、「ネット&SNS よりよくつかって未来をつくろう~ICT活用リテラシー向上プロジェクト~」や「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~」がある。この他にも、「生成AIはじめの一歩~生成AIの入門的な使い方と注意点~」「インターネットとの向き合い方~ニセ・誤情報にだまされないために~」「デジタル活用支援推進事業 標準教材・動画」などがあり参考になる。
もし、これら教材による自主的な学びや勉強会が難しいときは、最寄りのベンダーや公共の窓口に相談のうえ、民間の講座やトレーニングを受けるのも有効だろう。どちらにせよ、官民すべて、それぞれが正しい方向で「デジタル社会がポジティブな社会になるようなアクションを次々と起こし」、安心できる情報社会を「つくって守って」いきたい。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」