
脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)
"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り
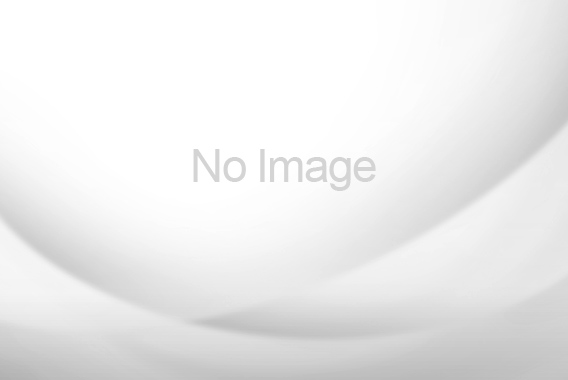
2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で、新たに始まる「電子データで受け取った書類の電子保存義務」が2年間猶予される。12月24日、令和4年度税制改正の大綱が閣議決定。27日、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」として交付された。具体的には、大企業であっても施行までに対応未完了の事業者が多数、中小企業においては制度の認知さえ十分に進んでいない、そんな実情に配慮し保存義務を延長した。
12月28日に出された「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」には、「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面による保存を可能とする。この宥恕措置の適用にあたって、納税者から税務署長への手続などは要しない」とある。なお、この解説はイメージ付きで分かりやすい。
先般、2021年7月に出された「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」にある「電磁的記録が保存要件を満たさない場合、青色申告の承認の取消対象となり得る」という記述が物議を醸した。
ところが11月の「お問い合わせの多いご質問」の補足説明に、要件を満たさぬ電子取引記録が経費とならず、青色申告の承認が取り消されるのではという質問に、「取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません」という回答がなされた。これで取りあえず胸をなで下ろした人も多かったのではないかと思う。
今回猶予される「電子データで受け取った書類の電子保存義務」とは、従来のようにやり取りしたデータを紙で出力して書面として保存する手段は認められず、電子取引のデータは電子による保存が義務化、しかもやり取りした電子取引データは「真実性」と「可視性」を確保した状態で、最長2カ月とおおむね7営業日以内に保存する必要がある。
多くの法人・個人事業主は今まで、電子データで送られてきた取引データや取引書類を印刷して、紙と同等に運用してきた。国税書類は紙の状態で7年間の保存が義務付けられ、各自、苦労して大量の書類を保存してきた。それがこの改正電子帳簿保存法の「電子データで受け取った書類の電子保存義務」により、大きな方向転換が強いられることとなった。
以前、当連載記事にも書いたが、そもそも電子帳簿保存法は、帳簿や帳票の電子化により、紙を印刷・保管するコストの削減、紙媒体の紛失の防止、働き方改革の推進(紙が存在する場所でしか仕事ができない状況をなくす)が目的だ。コロナ禍でのテレワークの増加などで、書類が紙から電子に変わりつつある状況に合った改正ともいえる。
電子帳簿保存法では、ゆくゆくは紙を全廃止し経理のオール電子化に向かう。電子データの印刷は廃止、さらに紙の帳票をスキャンなどで電子化して紙での保存も廃止できれば、大きな省エネ、省力化、環境保護につながる。
今回猶予される「電子データで受け取った書類の電子保存義務」に関して、猶予期間後は罰則が科せられる可能性もある。2年あるとはいえど、日々業務に追われていればあっという間なので油断は禁物だ。
企業向けクラウドサービスを提供するラクスが10月に行った全国の経理担当者への電子帳簿保存法に関する意識調査によれば、「来年1月からPDFで受領した請求書の印刷保管ができなくなる」ことについて、「知らない」「詳細までは知らない」との答えの合計が約73%だった。さらに10月の時点で来年1月の改正法施行に合わせて「電帳法に対応したい」が80%超だったものの、準備を進めているのはたったの20.1%というデータもある。
米国に対して日本のDX化は遅れている。デジタル時代の人材も思うように確保・育成できない現状もある。政府の掲げる「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」というスローガンの達成も困難が予想される。願わくはこの猶予の2年間で、分かりやすい講習会や勉強会、マニュアルやソフトの配布が行われてほしい。企業側もクラウドサービスの検討、質問できたり相談できたりする機関、相談相手の確保が急務となる。
猶予を与える、罰則をやめるという措置もありがたいものの、現状では基本的に自ら方法を模索しなければならない。企業向けサービスを提供する各社が、受け取った電子取引書類やデータを国税庁が求める要件で保存できるクラウドサービスを始めている。電子取引データの要件に即した保存を今から始めてみてはどうだろうか。
帳簿・帳票の保存には、紙のみ、紙と電子の共存、電子のみの3つの手段が存在するが、「紙のみ」はこの2年で消滅する。効率化と省資源を考えると「電子のみ(オール電子化)」の方向に行かざるを得ない。早期の電子化をめざそう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」