
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
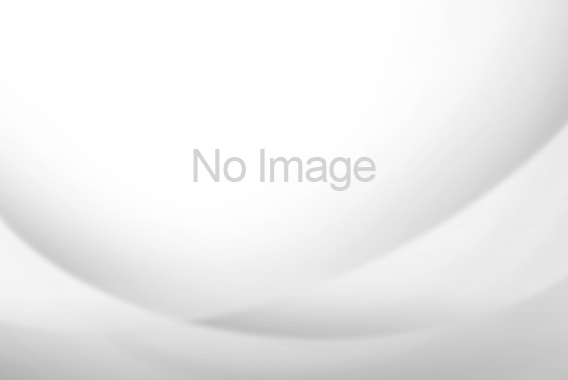
去る3月17日、肝の冷えるニュースが飛び込んできた。日本人の7割近くが利用するメッセージアプリ「LINE」が、中国の関連会社に開発を委託し、技術者たちがサーバー上の個人情報にアクセスできる状態にあったのが判明した。さらに続報で「トーク」に投稿されたすべての画像と動画が韓国内のサーバーに暗号化せず保管されていることも分かった。これについてはLINEにアップロードした個人の保険証などのデータも含まれていたという。
実際に不正アクセスや個人情報の漏えいがあったわけではないものの、以前から「韓国や中国のサーバーにデータが送られている」とささやかれていたのはほぼ事実ということになる。中国での業務委託と情報アクセスに関しては、民間企業に国の情報活動への協力を義務付ける中国の国家情報法との関連を問題視する向きもある。どちらにせよ日本の法律の届かないところで、越境したLINEのデータがどう扱われていたかを考えると怖い。
この報道に対して、LINEは「ユーザーの個人情報に関する一部報道について」でリリースを発表。ユーザーの個人が特定できる情報は、今後、原則として国内のサーバーで安全に管理すると伝える一方、一部の個人情報について説明が不十分だったと認めた。
これを受けて武田総務相は3月19日、総務省でのLINEを使った採用活動、意見募集や利用者への問い合わせ対応などの行政サービスの運用を停止すると述べ、関係省庁とも連携し、事実関係を把握して適切な措置を講じる考えを示した。さらに職員に対し、LINEをはじめとする外部サービスの利用に際し、業務上の情報を扱わないよう注意喚起を行った。
地方自治体では住民の利便性向上や業務効率化のため、保育所の入所申請、住民からの各種相談、粗大ごみの収集申し込みなどでLINEの活用が進む。全地方自治体に対して状況を報告するよう依頼した。地方公共団体の情報セキュリティ対策を支援する総務省としても、適切に対応したいとの考えを示した。
なお、報道を受けて、申請時に免許証など画像を送る必要のあるLINEの行政サービスを自主的に停止した自治体もある。さらに、ワクチン接種の受付にLINEを利用する予定だった自治体も、安全性が確保されるまでサービスを行わない指針を示した。
実際、首相官邸や厚生労働省の新型コロナウイルス感染情報をはじめとする政府関連のLINE公式アカウントは、更新が止まっている。警察庁の公式アカウントには「当面の間、運用を停止しております」と記されている。
総務省は「LINEに対する報告徴収」として、利用者情報の管理の状況などについて電気通信事業法の規定に基づき報告するよう求めた。さらに、個人情報が適切に管理されているかを監督する個人情報保護委員会もLINEに報告を求めたほか、立ち入り検査も行った。
LINEといえば家族や知り合い、悪意ある者の盗み見や、スマホの紛失・置き忘れによる情報流出、電話帳から友だちが自動で追加されるシステム、なりすまし詐欺、トークのやり取りでの人間関係のストレスなど、ネガティブな一面もささやかれてきた。
今回のニュースを教訓にすれば、基本的に業務上の連絡はビジネス専用のツールで管理するに越したことはない。「LINE」というキーワードで関連ニュースを検索すると、今までの動きや体制が見えてくる。LINEに限らずフリーのアプリのビジネス利用は、提供元のニュースなどを常にウオッチして体制や姿勢を見極め、定期的に利用の見直しを行うのがよい。
個人利用に限っていえば、LINEはみんなが使っていて連絡がつきやすく、総合的には便利この上ない。思えば東日本大震災で生活インフラがストップして安否確認も難しかった際、TwitterやFacebookのダイレクトメッセージで連絡がつき、その利便性が心に染みた。2011年6月、「こういう時にこそ大切な人と連絡を取ることかできるサービスが必要だ」という想いの元、生まれたのがLINEであった。個人の場合、クレジットカードや住所番地、免許や保険証など、個人が特定できる内容を避け “転ばぬ先のつえ”的に自衛しつつ使っていくしかない。
業務連絡でのLINE利用をやめる企業が続々といわれる一方、企業が提供するサービスを見直す動きは思いのほか鈍い。配達日時の変更や再配達依頼が行える宅配便や郵便局、料金や使用状況が確認できる電力会社やガス会社、チラシやセール、新製品情報を流すショップなど、登録者数や利便性の高さを重視し、サービスは停止せず今まで通り行い、今後の情勢を見定める動きが主流といえる。
LINEの出澤社長が4月23日夜に都内で行った記者会見によれば、中国からの完全アクセス遮断・業務終了とトークデータの国内完全移転し、プライバシーポリシーと情報保護の強化とともに、政府・自治体向けの公式アカウントに関しては、保管だけではなくアクセスについても完全国内化を行うと述べた。自治体向けのコロナワクチン予約システムに関しても、完全国内化で提供する見通しだという。
ユーザーへの分かりやすさに対する配慮が欠けていたことを問題視し、今後は信頼回復を第一に、明確な素早い対応を行う姿勢を明らかにした。記者会見の内容の全文はニュースサイトで閲覧できる。
ところで、3月1日、ヤフージャパンをはじめとする200超のサービスを提供するZホールディングスは、LINEとの経営統合の完了をリリース。「検索・ポータル」「広告」「メッセンジャー」を根幹とするとともに、「コマース」「ローカル・バーティカル」「フィンテック」「社会」という新領域にも集中的に取り組んでいく姿勢を明らかにした。
国内の大手企業であるZHDグループに組み込まれたLINEは、今後、日本の人々の国民的な連絡手段として存在し続けるだろう。そこで問われるのは、何よりもユーザーを大切にする「心」だと思う。
われわれが見守るべきは、政府や自治体、企業などが安心して情報提供を行える場を提供できているかだろう。今後、政府や自治体がどう見定め、サービスをいつ再開するかも興味深く見守っていこう。
※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です
※「Twitter」はTwitter,Inc.の商標または登録商標です
※「Facebook」はFacebook,Inc.の商標または登録商標です
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」