
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
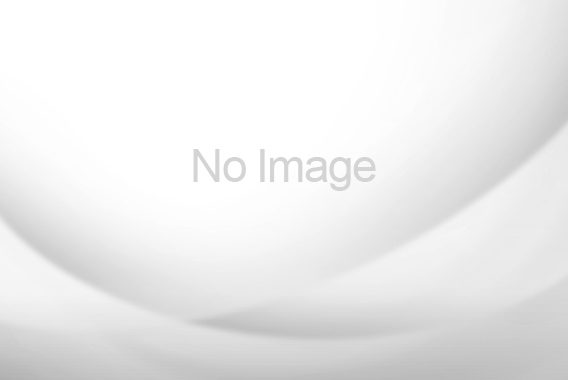
近頃よく聞く「デジタルアレルギー」という言葉。文字通り、デジタル機器やDXに対するアレルギー、拒否反応が起きる状態をさす。連絡は音声電話、情報源はテレビ・ラジオと紙媒体、買い物は実店舗主義、いまだにガラケー、スマホをアップデートせず使っているなど、現状に満足し、新しい機器や技術になじもうとしない人は、それなりに存在する。新しもの好きの筆者からしたら「もったいない」と感じる話だが、気持ちは分からなくもない。
コロナ禍で、テレワークやリモート会議への移行、おうち時間の増加などもあって、デジタル機器やネットワークの必要性や利用する機会が増えた。そんな中で、デジタルが苦手だったが使ううちに慣れた、利便性や楽しさに気づいて日常的に使えるようになった、操作や設定のモヤモヤを解決していくうちに突破口が開いた、という人も多い。
昨年公開されたIPAの「DX白書2021」は、「日米比較調査にみるDXの戦略、人材、技術」という内容で、我が国のDXの遅れを浮き彫りにしている。このDX化の遅れの原因の1つが、主に40代以上の企業の経営層もしくは管理職の「デジタルアレルギー」にあるのではないかとの声もある。
中高年層は、若いころからデジタル機器になじんできたわけではなく、歳を重ねてからの学びであるので大変なのはもちろんだ。その上、ビジネスで指示を出す立場にあり、デジタルを業務上扱わざるを得ない立場となる機会は比較的少ない。このため、デジタルアレルギーを抱きやすく、アレルギーを克服する機会にも恵まれず、モヤモヤを抱えたまま毎日を過ごしているケースもあるだろう。
デジタル庁が2021年9月1日に発足され、企業がDX人材育成に力を入れる中、大企業人材の約4割がDX業務にネガティブとのアンケート結果もある。背景には、経営層や役職層が「これからはデジタルの時代だ」「DX化が必要だ」と唱えつつも、行動や思考にデジタルへの積極性が見られないこともある。この場合、大なり小なりデジタルアレルギーを抱えているのでは、と考えてもよいだろう。DX推進がうまくいかない企業はそうした状況を疑ってみてもよいのではないだろうか。
「しなければならない」「必要だ」と、周りや自分に言い聞かせるように唱える場合、「口だけ」に終わることが多いのは世の中のセオリーだ。経営層や役職層がアレルギーやバイアスを抱えたままDX化を推進しても前向きな結果は得られず、「やはりダメだった」「やはりウチには合わない」などと傷を深くする悪循環を招きかねない。
DX化へのネガティブなベクトルは、「DXによる業務変化に果たしてついていけるか」「DXやAIで自身の仕事やポジションを失うかも」など、多くの人がDXに対して抱く危機感とシンクロして、さらに企業のDX化を阻む。DXに対するアレルギーや先入観克服は一筋縄ではいかない。
逆にデジタルを信じすぎる、期待しすぎる、頼りすぎる姿勢もバイアスの1つといえる。これらのバイアスやアレルギーを克服するには、デジタル・アナログにこだわらない、自身が苦手・得意などの先入観にとらわれず、常に目標を見失わない、広い視野と自由で柔軟な姿勢が必要だ。
自社業務の新規開拓、改善点や要望実現、効率化に対し、あらゆるジャンルから考えられ得る候補を挙げ、冷静に手段やプロセスを導き出し、シミュレーションやデータ比較で誰にも分かるよう「見える化」して冷静に検討する。あくまで顧客や社員の利益を第一に考え、あらゆる可能性を想定して、納得がいくまで検討し最善の手段を導き出そう。
そこで結果的にデジタルを選んだとしても、「納得がいくまであらゆる手段を想定して検討」した結果、たまたま有効であると判断しただけのことだと捉えよう。検討時には、ささいな点や初歩的なことであっても、恥ずかしがらず疑問点はすべて解決しておくのが、デジタルアレルギーを乗り超えて後悔しない答えを出すコツでもある。
デジタルを苦手に思う気持ちやDX化についていけないと思う気持ち、逆にデジタルや最新技術に頼りたい気持ち、デジタルを導入しないと時代に遅れるなどは雑念としていったん脇に置く。ビジネスの本来の目的を忘れずに、自由な発想であらゆる手段を想定し、納得する意思決定を行うことが、デジタルアレルギー克服の第一歩となるはずだ。
新しい技術に対して詳しい知識がなくても、実際にプログラムなどを行えなくても、新しい技術をビジネスに生かせないかをイメージすることは誰でもできる。「この業務を自動化できないか」「製造の流れをもっと効率化できないか」「監視システムを無人化できないか」「効率的なコミュニケーション手段はないか」「顧客の流れを分析して効果的な棚や商品の配置を導き出せないか」などは現場の人間や管理する人間なら容易に気づける。
気づきや声を取り上げ、柔軟に検討できる組織づくりが大切だ。現場から集めた「こうしたい」「ああしたい」を気軽に相談できる、DXの知識やノウハウに長けた外部機関があればよい。自社に合ったコンサル機関やソリューションを、ステークホルダーおよびWebや公共相談窓口などから見つけていくのも、DX化推進の突破口になるだろう。
DX化を図る上で重要な視点の1つは、優秀な外部人材の確保とされる。新技術や時代の最先端の流れ、データ分析や統計学などに長けていて、柔軟に対応できるノウハウをもつ、「DXナレッジ」の高い人材を招き、組織に新しい風を入れる発想だ。社内の人材を教育したり、デジタルが得意な社員を抜てきしたりするのも手だが、過度な負担や重圧がかかる可能性などもある。外部人材の活用という選択肢も考えたい。
最後に「DX白書」の巻頭の一部を要約して紹介しよう。「経営者自身が自分は何のため誰のためにビジネスをしているかという覚悟とビジョンを提示し、リーダーシップを発揮することが何よりも大切」「ビジョンを実現するために組織を変え、メンバーも問題を発見し自ら動けるようマインドを変え、顧客と直接つながるしくみを整備し、これらを実現するために新しい技術がある」と発信している。DX化は、「こうしたい」「ああしたい」をさらに効率よく容易に実現できる有効な手段だ。柔軟に取り入れて、明るい未来につなげていこう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」