
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
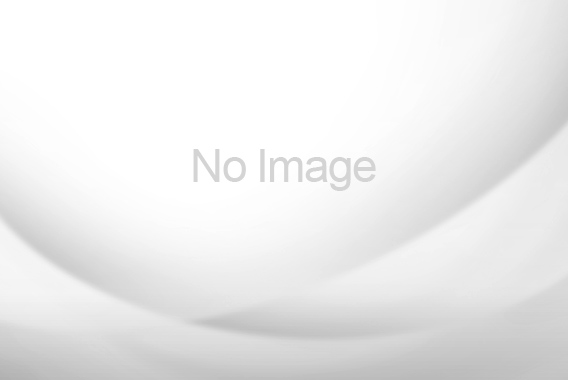
最近耳にする「デジタルツイン」、IoTなどで物理空間の情報を集め、サイバー空間内にリアル空間をまるごと再現し、将来を予測する新しい技術のことだ。言葉が生まれたのは1990年代だが、現実空間とデジタル空間を対にして扱うこと自体はさらに古く、1970年のNASAのアポロ計画に遡る。飛行中に酸素タンクが爆発する事故に見舞われたアポロ13号の生還は、地球上でスタッフが行ったシミュレーションのおかげという。
現実世界の環境を仮想空間にコピーした、鏡に映したもう1つの世界のようなイメージで「デジタルツイン(デジタルの双子)」と呼ぶ。背景にはIoT、AI、通信技術、クラウドなどの進化があり、IoTで取得したさまざまなデータがクラウド上のサーバーにリアルタイムに集められ、AIが分析、処理を行ってよりリアルな物理空間が再現される。
デジタルツインは近年、主に製造業で活用されている。例えば工場設備の摩擦状況や稼働状況をリアルタイムなデータで把握、シミュレーションで破損や故障、タイミングを予測し、予期せぬダウンタイムの発生を防止するほか、必要なタイミングで必要な部分をメンテナンスし、効率化やコスト削減が図れる。とある工場では、人員の稼働や業務負荷の状況をリアルタイムで収集・分析、最適なスケジュールや人員配置で効率化を図っている。
デジタルツインは現実世界の状態を継続的に感知するセンサー、データを送る通信ネットワーク、データを集約・管理・活用する情報基盤、という3つの要素で構成される。近年のIoT、AI、5G、クラウド、携帯端末、3Dモデリングなど技術の発展により、ビジネス分野を含め広く活用されるようになってきた。
さらに、デジタルツインがトレンドワードに選ばれたり、新型コロナウイルスの感染拡大シミュレーションに使われたりして知名度も上がってきた。米Deloitte社の調査によれば、デジタルツインの世界市場は年率38%で成長、2023年には160億ドルに達するという。
疑問として挙がりがちなのが、「デジタルツインとシミュレーションは何が違うの?」という点だ。デジタルツインはもちろんシミュレーションの一種であり、シミュレーションの技術の1つでもある。従来のシミュレーションとの違いはリアルタイム性と、現実にある機器と仮想空間内のデータが常に同期して、現実も仮想空間も発展し続ける点だ。まさに仲良く育つ双子のようだ。
最近では現実世界のセンサーのほか、仮想世界にバーチャルセンサーを置き、双方からデータを集めることも行われる。これにより現実のセンサーの数を減らせて効率化につながったりもする。そのほか、従来現実で行ってきた実証実験を仮想世界で行ったり、プロトタイプを仮想世界上で作ったりすることもできる。このように現実をある程度仮想でカバーできれば、経費節減や効率化以外にも、危険予測による事故のリスク回避などの利点は多い。なお、デジタルツインの仮想空間に集まって共同作業が行えるのも、このご時世では有用だろう。
小売業ならショッピングセンターや街中での人の流れをモデル化すれば、効率的な通路の設計や商品の配置が見えてくる。医療では、手術や治療のシミュレーションを仮想空間で行っておけば、より安全で速やかな治療が実現する。
さらに都市まるごとを3Dデジタルマップで作成し、街中に取り付けたセンサーのデータや民間の情報と共に、自動運転、配達ロボットなど先端技術の導入や災害対策、ネットワークの輻輳対策、街づくり、生活インフラの供給などに総合的に役立てる構想も盛んだ。
米GEのGE90エンジンは大型ジェット機に採用される世界最大級のエンジンで、巨大なサイズからメンテナンスコストが高止まりになっていた。2019年、デジタルツインにより時間経過によるエンジンブレード損傷の予測を可能にし、メンテナンス費用を数千万ドル削減した。GEのデジタルツインは、使い続けることによってアルゴリズムの学習が促され、精度向上が期待できる仕組みとなっている。
鹿島建設は2020年、資機材の位置や稼働状況、人の位置やバイタル情報をリアルタイムに3次元で表示する「3D K-Field」を、大規模複合施設「HICity(エイチ・アイ・シティ)」に導入。施設や自律走行バスの混雑状況、スタッフやサービスロボットの稼働状況を把握し、来場者の満足度向上や合理的な管理・運営をめざす。
2014年に始まったシンガポールの「バーチャル・シンガポール」プロジェクトは、スマートシティーのはしりともいわれる。3Dモデル上でさまざまなシミュレーションが可能なアプリを提供、環境や防災などのシミュレーションからインフラ・エネルギー管理など幅広い分野での活用をめざす。シンガポール市街地で開催されるF1レースでは、事故が発生した場合何万人もの観客を速やかに避難させる必要がある。バーチャル・シンガポールでは、観客が持つセンサー端末からの情報を基に人の流れを表示、避難経路が策定される。
内閣府が2016年から提唱・推進する「Society 5.0」は、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の未来社会だ。IoTで全ての人とモノがつながり、知識や情報が共有され、課題や困難を克服していく構想だ。デジタルツインという言葉こそ出てこないものの、実現には欠かせない要素となるだろう。
2020年2月に出された東京都の「スマート東京実施戦略」には、「すべての都民が幸せを実感できる都市・スマート東京の実現に向けて」というコンセプトと共に、都民のQOL(Quality of Life)の向上に向けて、東京を誰もが快適な生活を送れる、活力に満ちた「スマート東京」へと進化させるべく、デジタルテクノロジーの力で未来に向けた明るいシナリオを描く。デジタルツインはスマート東京の実現を支える重要な要素とされている。
国土交通省は2021年3月、「都市空間のデジタルツイン」として、サイバー空間に日本全国の都市を3Dで再現する、3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」を公開した。都市活動のプラットフォームデータとして、日本中の3D都市モデルを整備。3Dデータのほか、人の流れや人口、防災、都市計画、農水統計などのデータセットを公開し、誰もが自由に活用できるようにした。
総務省の情報通信白書令和3年版「デジタルで支える暮らしと経済」にある「デジタルツイン」に関するコラムには「従来は製造業を中心に業務効率化を中心に活用されてきたデジタルツインだが、今後は街づくりなどより広範な領域の付加価値向上に活用されていく可能性がある。また、デジタルツインの適用範囲が広がることで、行政機関や民間事業者を含めた組織を跨いだデータ統合・活用のニーズが増加していくことが想定される」とある。
デジタルツインはまだ歩き始めたばかりの技術だ。IoTもAIも、通信技術も発展途上だ。今後ITの発展と共に、さらなる広いジャンルに活用されていくのは間違いないだろう。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」