
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
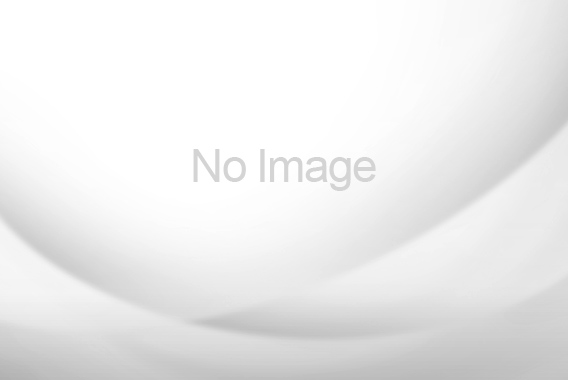
国内で新型コロナワクチンを少なくとも1回接種した人が、6月1日時点で1000万人を超えたニュースが流れた。これで国民の8%がワクチン接種を受けた計算になる。このときの接種ペースは1日平均56万回。一刻も早く菅首相が唱える1日100万回の達成を急ぐ。なお、日本で接種を行うファイザー社のワクチンは3週間空けて、2回の接種が必要だ。
首相官邸ホームページの「新型コロナワクチンについて」には、「これまでのワクチン総接種回数」が公表されている。2021年6月現在の数値は、医療従事者等850万回、高齢者等990万回(ともに6月7日時点)、そのほか高齢者等の接種状況のグラフや、日別、都道府県別の実績が掲載され興味深い。
接種は自治体(市区町村)単位で行われ、6月末までに高齢者の2回分の量を自治体に供給。7月末を念頭に希望する高齢者が2回の接種を終えられるよう、政府を挙げて取り組む方針だ。見通しがついた市区町村から接種を開始する。
新型コロナワクチンについて、厚生労働省の「新型コロナワクチンQ&A」ページが参考になる。概要を知るには「新型コロナワクチンを受けるには」の動画を見るとよい。なお、新型コロナウイルスの状況は、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症について」を参照するとよいだろう。
市町村からクーポン券(接種券等)と「接種のお知らせ」が届いた人は、接種の予約を行う必要がある。予約はお知らせに従って電話やインターネットで行い、予約した日時に接種会場で接種を行う。2回目も予約が必要となる。
4月に市から届いた母の接種券には「ご予約方法の案内」が添付され、5月1日から、電話、インターネット、LINEの3手段で接種予約を受け付ける、とされていた。接種予約は、接種券番号と接種を受ける人の生年月日が分かれば代行もOKだ。母は少し前から施設に入所しており、筆者は予約せずに済んだものの、周囲からは電話がつながりにくくて困った、ネット予約で市のサイトがつながりにくかった、エラーで進めなかった、などの話も聞いた。
そのうち続々と、「ネットも電話もパンク。窓口には人だかり」などという、各自治体の様子がニュースで流れてきた。電話やネットがつながらず不安になった高齢者が、役所の窓口に詰めかけた。ちなみに窓口では予約は受け付けていない。一方で、高齢者自身が慣れないスマホを駆使してやっと予約できた、などのニュースもあった。
予約のための入力作業の支援窓口を開設し、高齢者が長蛇の列をなした自治体もある。事前にスマホでの予約の練習会を開いたり、自宅訪問による予約代行を実施したり、大学生らのボランティアを置いたりなど、自治体それぞれの工夫が目立つ。ほかにもスマホショップが代行または教えるサポートサービスを無償で行った話もある。
3週間空けて2回目の接種の予約は、さらに難易度が上がる。今は高齢者のみだが、この先、ボリュームゾーンに入ったらどうなるか心配だ。受付電話回線を増やす、インターネット回線やサーバーを増強する、スタッフをさらに動員する...、果たしてそういう問題だろうか。
筆者は、「つながった者から予約できて枠が埋まる」早い者勝ちの方法こそが問題ではないかと思う。命に関わることで気がはやるのは当然で、われ先にと殺到するのは目に見えている。イベント予約ならまだしも、ワクチン接種の予約がこんなやり方でいいのかと危惧している。
願わくはある程度期間の余裕を持って、対象となるすべての人に、行ける会場と日時の組み合わせ候補を複数提出できる仕組みがほしい。提出のない対象者には自治体側から問い合わせを行うシステムもあるとよい。対象者の希望が出そろったところで、それらを自治体側で調整してスケジュールを組み、通知する形が理想ではないかと個人的には考えている。
予約と接種の調整の方法や手段について、各自治体にお任せなのも問題かもしれない。自治体ごとに接種や予約の方法が違うので、情報交換の範囲が限定的となる。統一したシステムを各自治体に提供できればよかったのではないかと思う。
実はこの混乱を見かねたチケット予約の「ぴあ」がワクチン接種予約受付サービスの提供を5月14日開始した。リリースによれば、「国内での新型コロナワクチン接種に際し、各自治体にて、予約受付時のトラブルや窓口への行列が相次ぐ中、チケットぴあの仕組みを活用した新型コロナワクチン接種予約受付・抽選サービスの提供を開始します。今後の大規模接種や若年層への普及に向け、(中略)大規模なイベントのチケッテング業務を受託してきたノウハウを生かせるものと判断しました」という。
ぴあは、新型コロナワクチン接種券について、接種日や接種会場、施術時間帯などの個別予約受付と、その抽選が可能となるシステムを提供する。リリース時点で利用を希望する自治体との交渉を開始しており、稼働させる予定の自治体もあるという。先述した、先着順ではないシステムに近い。
政府および各自治体は、できる限り混乱を招かない、できる限り平等にそして全員が滞りなく接種を受けられるよう、全力を尽くすべきだ。ぴあのほかにも技術を提供できる企業もあるだろう。電話やネットの回線増強やシステムの見直しはもちろんだ。なお、医療従事者以外にも、予約システムの従事者にも接種を優先してあげられたら、とも思う。
我々にできるのは、全員接種はできると信じ、落ち着いて判断・行動することだ。予約は自治体ごとなので、自治体の広報やWebページなどの情報、届いた資料をよく読む。SNSなどにはワクチンに関するノウハウも公開されているが、間違った情報や自分の自治体には合致しない情報もあるので冷静な目が必要だ。「優先して予約ができます」「お金を払えば受けられます」とかたり、詐欺をはたらく例も報告されている。うかつに乗らないよう注意しよう。
接種前の準備や接種後のケアへの不安もあるが、先述の公的なサイトでおおかた取り除けるはずだ。もちろんワクチン接種を行えば100%安全というわけではない。マスク、手洗い、3密を避けるなどの基本を守り、新しい生活様式に適応していきたい。高齢者の予約で、スマホなどIT機器を使おうとする高齢者の心意気に胸を打たれた。総務省は高齢者1000万人に対して、スマホやマイナンバーカードの使い方の講習を行う構想も示した。新しい"常態"の訪れを感じる。我々もうかうかしてはいられない。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【T】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」