
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
自然環境の変化が著しい現代において、多くの企業にとっての懸念事項は「いつ発生するかわからない災害」だろう。筆者自身も、大規模な断層の近くに住んでいることもあり、Windowsタブレットで地震情報を常時表示している。これを始めたのは東日本大震災がきっかけで、すでに長い年月がたつが、日本における地震の多さには驚かされる。タブレットで速報を視覚と音(警報)で確認できるのでスマートフォンやテレビの通知より一歩早く、心構えや対策ができ、なかなか役に立っている。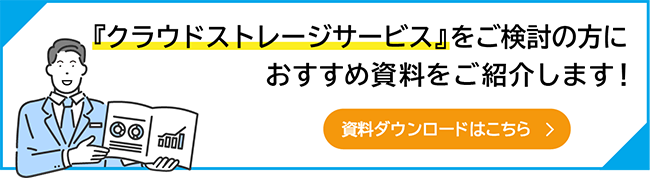
実際、2024年の元日に発生した能登半島地震からも分かるように、自然災害はいつ起こるか予測がつかない。そして、いつ、どこで、誰の身に起こるか分からない。それが現実だ。さらに「ウェザーニュースLive」を日常的に流していると、地震の他、ゲリラ豪雨や台風、雷、豪雪など、異常気象による災害が全国各地で起こっているのを実感する。気候変動の影響なのだろうか、災害の頻度も規模も確実に深刻化しているように思える。
私たちの生活は、こうした自然災害によって容易に脅かされる。避難生活を余儀なくされたり、損壊した家屋の片づけ、不完全なインフラ環境での生活が続いたりすることもある。災害は人々にとって深刻な問題だが、企業にとっても同様だ。社員それぞれが被害を抱えた中、どうやって事業を継続していくのか、大きな課題となる。
そこで重要なのが「BCP(Business Continuity Plan)」だ。自然災害、テロ、パンデミックなどのリスクを事前に想定し、その影響を最小限に抑え、非常時でも事業を継続できるよう計画する取り組みだ。BCPはさまざまな解説記事があるので、詳細はそちらに譲るが、今回、取り上げたいのは、BCPと密接に関わる「防災テック」についてだ。
「防災テック」は、防災とテクノロジーを掛け合わせた造語で、近年注目が高まっている分野だ。地震・台風・津波・洪水といった災害予測、被害の把握、避難や復旧支援などを目的とした、最新の技術やサービスをさす。より具体的には、緊急地震速報などによる災害予測、水位監視システムやドローンによる被害状況の可視化、防災アプリを通じた避難支援や安否確認、衛星通信を利用した非常時の通信手段の確保など、災害時の対応をより迅速かつ効率的に行うための技術が次々と登場している。こうしてAIやIoT、クラウド技術などを活用、災害の予兆を検知したりリアルタイムで情報共有したりと、テクノロジーはまさに「命を守る道具」として進化している。
日本は、世界でも有数の「災害大国」といわれている。そういわれるゆえんは、内閣府「防災情報のページ」にある「災害を受けやすい日本の国土」でも明らかだ。これによれば「我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい」と明記され、日本は世界の0.25%の国土面積にもかかわらず、世界全体の地震(マグニチュード6以上)の約20%が日本で発生しているという統計も添えられている。
こうした背景を受け、政府は「防災立国推進」を掲げつつ「令和7年版 防災白書」において、2024年10月に「防災庁」の設置の方針を打ち出している。防災庁は防災の専門機関として平時からの備えを抜本的に強化、非常時には政府の司令塔として機能することを目的としている。防災庁は2026年度中の設置をめざし、2024年11月には「防災庁設置準備室」が内閣官房に発足。12月には人命最優先の「防災立国」を早急に構築するべく、総理を議長とした「防災立国推進閣僚会議」を開催、さらに2025年1月には、有識者20名による「防災庁設置準備アドバイザー会議」がスタートした。その後、防災教育、避難生活、デジタル連携、事前防災の在り方などを8回にわたり議論、6月にとりまとめが行われた。
とりまとめの「概要」によれば、「我が国の防災全体を俯瞰し、産官学民のあらゆる力をつなぎ合わせ、我が国にふさわしい防災の在り方を中長期的に構想・実現する『司令塔』となる組織が必要」とし、その司令塔たる「防災庁」は「国民の命と暮らしを守り抜く」ことを究極の目的とし、「防災に関する基本的政策・国家戦略の立案」「平時における徹底的な事前防災の推進・加速の司令塔」「発災時から復旧・復興までの災害対応の司令塔」という3つの機能を担うという。
災害大国・日本で暮らす以上、自然災害から逃れることはできない。だからこそテクノロジーを駆使して災害リスクを最小限に抑える取り組みが不可欠だ。BCP、防災テック、防災庁設置――これらの動きは「起こってから対応する」のではなく、「起こる前に備える」ことへの明確なシフトといえる。
災害発生時、被災地周辺のすべての人に確実に情報が届き、適切な対応が取られなければ、「国民の命と暮らしを守り抜く」ことはできない。例えば、津波警報1つとっても、スマートフォンの通知だけに依存するのは不十分である。高齢者や、スマホの通知に気づかない人々にも対応が必要となるため、多重化された情報伝達手段の整備が欠かせない。
加えて、優れたテクノロジーで災害を予知・監視できたとしても、それらが適切に連携、共有、通知されなければ意味を成さない。特に重要なのは、災害時における通信インフラの確保である。災害後の混雑はもとより、遠隔医療や遠隔操作などの大容量通信にも耐える、安定した回線の確保は極めて重要だ。
こうした課題に対応するため、内閣府は2021年に「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム(防テクPF)」を設置した。目的は、地方公共団体が抱える災害対応上の課題(ニーズ)と、民間企業等が持つ先進技術とをマッチングさせ、効果的な活用事例の共有と横展開を進めることである。
このプラットフォームでは、登録団体間の交流の場としてマッチングセミナーも開催されており、直近では2024年2月に第10回セミナーが実施された。「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム 活用事例」では、「情報通知」「避難生活支援」「防災学習」など、地方公共団体における先進的な事例が紹介されている。
ところで、防災テックの活用領域は、主に以下の4つに分類できる。
①予測・監視系
AIによる災害予測、IoTセンサー、ドローン監視などにより、災害の兆候をいち早く把握する。
②避難・情報提供系
多言語対応の防災アプリ、ARナビゲーション、防災チャットボットなどにより、正確で迅速な避難行動を支援する。
③備蓄・ライフライン支援系
スマート非常食管理、太陽光・蓄電池連携システム、水浄化装置や発電機、衛星通信など、非常時の生活維持を技術でサポートする。
④復旧・復興支援系
ドローンやロボットによる被害状況把握や救助活動、ブロックチェーンでの支援金管理、生成AIを活用した被災者ニーズの把握などで、人手不足の現場で支援の自動化・効率化を実現する。
その他、災害体験VRや、Wi-Fi完備・発電機付きのスマートシェルターなど、体験型・生活密着型の技術も注目されている。
ところで、国土交通省では、緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE(テックフォース)」を組織、大規模災害時における迅速な被害把握や復旧支援を行い、地方自治体の災害対応を支援する存在として重要な役割を果たしている。主な支援内容は、防災ヘリによる被災状況の把握の他、最新技術を活用したドローン、遠隔操作式の重機などを復旧支援などに活用している。
テクノロジー利用に関しては、災害対策用ヘリコプターや監視カメラ等で被災現場の映像情報を衛星通信車や小型衛星画像伝送装置(Ku-sat)により、役場などにリアルタイムで配信、また、これらの装置は通信が遮断した被災地における通信回線の確保も可能という。その他、通行可能なルートをTEC-FORCEが調査、自治体や救命・救助部隊などに情報提供している。
こうしたテクノロジーの力をどう生かすか。いかに最先端技術を活用するか、ではなく、いかに確実に「命と暮らしを守り抜く」か、が重要だ。防災テックは、まさにその最前線での「実装力」が問われる分野である。
ここまで主に公的機関の取り組みを紹介してきたが、これを機に、企業においても、会社と社員の「命と暮らしを守り抜く」ための従来の体制を見直し、「防災テック」の導入を検討することが重要だと思う。先述の地方公共団体による活用事例も実際の導入を考える上で有用なヒントとなるだろう。最初の一歩としては、災害時の連絡にも有用な、あらゆる端末で利用できる社内ビジネスチャットなどの導入から始めるのが一案だ。
その他、自社内での災害発生予測装置や警報・警告装置、パソコンおよびスマホアプリ、さらには復旧活動を支援するためのドローンや遠隔操作重機などのサービス利用も、検討する価値がある。具体的には、地震や津波、水害など身近な災害リスクに対する早期警報システムがおすすめ。センサーからのデータをAIがリアルタイムで解析し、災害発生前から自社業務において、事前対応が可能となる。
また、社内の災害対応訓練にVRやARを活用すれば、実際の災害に近い状況のシミュレーションが可能となり、従業員の初動対応力を高められる。加えてクラウド技術によるバックアップ体制や、災害時にも対応可能なリモートワーク環境の整備も、BCP(事業継続計画)を強化する上で欠かせない「防災テック」の1つだ。「防災テック+ソリューション」などのキーワードで検索すれば、多様なサービスや導入事例が見つかる。それらを積極的に調査・検討したり、最寄りのベンダーや公的相談窓口に相談したりするのもよいだろう。
海外に目を向ければ、IBMやGoogleといったグローバル企業が高度なデータ分析を通じて災害予測モデルを構築、迅速な情報提供や被害の軽減に貢献している。自社で蓄積したノウハウや防災テックの技術を、地域や他社に還元することも、社会的貢献の1つとなる。
将来的には、生成AIやIoT、クラウド技術などの進化により、防災テックもさらに高度化する。より精密な災害予測やリスク評価、迅速な情報収集・救援・復旧などがテクノロジーによって一層充実していくだろう。こうした技術発展の動向に目を向けつつ、自社のBCP体制を見直し、もしもの際に社員と事業を守るための体制構築を進めていこう。災害は「起きてから」ではなく「起こる前」に備えることが重要だ。今こそ防災テックを活用し、「命と暮らしを守り抜く」企業の力を、改めて問い直すタイミングだと思う。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「自分流ブログ入門」「70歳からはじめるスマホとLINEで毎日が楽しくなる本」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
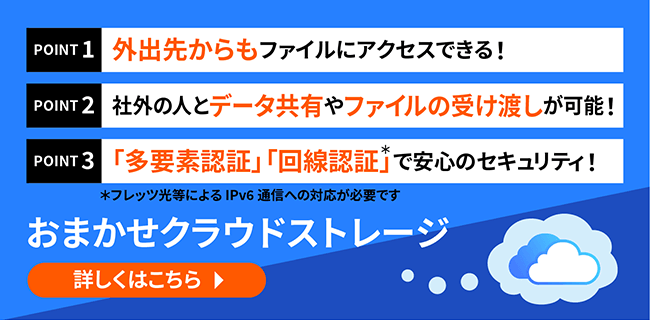
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」