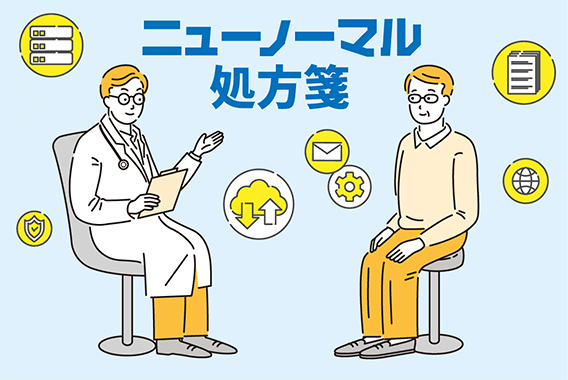
ニューノーマル処方箋(第83回)
今さら聞けない「IPv6」と「IPv4」の違いを簡単に解説。仕組みやメリット・デメリットとは?

昨年9月、この連載の「IT導入補助金を活用しよう!~概要から申請まで」で、経済産業省・中小企業庁が行う「IT導入補助金」を紹介した。この制度は「中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金」というコンセプトで2017年に始まり、本年度で7回目を数える。
本年度の「IT導入補助金2023」は、3月下旬から申請受付を開始している。基本的に業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のためのITツール等の導入費用を支援する目的は変わらないが、若干の変更がある。
本年度の変更は、インボイス制度への対応を見据えたITツール導入の支援のため、補助額の下限撤廃や引き下げが主となる。中小企業庁「生産性向上を目指す皆様へ」には、「インボイス対応に活用可能!安価なITツールの導入でも利用可能!」という見出しで本年度の概要が書かれているが、2ページ目の表は、赤字で変更点が理解しやすく示されている。
例えば、「通常枠」のA類型では補助金の下限が「30万円~150万円」から「5万円~150万円」に引き下げられた他、クラウド利用料の補助期間が1年分から最大2年分までに延長された。「デジタル化基盤導入枠」では、3/4以内の補助率の「50万円以下」にあった下限(5万円~)が撤廃された。インボイス対応で、便利なITツールの導入を検討している企業も多いと思う。ぜひ活用を考えたいところだ。
「IT導入補助金」とは、経済産業省・中小企業庁が行う中小企業・小規模事業者向け補助金・給付金の1つ。中小企業庁のパンフレット「やるぞ生産性向上!」には、IT導入補助金を含む中小企業・小規模事業者向けに生産性向上を支援する4つの補助金が紹介されている。これらの補助金は必要に応じて活用するとよいだろう。
中小企業庁の「ミラサポplus」内の「IT導入補助金とは」では、IT導入補助金は「中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助金」と定義される。ここでの「ITツール」とは「業務効率化のために新たに導入されるソフトウエア製品やクラウドサービスなど」を指す。
IT導入補助金を「どんなことに役立てるか、何を補助してもらえるのか」を具体的に理解するには、「ITツール利用者の話」や「ITツール活用事例」を参照するのが早道だ。ここには、RPAの活用で業務時間を大幅削減した製造業や、販売管理で経営に関する情報を一元管理する卸・小売業、3次元CADの活用で提案力が向上した建設業など、ITツールで効率化に成功した事例が挙げられている。
「業種別お悩み解決ITツール機能」も参考になる。「全業種共通」で、自動化・効率化ツールRPAの導入が多くアドバイスされているのは、広い業種でRPAが業務効率化に役立つ、最近の流れでもある。ここに掲げられる事例は、年ごとに少しずつ時代に合わせて変えられている。また、中小企業庁のデジタル化支援サイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」も役に立つだろう。ここでは、経営課題やデジタル化への取り組み状況を確認し、専門家からデジタル化に向けたアドバイス、補助金などの最適な施策、ITツール機能の紹介などがもらえる。
補助金の種類と補助対象は公式サイト「IT導入補助金2023」内の「IT導入補助金について」が詳しい。各枠の交付規定や公募要領もよく目を通しておこう。先述の補助額下限の撤廃や引き下げなど、常に変更点が生じる可能性も踏まえ、常に最新の情報をチェックするよう心がけよう。
ここで改めて、補助金制度のおさらいをしよう。ラインアップについては、「通常枠(生産性向上のためのITツール導入費用を支援する)」に加え、会計や受発注、決済、ECソフトの導入を支援する「デジタル化基盤導入枠(パソコン、タブレット、レジなどハードウエアの導入費用も支援)」、セキュリティサービス利用を支援する「セキュリティ対策推進枠」などがある。
具体的にいえば、インボイス対応を含む会計関連の導入なら「デジタル化基盤導入枠」が、勤怠管理やコミュニケーション、定型業務の自動化(RPA)などの業務効率化なら「通常枠」、セキュリティ関連なら「セキュリティ対策推進枠」という選択となる。
補助金の対象となるITツールは、事務局にパートナーとして認められた「IT導入支援事業者」により登録され認定を受けたものに限られるので、特に留意が必要だ。ゆえに「IT導入支援事業者・ITツール検索」から検索するのが効率的だ。「セキュリティ対策推進枠」も、対象が「セキュリティサービスお助け隊」サービスに限られるので注意が必要だろう。
申請・手続きについては、大まかに「支援機関に経営課題や課題解決のためのITツールを相談」→「導入したいツールやパートナーを決定、必要な情報を提出」→「審査を経て採択されたら、ITツールを導入・活用」という3ステップとなる。1ステップ目は必須ではないが、支援機関(よろず支援拠点、商工会、商工会議所、ITコーディネーターなど)の知恵を借りることが早道かもしれない。
本年度のスケジュールを確認すると、現状では枠ごとに1次締め切りや2次締め切りなどと申請期限が決まっている。予算に余裕があれば3次、4次と続くが、申し込みが殺到すると早期に終了する可能性もある。スピード感のある対応が必要となるだろう。なお、交付決定の連絡が届く前に発注や契約、支払いなどを行ってしまうと、補助金交付を受けられないことがあるので、この点にも気を配りたい。
具体的な申請は「申請・手続きフロー」によれば、本事業への理解→IT導入支援事業者の選定とITツールの選択→「gBizIDプライム」アカウントの取得とIPA「SECURITY ACTION」での宣言および「みらデジ経営チェック」の実施→交付申請→交付決定→補助事業の実施、というプロセスとなる。
gBizIDプライムアカウントの発行には「おおむね2週間」。もちろん、自社課題の洗い出しから相談・決定のうえ、IT導入支援事業者とツールの選定、支援事業者との共同作業による申請までには、それなりに時間も手間も必要となる。補助金活用を考える場合、目標とする締め切りまでに余裕をもったスケジュールを設定し、早め早めに動くのがよい。本年度のIT導入補助金は、インボイス対応を見据えて門戸が広げられている。相談や申請が混み合うことは容易に想像がつく。まずはサイトや公募要領などをよく読み、補助事業について理解しつつ、自社の経営・業務課題を洗い出し、パートナーやITツールの当たりを付けて相談もしくは申請に向けて動こう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」