
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
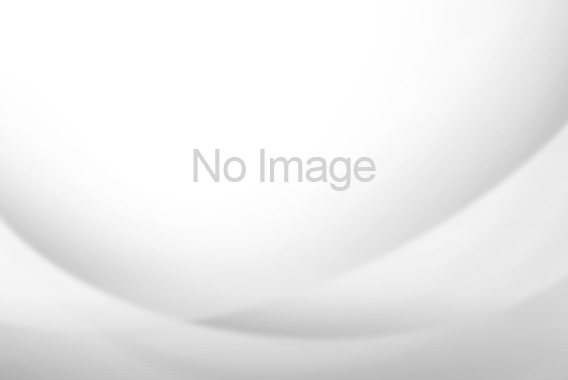
Googleは2024年11月29日、Google社のサイバーセキュリティ対策部門をはじめ、政府機関、アカデミアの研究者・学生など産官学を代表する専門家が一堂に会する「Cybersecurity Research Symposium」を東京都内で開催し、講演やセッション、授賞式などが行われた。
Googleは2024年3月7日、日本にサイバーセキュリティ研究拠点(Cybersecurity Center of Excellence)を設立、アジア太平洋地域のサイバーセキュリティの強化をめざしている。この拠点を通して、政府をはじめとする各関係者と連携を強化、誰もが安全に安心してデジタル上の日常生活を過ごせるための取り組みを推進するという。また、アジア太平洋地域全体のサイバーセキュリティ標準の向上と持続可能な成長への貢献を目的に、日本をはじめとするこの地域の教育機関と連携した研究支援やトレーニングプログラムの提供を行っている(詳しくはGoogle「サイバーセキュリティ研究拠点の取り組み」を参照)。
Googleは、先ほど触れた「サイバーセキュリティ研究拠点の取り組み」に対し、「政策対話」「人材育成」「研究支援」という3本柱を掲げる。「政策対話」では、産官学関係者によるセミナー、パネルディスカッションなどを通じた対話の促進、意識の向上・共有、技術標準化に向けた政府との協力対話を行うものとし、このシンポジウムもまさにその一環といえる。
シンポジウムでは、日本のセキュリティ人材の不足にスポットを当て、サイバーセキュリティ人材の量的な底上げと高度な能動的サイバー防御を行うこと、国家安全保障のマインドと知識を持った人材育成の2つが必要という結論が出された。なお「能動的サイバー防御」とは、「外部からのサイバー攻撃について、被害が発生する前の段階から、その兆候に係る情報その他の情報の収集を通じて探知し、その主体を特定するとともに、その排除のための措置を講ずること」と衆議院の法案で定義されている。
サイバーセキュリティ人材については、3本柱の「人材育成」の一環といえるが、初級から専門家向けまでレベルに応じた人材育成研修を実施、幅広いニーズに対応する「サイバーセキュリティ学習コンテンツ」をGoogleは提供している。この中にはサイバーセキュリティのキャリアへの早道とされる「グーグル・サイバーセキュリティ プロフェッショナル」の認定プログラムも含まれる。シンポジウムで受賞者が発表された「Google JAPAN Cybersecurity Research Award」は、3本柱の「研究支援」の一環だろう。これは日本の大学および研究機関を対象にした研究支援プログラムで、Gooleは各プロジェクトに3万ドルを1年間提供、セキュリティ研究と暗号技術の2分野で助成を行っている。
実は、シンポジウムと同日、首相官邸において「第4回サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」が行われ、サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入に向けた最終提言がとりまとめられた。提言内容は「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言(概要)」が分かりやすい。それによれば、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等かそれ以上に向上させる新たな取り組みの実現のため、必要となる法制度の整備などについて、提言をとりまとめたという。実現すべき具体的な方向性は「官民連携の強化」「通信情報の利用」「アクセス・無害化」の3つで成り立っている。
「官民連携の強化」は、国家をも背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大と技術のめざましい進展から、官のみ・民のみでのサイバーセキュリティ確保は困難と考え、政府が率先して情報提供を行い、官民双方向の情報共有を促進すべき、との点を提示している。次に、「通信情報の利用」は、先進主要国では国家安保の観点からサイバー攻撃対策のため事前に対象を特定せず一定量の通信情報を収集・分析しているが、わが国でも重大なサイバー攻撃への対策のため、一定の条件下での通信情報の利用を検討すべき、ことを示している。最後の「アクセス・無害化」は、近年のサイバー攻撃の特徴を踏まえ、被害防止を目的としたアクセス・無害化を行う権限を、臨機応変かつ即時に対処可能な制度で整備すべき、というポイントを示している。
全体的には、「国民生活や経済活動の基盤」と「国家及び国民の安全」をサイバー攻撃から守るため「能動的なサイバー防御」体制を整備する、というイメージだ。法、人権、プライバシー、機密情報保持など、さまざまな観点から困難な点も多いと思われるものの、それらを乗り越えつつ官民一体での「能動的サイバー防御」が必要となっていきそうだ。
シンポジウムでは、Googleのシェーン・ハントリー(Shane Huntley)氏が、世界のサイバー攻撃はすでに半分がAIを使った攻撃であると指摘、これに対しAIを「有能な防衛者」として学習を重ねて活用していく方針を述べた。Googleは「セーフティセンター」において、Google検索やGmail、Chrome、Googleマップ、YouTube、Googleフォト、Google Pixelなどのサービスや製品に「業界最高水準のセキュリティでユーザーを保護」しているとうたう。私たちの生活に不可欠なのは「重要なインフラストラクチャーの保護」とし、Googleは、社会の重要インフラがより安全になるよう、高度なセキュリティ保護を導入する方針を示している。
Googleは、イノベーションが進むにつれ、責任を持ってAIを開発し導入するためのセキュリティ基準が求められることから、AIシステムを安全に保護するための概念的なフレームワーク「SAIF(Secure AI Framework)」を2023年6月から導入している。SAIFは、AIや機械学習モデルのリスク管理、セキュリティ、プライバシーなど懸念されている課題に対応、AIモデルを安全なものとして実装するのに役立つという。SAIFは、強固なセキュリティ基盤をAIエコシステムまで拡大、検出機能と対応機能を拡張し組織の脅威対策にAIを取り込む、AIにより防御を自動化し既存および新規の脅威に対応する、など6つの基本要素で構成。政府や組織に提供しつつ、新たなリスク、状況の変化、AIの進歩に対応するため、改良と構築を続けていくという。
まさに、「AIの脅威をAIで防ぐ」ということになる。サイバーセキュリティ人材が不足している現在、SAIFのようなAIを活用したセキュリティツールが、セキュリティ人材不足のギャップをある程度埋めていける可能性もある。
悪意ある者はAIをも使いこなし、常に最新の技術で利益を求める。防御するわれわれは悪意ある者以上の知恵と技術をもって、対処しないといけない。この「いたちごっこ」は気を抜くと負けだ。「能動的サイバー防御」は常に新たなる脅威に先回りするもの。たとえAIをAIで防ぐとも、優秀なセキュリティ人材が量的・質的に必要だ。官民連携も、セキュリティ人材あって成立するものだと思う。
セキュリティ人材確保の早道の1つが教育・育成だ。手っ取り早く常識を身につけるには先述Googleの「サイバーセキュリティ学習コンテンツ」初心者向けの「はじめてのサイバーセキュリティ」がおすすめだ。無料受講できるものなので、自主的な学びはもちろんだが、利点は大きいので時間をとって組織的に多人数で受講、勤務時間内での受講を許可する、なども有効だ。中小企業関係者、サイバーセキュリティについてあまり詳しくない人、基本的なセキュリティ対策を学びたい人はもちろん、組織としてセキュリティ対策をしたいがどう対策すればいいか分からない場合にも役に立つとGoogleは言う。最後に選択式10問のテストがあり、得点率50%以上は修了証が発行され、励みにもなりそうだ。
サイバーセキュリティを扱うキャリアへの第一歩として、冒頭で紹介した「グーグル・サイバーセキュリティ プロフェッショナル認定」もかなり有効だ。即戦力として活躍できるスキルを6カ月以内で身につけられる。1名199ドルで1年間無制限に教材にアクセスできる制度もあり、これを活用すれば、働きながら技術を身につけられそうだ。加えてさらなる上級の「プロフェッショナル証明書」8コースを備え、サイバーセキュリティ人材を育成したい企業には「もってこい」な制度と思う、前向きに検討しよう。
生成AIは、毎日続々と新しいニュースが聞かれる。新しい技術には新しい脅威がセットで発生することを頭に入れ、今後の発展を願いつつ、セキュリティ人材を育て、自らも情報を定期的にチェック、共有して、官民一体の「能動的サイバー防御」を行い、明るい未来を築いていこう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」
審査 24-S1007