
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
8月を迎えて夏休みを取得する人も多いだろう。しかし、長期休暇は実はサイバー攻撃にとって絶好の機会だという点を忘れないようにしたい。実際に夏休みなどの長期休暇の期間はサイバー攻撃が増える傾向にあり、インシデントの発見が遅れて大きな被害につながることもある。ここでは、長期休暇を迎えるにあたって、担当者が考えておくべきセキュリティ対策のポイントを「休暇前」と「休暇後」で考えてみたい。
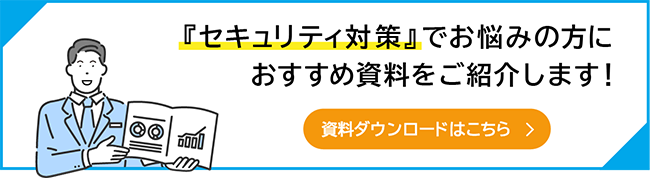
長期休暇に入る前にまず行っておきたいのが、対策手順の再確認だ。長期休暇中の監視体制を確認し、システムアラートなどが発生した際にはどう対処するのかを確認しておこう。例えば、自分自身が不在の時に、誰がどこまで判断するのか、どんな事態になったら緊急連絡を行うのかという基準を明確にすると良いだろう。
次は、インシデントが発生した際の連絡体制の整備だ。セキュリティインシデント対応を委託する外部の専門企業も含めて、緊急時の連絡手段を確立し、実際に連絡が取れるか確認する。担当者の連絡先や電話番号に変更がないかも確認しておこう。
これらに併せて、休暇に入る前の各種のシステム対策を実施する。まずはバックアップだ。重要なデータや機器の設定ファイルに対して、事前に定めたルールに従ってバックアップを実行する。ソフトウエアのアップデートも必ず行おう。脆弱性対策の状況を確認してセキュリティパッチを適用し、機器のファームウエアも最新のバージョンにアップデートする。最も安全な状態で長期休暇を迎えるのが、サイバー攻撃対策の基本だ。
最後に、長期休暇中に使用しない予定のサーバーなどは、電源をOFFにする。物理的な攻撃防御として有効な手段となる。長期休暇中にメンテナンス作業などで社内ネットワークに機器を接続する予定がある場合は、あらかじめ接続ルールの順守を社内に徹底しておくと良いだろう。
長期休暇明けの作業は、担当者やセキュリティ部門の専門性が問われる重要な局面と捉えておこう。慎重な対応が求められる。
まず、電源を落としていた機器を起動後、不正プログラム対策ソフトウエアなどの定義ファイルを更新しよう。これらは電子メールの送受信やWebサイトを開く前に実施するのが重要だ。
また、長期休暇中に公開されたOSや各種ソフトウエアの修正プログラムの有無を確認しよう。修正プログラムが公開されている場合は適用し、関連する脆弱性情報も確認する。そして、更新済みの不正プログラム対策ソフトウエアなどで機器の安全性を確認する。特に長期休暇中に持ち出されていたパソコンなどがあれば、入念にチェックしよう。
最後にログの確認を行う。サーバーなどの機器への不審なアクセスがなかったか、VPNやファイアウォール、監視モニターなどのログやアラートで確認しよう。不審な点が見つかった場合は、該当する端末をネットワークから切り離して、詳細な調査を実施する。
これらの確認作業で異常が認められなければ、通常業務に移行できる。なお、定義ファイルの更新や修正プログラムの適用、持ち出した機器のセキュリティチェックは、社員一人ひとりにとっても必須の作業だ。長期休暇から戻る社員全員に、メールやWeb閲覧の前にこれらの作業を実施するよう周知徹底しよう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです。
執筆=高橋 秀典
【TP】
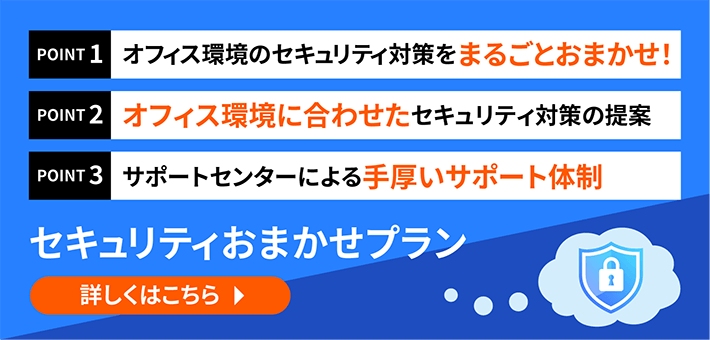
最新セキュリティマネジメント