
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
サイバー攻撃のリスクが社会問題となる中、多くの企業が基本的なセキュリティ対策を実施しているはずだ。しかし、中小企業では人材不足によりセキュリティ専門部署を設置できないケースが多く、サイバー攻撃の検知や対応について適切な措置を講じるのは困難な状況にある。このため、攻撃を受けた際にはリスクが拡大してしまう恐れがある。このような課題を抱える中小企業に対して、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の相談窓口の活用をお勧めしたい。
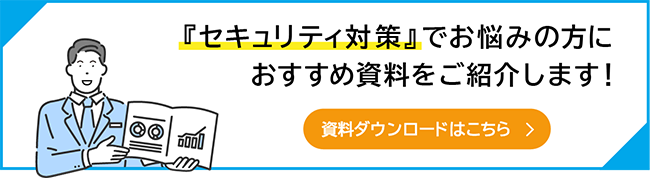
独立行政法人情報処理推進機構(以下、IPA)には、ウイルスや不正アクセスなど情報セキュリティに関する技術的な相談に対してアドバイスを提供する「情報セキュリティ安心相談窓口」があるのをご存じだろうか。特に企業組織向けには「サイバーセキュリティ相談窓口」が設けられている。
受け付けている相談の範囲は広い。各種インシデント発生時の初動対応に関する相談から、標的型サイバー攻撃に関するインシデント相談、その他の情報セキュリティに関する一般的な相談まで対応している。さらに、IPAが注意喚起している脅威情報に関する情報提供も行っている。
IPAは相談された事案についての調査や解析の実施には対応していないものの、発生している事象をヒアリングし、被害の有無を判断した上で、被害が確認された場合には有効な応急処置の案内や専門業者の紹介、適切な相談先や報告先の案内などを行っている。
具体例として、レンタルサーバー上のウェブサイトが不正アクセスの被害に遭い、顧客のクレジットカード情報が窃取された可能性を心配する企業からの相談に対し、レンタルサーバー企業への調査依頼の方法や、カード会社への相談、個人情報保護委員会などの監督官庁、警察などへの連絡方法を提案した事例がサイト上で紹介されている。
さらに今後に向けた対策についても詳細な解説をしており、インシデントへの対応や再発防止策の検討などについて、専門的な立場からの支援を受けられる。セキュリティ対策の専門部署を持たない中小企業にとって、心強い味方となることは間違いないだろう。
実際にIPAの情報セキュリティ安心相談窓口には2025年1月から3月の間に、企業や組織からの123件を含む3215件の相談が寄せられている。相談内容で最も多いのは、突然画面上に偽警告メッセージを表示させて電話連絡を要求する「ウイルス検出の偽警告」で、全体の3割強となる1084件に上っている。
その他にも、不正ログインによってSNSにログインできなくなったという「不正ログイン」の相談や、各種サービスや企業をかたり個人情報やクレジットカード情報を盗み取ろうとする「フィッシング」、偽の恐喝で暗号資産を要求してくる「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」などの相談も寄せられている。
相談方法としては電話が最も多いが、電子メールやチャットボット、SMSなどからの相談も増加傾向にあり、気軽に相談できる体制が整備されている。不安に思うことがあれば、悩みを抱え込むのではなく積極的な活用を検討すべきだ。それがリスクの拡大防止にもつながるはずである。
IPAではこうした相談窓口の運営に加え、「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」といったインシデント対応に関するコンテンツを提供し、各種マニュアルやパンフレットも無料で用意している。
専門企業が提供するサポートサービスと併せて、"転ばぬ先のつえ"としてIPAの機能を把握しておけば、セキュリティリスクの拡大防止につながる。人材が不足している企業だからこそ、こうしたサービスを知り、活用すべきだろう。
執筆=高橋 秀典
【TP】
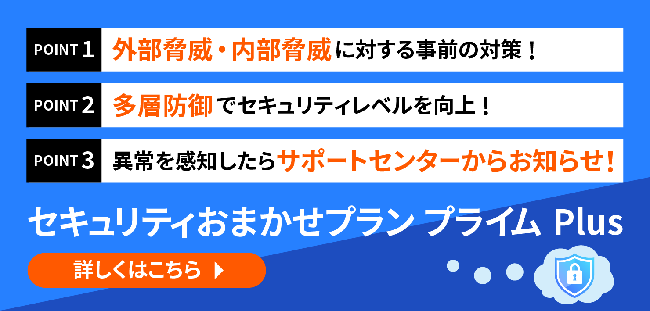
最新セキュリティマネジメント