
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
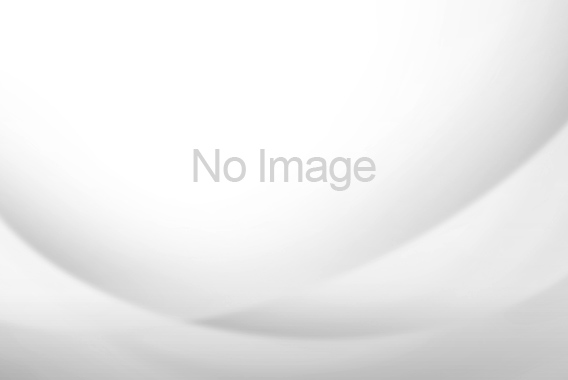
「コネクテッドカー」(つながるクルマ)とは、ICT端末としての機能を備えた自動車のことだ。車両の状態や周囲の道路状況などのデータをセンサーで取得し、ネットワークを介して集積・分析する。総務省の情報通信白書によれば、事故時に自動的に緊急通報を行うシステムや、盗難時に車両の位置を追跡するシステムが実用化されつつある。
私たちが日常持つスマホのように、車が常にインターネットにつながり、ネット上のクラウドサーバーとやり取りして便利な機能を提供するには、5Gによるモバイルネットワークの高速・大容量化や、IoT、ビッグデータ、AIなどの進展が欠かせない。未来に向けた総務省のコネクテッドカー構想については、平成29年の「Connected Car社会の実現に向けて」が詳しい。
ICTなどの最新技術により、自動運転や安全制御装置、盗難防止、事故やトラブル時の対応、快適な車内環境のコントロールなど、よりラクに安全に利用できるのはうれしいことだ。ただし、サイバー攻撃が高度化し被害が急増する世の中では、便利さに潜むリスクを気にせずにはいられないのも真実だ。
2015年、米国でジープ・チェロキーをWi-Fi経由でハッキングし、遠隔地から走行中の車両のエンジンを止める、ブレーキを操作する、ワイパーを作動させる、情報ディスプレーやオーディオシステムを乗っ取る操作実験が成功し、140万台のリコールに発展した。この事件をきっかけに、自動車におけるセキュリティ対策の必要性が問われるようになった。
コネクテッドカーの実現で、車のセキュリティ問題はネットワーク全体に広がった。コネクテッドカーのサーバーをハッキングすれば、そこにつながるすべての車を人質に取れる。車1台からネットワークに侵入され、サーバーやシステムにアクセスされる可能性もある。
もし今どきのハッカーがコネクテッドカー・システムへの攻撃を計画したらと想像してみた。ハンドル制御やアクセル制御を乗っ取って自動車を暴走させれば、事故を引き起こせる。安全装置や救助システムを停止させて、メーカーの信用を落とすこともできる。流通システムの車をかく乱し、流通を止めることもできる。集められた走行データを人質に、身代金要求もできるだろう。ハッカーにとって金の鉱脈となる可能性は少なくない。
一般的なコンピューター端末なら、セキュリティ装置やセキュリティソフトの導入がある程度浸透しているが、車や家にあるAI搭載のエアコンや電子レンジに使用者自らセキュリティ対策を行うのは考えにくい。
コネクテッドカーの技術は進歩しているものの、セキュリティ対策は追い付いていないといわれる。そんな現状に対し、日本の自動車業界が2021年2月11日、トヨタ自動車をはじめとする車メーカー14社が車部品メーカー7社と共同で、「つながるクルマ」のサイバー攻撃対策のための新団体、一般社団法人「Japan Automotive ISAC(J-Auto-ISAC)」を設立。8月30日には、会員企業が92社になった。
活動方針には脅威・脆弱性情報の収集および解析、関連情報の共有、管理施策やシステム施策の紹介、方針やガイドラインの策定、SIRTの構築および強化、外部連携、人材の育成などが挙げられている。
こうしたコネクテッドカーの国内での現状は、トヨタの「T-Connect」、日産の「NissanConnect」、ホンダの「Honda CONNECT」、マツダの「MAZDA CONNECT」、スバルの「SUBARU STARKINK」など各サイトから知ることができる。
T-Connectに記載されている例を紹介すると、もしものときに車自身が緊急通報したり救急車やドクターヘリを呼んでくれたりする。離れた車の状況をスマホに知らせ、盗難に気が付いたときはスマホからエンジンやステアリングをロックする。窓の閉め忘れをスマホに通知し、スマホからドアロックする。警告灯点灯時などに操作を案内したり、集中力の乱れを察知して注意喚起を行ったりする。そのほかスマホのように話しかけるだけで知りたい情報を教えてくれたり、リアルタイムの情報と過去の統計を駆使したルート案内などを提供したりもできる。
国内外のコネクテッドカーの状況は、経済産業省の2020年3月の資料「自動運転が活用されうるコネクテッド技術・商用モビリティサービスに関する国内外動向調査」が詳しい。ここではコネクテッドカーの新車販売台数は、2035年には1億台を超えると予想している。
統計によると、乗用車におけるコネクテッドカーのサービス内容は各国大きな差異は見られないという。遠隔操作などの運転支援・車両制御、ナビやオーディオなどのマルチメディア、車両の異常の感知やメンテナンス通知を行う車両管理、事故を通報したり盗難を知らせたりする安全管理、そのほか燃費・バッテリー管理、保険会社との連携などだ。車載イーサネットで車内ネットワークの通信量増大に対応しようという動きも盛んだ。
ただし、セキュリティ対策の遅れも懸念される。世界において自動車業界の約半数の企業が、セキュリティ対策のための人材が不足しているという。国内でも優秀な人材を育成する仕組みや動機付けが急務だ。
先日、トヨタのレンタカー無人貸し出しサービスを利用したユーザーのツイートが話題となった。山奥で車とスマートフォンのBluetooth接続が失われ、車のドアが開閉できなくなったという。スマホアプリのみでレンタカーの予約やドアの開閉、精算ができるサービスだったが、その便利さゆえに生じたトラブルといえる。車が正常でもスマホがダメになる可能性はある。容易に助けが来られない場所でトラブルに遭うかもしれない。身近な問題として捉えざるを得ない。
スマホ決済の黎明(れいめい)期にもトラブルが頻発し、サービスの熟成を待ったほうがよいともいわれた。ただ、最近のITサービスのトラブルは、サイバー攻撃起因のものも少なくない。さらに、なりすましなどのトラブルが解決済みなわけではない。
コネクテッドカーに関しては、常にリスクの可能性を想定しなくてはならない。サービスを享受する側、提供する側どちらかだけが気を付ければよいというものでもない。“通信”にはセキュリティ対策が必須だ。実際に便利さを手に入れようと思えば、自ら情報収集するくらいの意識は常に持っておきたい。
執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
【TP】
IT時事ネタキーワード「これが気になる!」