
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
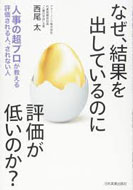 なぜ、結果を出しているのに評価が低いのか?
なぜ、結果を出しているのに評価が低いのか?
西尾 太 著
日本実業出版社
人事評価の本です。高い評価をされる人になる方法が分かります。ビジネスパーソンなら、評価には無関心ではいられないはずです。ところが、実際には、どう評価されているのかを意外に知らないものです。もちろん、評価の仕組みや評価基準は知らされているかもしれません。でも、それはあくまでも建前で、本当は違うということも少なくありません。
だから、会社に忠誠を尽くし、成果も上げているのに評価されないという人が出てくるのです。そんな「もったいない人」に自分がならないために、人事のプロが評価のリアルを教えます。
ビジネスパーソンは、結局人事評価です。給与も処遇も、配転、リストラ、転職まで、キャリアのすべてが評価で決まります。だからこそ、誰もが血眼になって評価を競い合っています。
ところが、大した成果を上げていないのに評価され、出世する人がいます。それを見て「不公平だ」「理不尽だ」とぼやいても始まりません。そんな暇があるなら、評価される方法を研究するべきです。評価されるには、ツボを押さえて振る舞うことです。しかも、そのツボ、著者いわく「あらゆる組織でほぼ同じ」ということですから、知らないと怖いのです。
また、著者は「評価を決めるのは、本人の性格」だと言います。そして、それがどう評価に影響するのかを教えます。チェックシートも用意されていますので、自己診断ができます。
「結果を出しているのに、頑張っているのに、評価されない」と感じている人、努力ややる気を無駄にしたくないと考える人など、評価に悩むすべてのビジネスパーソンにお勧めしたい本です。
評価を巡る競争は激しさを極めます。その理由は、1つには、各人の実力が伯仲しているからです。競争相手は、同じ基準をクリアして入社した同レベルの人間たちです。
加えて、すでに述べた通り、評価の基準がいまひとつ曖昧です。もちろん、普通の会社なら人事評価制度などがつくられ、公開されています。問題は、その運用が曖昧だということです。
結局「評価は上司の胸三寸」というのが現実です。同レベルの人間が、上司の気持ちや考えという曖昧な尺度の下で競い合うから、競争の厳しさに拍車がかかるのです。さらに残酷なことは、ある時まで自分の評価が不明確だということです。当人は、評価を得ているつもりでも、実際はそうでもないということがよくあります。不遇をかこって初めて知ることもあります。
評価する側がそんな調子ですから、評価される側も備えるしかありません。本書を読めば、その対処法が分かります。決め手は、著者いわく「性格」ということです。そして、評価のためには「評価される性格」になるしかありません。もちろん、性格は個性ですから、良いも悪いもありません。でも、評価されたいなら、評価される性格に変わるしかないのです。
しかも、著者は「評価基準はどこでも共通」と言います。確かに、できる人は、どこでも「できる人」とされるものです。反対も、またしかりです。
だから、評価が気に入らなくて、異動や転職をするのは無意味です。もし、自分の性格が評価されにくいもので、かたくなに性格を変えたくないと思うなら、低い評価に甘んじるしかありません。ただ、性格を変えるとはいっても「別人格に変われ」ということではありません。あいさつするとか、悪口を言わないとか、時間を守るとか、社会人なら当たり前のことばかりです。
普通の社会人なら、ほぼできていることばかりだと思います。だから、念のためチェックして、できていないことを修正すれば十分です。それだけで評価が変わるなら、やらない手はないと思います。
執筆=藤井 孝一(ビジネス選書WEB)
ビジネス書評家、読者数5万人を超える日本最大の書評メールマガジン『ビジネス選書&サマリー』の発行人。年間1000冊以上の書籍に目を通し、300冊以上の書籍を読破する。有名メディアの書評を引き受けるほか、雑誌のビジネス書特集でも、専門家としてコメント。著書は『読書は「アウトプット」が99%』(知的生きかた文庫)のほか、『週末起業』など、累計50冊超、うちいくつかは中国、台湾、韓国でも発刊されている。
【T】
読書でビジネス力をアップする