
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
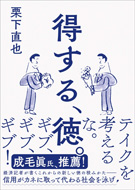 得する、徳。
得する、徳。
栗下直也 著
CCCメディアハウス
働き方や生き方を考える本です。人に与えたり、人助けをしたりすることで、やがて成功者になれると説きます。もちろん、単なるお人よしでなく、成功者になるための正しい徳の積み方が分かります。
昔から「ビジネスには信用が大事」といわれてきました。昨今は、「信用さえあれば生きていける」とまでいわれます。そうはいっても、やはりきれい事と思われるかもしれません。しかし、歴史をひもとけば、名経営者ほど徳を積んで成功しています。どうすれば正しく徳を積むことができるのか、多くの財界人を取材してきた経済記者が教えてくれます。
「信用がお金に変わる」といわれても、戸惑うのが普通です。そこで、例えば「信用」を「徳」に置き換えてみます。すると歴史に先人のお手本があふれていることに気付かされます。
本書は「お金よりも信用を積め」「テイクを考えずギブせよ」と主張します。まるで怪しい宗教団体のようでうさん臭いと思うかもしれませんが、読めば「徳がやがて得になる」ことが分かるはずです。
まず「徳」が重視されつつある現状と、徳の積み方を説明します。次いで偉人たちの足跡をたどりながら、彼らの徳を現代社会に生かす方法を解説してくれます。
さらに、徳とは無縁でいられなくなった会社を考えます。「金にならないことはやりたくない」とか「そんな余裕はない」という人も、徳を積むべき理由が分かるはずです。
会社を経営する経営者や幹部社員、そういう人たちを顧客に持つ仕事をしている人は必読です。さらに、信用がお金に勝るといわれる時代をどう生きればいいか分からないい人にもオススメです。
「カネより信用」「信用があれば生きていける」といわれる時代です。これまでも銀行で融資を受ける際や、取引を選定する際にも、信用が大切だといわれてきました。
近年は、それがさらに進んでいます。例えば中国の「芝麻(ゴマ)信用」(Sesame Credit)(※)のように信用をポイント化する動きが日本でも出てきています。それ以前に、ネットの世界では口コミが経済を動かしてきました。
※中国モバイル決済アプリでトップシェアを誇る「Alipay(アリペイ)」に搭載されている機能
特に、日本では昔から「徳を積む」という行為を推奨してきました。「情けは人のためならず」「損して得取れ」などという言葉も定着しています。しかし、現実には、日本人は徳の意識は低いようです。
寛容さを調べた調査では、日本の公共心は128カ国中107位と低水準です。確かに日本では芸能人が寄付したというニュースもあまり聞きません。できていないから、声高に叫ぶのかもしれません。
本書にも出てきますが『GIVE & TAKE』(邦題「GIVE & TAKE 『与える人』こそ成功する時代」)という本では人間を3種に分類します。とにかく人に与えるギバー、自分の利益を最優先するテイカー、ギブとテイクのバランスを保つマッチャーです。
そして、最後に勝つのはギバーだということを、さまざまな調査から明かしていきます。例えば、他者を援助することに関心のある営業担当者の売り上げは、関心を示さない人より50%も高いそうです。
これなど、起業の手伝いをしていても強く感じることです。時々、自分のことより他の人のサポートに熱心な人がいます。そういう人は周囲から愛され、助けられ、やがて成功していくものです。
反対に、人の顔を見ればお願いばかりする人がいます。そういう人ほど、人を助ける気持ちは皆無です。やがてトラブルに巻き込まれたり、周囲から煙たがられたりして消えていくものです。
もちろん、無理にいい人をめざす必要はありません。そもそも続きません。まずは、自分にできることを、無理のない範囲で手伝うことです。やがて、与えることの喜びが分かるはずです。
喜びが分かれば、あとは無理なく、自然に、困った人に与えることができるようになるはずです。巡り巡って、自分の得につながることが起きるようになるのだと思います。
執筆=藤井 孝一(ビジネス選書WEB)
ビジネス書評家、読者数5万人を超える日本最大の書評メールマガジン『ビジネス選書&サマリー』の発行人。年間1000冊以上の書籍に目を通し、300冊以上の書籍を読破する。有名メディアの書評を引き受けるほか、雑誌のビジネス書特集でも、専門家としてコメント。著書は『読書は「アウトプット」が99%』(知的生きかた文庫)のほか、『週末起業』など、累計50冊超、うちいくつかは中国、台湾、韓国でも発刊されている。
【T】
読書でビジネス力をアップする