
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
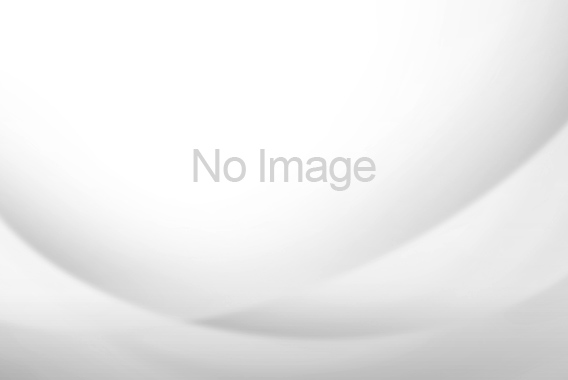 血液には、酸素や栄養素を全身に運び、老廃物や疲労物質を回収・排出する役割があります。そのため、冷えによって血流が滞ると、寒さや肩こりといった自覚症状の出現をはじめとして、栄養不足で免疫力が低下したり、なかなか疲労回復しないといった体の不調を招いたりします。また、そうした状態が続くと便秘や肌荒れ、肥満など体質の悪化を引き起こしやすくなります。
血液には、酸素や栄養素を全身に運び、老廃物や疲労物質を回収・排出する役割があります。そのため、冷えによって血流が滞ると、寒さや肩こりといった自覚症状の出現をはじめとして、栄養不足で免疫力が低下したり、なかなか疲労回復しないといった体の不調を招いたりします。また、そうした状態が続くと便秘や肌荒れ、肥満など体質の悪化を引き起こしやすくなります。
キリン食生活文化研究所が行った「体の冷え」についての調査*1によると、冬に体の冷えを「いつも感じている」「感じることが多い」人は、30~40代女性で70%以上、30~40代男性で約50%弱を占めています。
*1 「キリン食生活文化研究所レポートvol.55」……あなたのくらしのアンケート「体の冷え」/20~69歳の男女/1万8202人が対象/2015年12月全国Web調査
この調査において、冷え対策として何をしているか、と体の冷えを感じる人に聞いたランキングが公表されているのでトップ5まで紹介します。
<冷え対策の内容>(冷えを感じる人 1万6651人からの回答)
・第1位:体を温める飲食物を取る(45.6%)
・第2位:機能性下着を着用する(42.0%)
・第3位:手首、足首、首を冷やさない(35.0%)
・第4位:マッサージをする(30.0%)
・第5位:朝ごはんをしっかり食べる(29.4%)
トップ5を眺めてみると、第2位の「機能性下着を着用する」以外は、すぐに始められることばかり。冷えは代謝の低下や倦怠(けんたい)感、風邪など、さまざまな体の不調を招きます。血行を良くして代謝を高める冷え対策を、ぜひ日常生活に取り入れましょう。
冬の食生活では、血液をサラサラにする成分を摂取して血行を促進し、熱を生み出す筋肉の主な原料であるたんぱく質を欠かさないようにすることが大切です。温かい食事で内臓から体を温めましょう。
●たんぱく質を不足させない
筋肉には、血液を送り出したり、体温調節をしたり、エネルギーを消費する働きがあります。そのため、筋肉の老化は冷えや不調につながります。日々の食生活で、筋肉の維持に必要なたんぱく質を積極的に摂取しましょう。肉や魚、卵、豆類(豆製品)、乳製品などに豊富に含まれています。
●血液をサラサラにする食材を選ぼう
玉ねぎには、代謝を促して血液の凝固を抑制する働きのある「硫化アリル」という成分が豊富に含まれています。また、硫化アリルにはビタミンB1の吸収率を高める効果があり、ビタミンB1を多く含む豚肉との相性がピッタリ。合わせて食べると疲労回復や代謝アップ効果が期待できる食材です。
納豆に含まれるたんぱく質分解酵素「ナットウキナーゼ」には、血栓を溶かして血液を流れやすくする働きがあります。納豆そのものは植物性たんぱく質を含む豆類であり、長期保存ができるため、遠征の多いアスリートにも人気の食材です。
●食事の最初は、温かいスープがオススメ!
食事はじめに、体を内側から温めることができるスープを取り入れましょう。胃腸を温めることで満足感も高まり、食べ過ぎ防止にも役立ちます。
野菜とささみのコンソメスープや、大豆入りの野菜たっぷりミネストローネ、アサリたっぷりのクラムチャウダー、白身魚の鍋料理など、野菜とたんぱく質が豊富な食材を組み合わせたホカホカの一品なら、比較的手軽に作れます。
肌の表面には毛細血管が張り巡らされています。そのため、優しく肌をさするだけでも血色が良くなり、温かくなるのを感じることができます。冷えを感じたときや集中力が途切れたときには、手足のマッサージやストレッチがお勧めです。ここでは、オフィスで気兼ねなくできる手のマッサージを紹介します。
(1)ハンドクリームを手になじませる
デスクワークの方は、ベタつかないタイプを選びましょう。
(2)両手を組み、ゴリゴリともみ合う
右手で左手の指をつかみ、指の付け根から指先に向けて、指圧しながら引っ張り上げる。左手・右手の指を、前後左右からつまみ上げます。
(3)手のひらをゴリゴリともみ込む
手のひらを柔らかくするイメージで、親指を使ってもみます。
(4)右手で左手を前後にストレッチする
左右両方行います。
血流を促すハンドマッサージやツボ押し、足裏マッサージ法をより詳しく知りたい方は、資生堂のプレスリリース「オフィスでできる簡単ケア!冬の大敵『乾燥』『冷え』『むくみ』を防いで快適に過ごそう」を参考にしましょう。
血液の巡りは、心臓や筋肉のポンプ作用だけでなく、全身を大きく動かすことによっても促されます。同時に、筋肉に刺激を与えて鍛えることは、老化予防にもつながります。デスクワークの方は特に歩数を意識すること。駅や社内の移動にエレベーターではなく階段を使うだけでも、運動量は増えていきます。積極的に“大きく全身を動かす”運動を取り入れていきましょう。
過ごし方の工夫で、冬の不調は予防・改善が可能です。温かい食事や運動習慣から、冷えに負けない体づくりに挑戦してみてください。
執筆=Nao Kiyota(Self Training Café)
美容・健康ライター。ダイエットアドバイザー、リンパケアセラピスト、心理カウンセラーの資格を生かし、健康で美しくなるためのセルフトレーニング法を発信している。最近カメラを購入。写真で「もっとわかりやすく」伝えられるよう、日々修行に励んでいる。抹茶ラテ(豆乳・シロップ抜き)と足つぼマッサージが大好き。
【T】
疲れ解消★カンタン!アンチエイジング