
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
気温が下がり空気が乾燥する冬の時期はウイルスの感染力が強くなるため、これまで以上に感染症対策に注力しましょう。マスクの着用や手洗い、うがい、消毒などの継続に加え、感染症に負けない免疫機能の維持・向上が重要です。
今回は、健康を保つ生活習慣の1つである食事に焦点を当て、ウィズコロナ時代に注目されている「発酵性食物繊維」の積極的な摂取と、そのためのレシピを専門家に伺いました。
「発酵性食物繊維とは、腸内で発酵しやすい食物繊維のことで、主に玄米や小麦ブラン、大麦やオーツ麦などの穀物に含まれる食物繊維をさします。1日プラス2.0g以上の発酵性食物繊維を目安に食事の1品として取り入れることで、腸内環境の改善が期待できます」と語るのは、日本食物繊維学会理事長の青江誠一郎先生です。
腸内を弱酸性に保ち、ビフィズス菌などの有用菌(善玉菌)がすみやすい環境を整えると知られている“酪酸”は、腸内にすむ酪酸菌が食物繊維を発酵・分解することで産生されます。つまり、発酵しやすい食物繊維を摂取することで酪酸菌の働きが進み、腸内環境の改善につながるということ。腸内環境の健康は、炎症の抑制、アレルギー抑制、がん化細胞の増殖抑制など、全身の健康にも影響することが分かってきているとのこと。
青江先生によると「近年の研究では穀物由来の食物繊維と疾病の関係が続々と明らかにされていて、世界的にも注目されている」といいます。
「今年6月、新型コロナウイルス感染症の患者さんの腸管には酪酸を産生する有用菌が極めて少ない、という臨床研究が香港の大学において発表されました」と教えてくれたのは、京都府立医科大学准教授の内藤裕二先生。内藤先生によると「酪酸菌の働きはT細胞、マクロファージ、樹状細胞、B細胞など免疫細胞にも影響するため、酪酸菌を含む有用菌を腸内に増やし、定着させることが免疫機能アップの鍵になる」とのこと。そのためにも、発酵性食物繊維を積極的に摂取することが第一だといいます。
発酵性食物繊維を毎日プラス2g以上摂取するためのレシピを、フードプランナーで管理栄養士の岸村康代先生に考案いただいたので、ここで紹介しましょう。こうした食事を参考に、発酵性食物繊維の摂取量を増やすように工夫してください。
【枝豆とブランの白和え風:1人前】
発酵性食物繊維量:2.0g
調理時間:3分

<材料>
冷凍枝豆(さやから外したもの)……35g
ツナ水煮缶(水気を切ったもの)……1/4〜1/3缶
小麦ブランシリアル……25g
絹ごし豆腐……70g
白すりごま……大さじ2分の1
めんつゆ……大さじ2分の1
<作り方>
(1)冷凍の枝豆をぬるま湯で解凍しておく
(2)シリアルと豆腐を混ぜ合わせ、すりごま、めんつゆを混ぜ合わせる
(3)(2)に(1)とツナを混ぜる
※時間がたつとシリアルがふやけてきます。サクッとした食感を残すなら混ぜたらすぐに食べましょう。
【ゴボウとキノコのペペロンチーノ風:1人前】
発酵性食物繊維量:2.1g
調理時間:10分
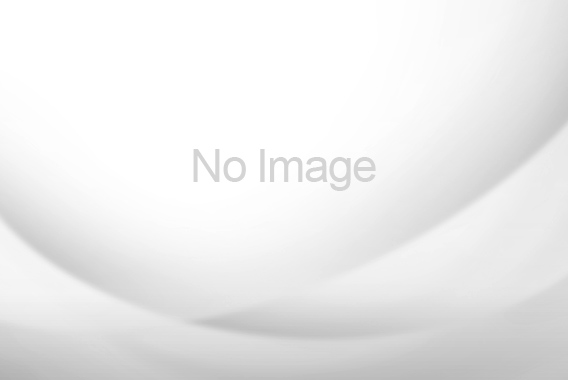
<材料>
ゴボウ……65g
刻み昆布……7g
まいたけ……50g
エリンギ……50g
塩……少々
しょうゆ……小さじ1
黒こしょう……たっぷり
【A】調味料
おろしにんにく……1カケ(チューブでも可)
鷹の爪(種を取って輪切りにしたもの)……1/2本
オリーブ油……大さじ1
<作り方>
<1>刻み昆布を水かぬるま湯で戻しておく
<2>ゴボウはよく洗い、半分に切ってから斜め切りにする。まいたけは小さめのひと口大にほぐし、エリンギは縦半分にして薄切りにする
<3>フライパンに【A】調味料を入れて弱火~中火で加熱し、香りが出たらゴボウ、まいたけ、エリンギを炒める。焦げそうになったら水を大さじ1(分量外)を加えながら弱めの中火で炒める
<4>火が通ってきたら<1>で戻した刻み昆布と塩、しょうゆを加えて炒め合わせる
<5>黒こしょうを振って、できあがり
【メカブと納豆のもち麦キムチごはん:1人前】
発酵性食物繊維量:2.7g
調理時間:2分
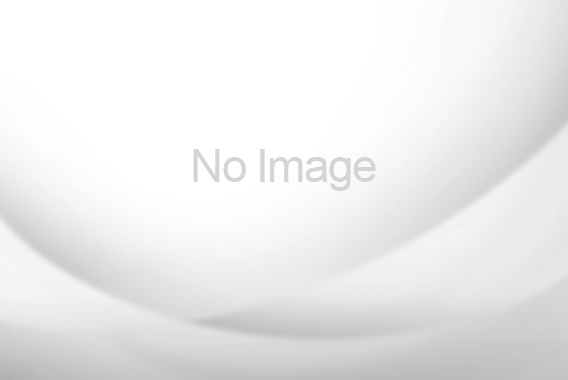
<材料>
めかぶ……1パック(45g)
大麦ごはん……150g
納豆 ……1パック
キムチ……50g程度
海苔……0.5g程度
<作り方>
[1]納豆にタレとからしを入れ、混ぜ合わせる
[2]器に大麦ごはん、めかぶ、キムチ、[1]をのせ、のりをかける
※最もカンタンでお手軽に摂取量を上げることができるのでオススメです。
【ブランキウイヨーグルト:1人前】
発酵性食物繊維量:2.5g
調理時間:1~2分
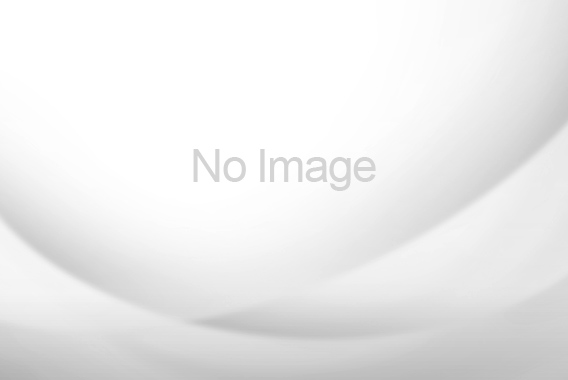
<材料>
小麦ブランシリアル……40g
ヨーグルト……150g
キウイフルーツ……1/2個(50g)
はちみつ……小さじ1
エゴマ油……小さじ1
<作り方>
【1】オールブランとヨーグルトを混ぜ合わせる
【2】キウイフルーツの皮をむき、角切りにする
【3】器に【1】を盛り付け、はちみつをかけて【2】をのせ、エゴマ油をかける
発酵性食物繊維を積極的に摂取し腸内環境を整えること、こうした腸活で免疫機能を高めてこの冬を乗り切りましょう。体づくりも忘れずに、来年も元気で健康にお過ごしください。
【取材協力】 青江誠一郎(あおえ せいいちろう)先生
青江誠一郎(あおえ せいいちろう)先生
日本食物繊維学会 理事長・編集委員 / 大妻女子大学家政学部食物学科教授
大麦の食物繊維とメタボリックシンドローム予防に関する研究で同学会賞を受賞。著書多数、食物繊維研究の国内第一人者。
 内藤裕二(ないとう ゆうじ)先生
内藤裕二(ないとう ゆうじ)先生
京都府立医科大学 消化器内科学教室 准教授 / 同附属病院 内視鏡・超音波診療部 部長
消化器病学の専門家として最先端の研究を行う傍ら、臨床の場で 30 年以上にわたり 5万人以上の診察経験を積む。長寿腸内菌として知られるようになった「酪酸菌」研究の第一人者。
【レシピ考案】 岸村康代(きしむら やすよ)先生
岸村康代(きしむら やすよ)先生
フードプランナー 管理栄養士 / 野菜ソムリエ上級プロ
一般社団法人大人のダイエット研究所 代表理事
執筆=Nao Kiyota(Self Training Café)
美容・健康ライター。ダイエットアドバイザー、リンパケアセラピスト、心理カウンセラーの資格を生かし、健康で美しくなるためのセルフトレーニング法を発信している。最近カメラを購入。写真で「もっとわかりやすく」伝えられるよう、日々修行に励んでいる。抹茶ラテ(豆乳・シロップ抜き)と足つぼマッサージが大好き。
【T】
疲れ解消★カンタン!アンチエイジング