
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
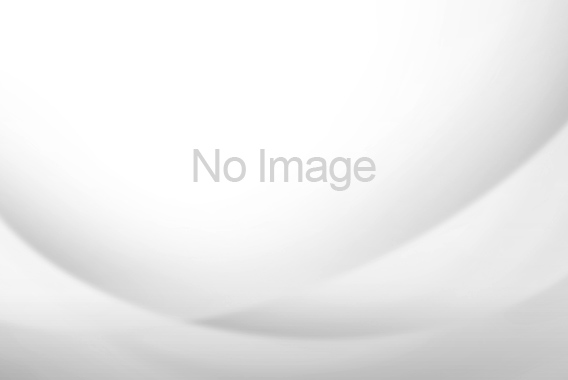 春の陽気が待ち遠しい今日このごろですが、まだまだ寒い日が続いています。2017年の1月末から2月頭に猛威を振るった「インフルエンザ」ですが、まだまだ安心はできません。過去の統計からも3月までは流行シーズンです。インフルエンザは感染症ですから、1人の力では防ぐことが難しく、また、高齢者や免疫力の低下している状態でかかってしまうと重症化する恐れがあります。長期間仕事を休むわけにはいかないという人こそ、職場の方や家族と正しい知識を共有し、周囲と一緒にインフルエンザ対策に努めましょう。
春の陽気が待ち遠しい今日このごろですが、まだまだ寒い日が続いています。2017年の1月末から2月頭に猛威を振るった「インフルエンザ」ですが、まだまだ安心はできません。過去の統計からも3月までは流行シーズンです。インフルエンザは感染症ですから、1人の力では防ぐことが難しく、また、高齢者や免疫力の低下している状態でかかってしまうと重症化する恐れがあります。長期間仕事を休むわけにはいかないという人こそ、職場の方や家族と正しい知識を共有し、周囲と一緒にインフルエンザ対策に努めましょう。
もうすでに感染が発生したという職場や家庭も、今一度「予防」を見直してください。
国立感染症研究所感染症疫学センターによると、インフルエンザは毎年世界各地で流行しているウイルス性の気道感染症で、北半球では1月から2月ごろ、南半球では7月から8月ごろに流行のピークになるそうです。日本におけるインフルエンザ流行は、流行の程度とピーク時期はその年によって異なるものの、およそ1月から3月ごろに患者数が増加し、4月から5月にかけて減少していくという類型がみられます。
1月から3月ごろに流行する理由は、病原菌のインフルエンザウイルスが低温で乾燥した環境を好むことにあります。2月後半から本格的な寒さが続くこの時期には、一歩外に出れば冷たい風が強く吹き荒れている、ということもしばしばで、ウイルスが飛散しやすく、感染しやすい条件がそろっています。
感染を防ぐには、周囲の理解と努力が必要です。個人の対策として流行前のワクチン接種も大切ですが、こまめなうがい・手洗いに加えて、次のような予防対策を、職場や家庭で取り入れましょう。
●職場・家庭では「せきエチケット」を徹底しよう
せき、くしゃみかな?と思ったら、他の人にうつさないためにマスクをすることが鉄則です。せき、くしゃみによるウイルスの飛散や感染を防ぐために、説明書に従って、隙間がないようマスクを正しく使ってください。
マスクがない場合に、どうしてもせき、くしゃみがしたくなったら、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れましょう。手のひらで遮ったときはすぐに手洗いしてください。
また、せき、くしゃみをする人がいたら、積極的にマスクの着用を呼びかけましょう。厚生労働省は、「咳エチケット」をキーワードにした啓発活動を行っていますので、詳しく知りたい方は「平成28年度 今冬のインフルエンザ総合対策」をご覧ください。
●室内の保温・保湿に協力しよう
ウイルスを寄せつけないために重要なのは、ウイルスにとって快適な空間に身を置かないことです。乾燥した環境では、ウイルスが活発に活動するだけでなく、喉や鼻の粘膜が乾燥して免疫力が低下します。職場や家庭の室内の湿度は50~60%を目安に、加湿器などで調節しましょう。
多くの人が出入りする環境では、適度な換気と加湿が大切です。扉やドアの開け放しは厳禁と心得ましょう。高齢者に座席を譲るように、普段から公共マナーの1つとして心掛けましょう。
●喉・鼻の働きをサポートする食事を取ろう
生命活動の維持に欠かせない酵素の働きが活性化するのは36.5~37度といわれており、それよりも体温が低下すると、内臓機能や疲労回復の働きが減退し、免疫機能が弱まってしまいます。温かい食事などを心掛け、体を温めながら栄養を摂取するようにしましょう。
喉・鼻の粘膜の働きを活性化し、免疫力を高めるためには、三大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質)に加えて、粘膜の働きを助けるビタミンA、代謝を高めるビタミンB群、抗酸化作用(老化抑制)や免疫力を高める役割を担うビタミンC、ビタミンEをバランスよく取ることが大切です。
ビタミンAが豊富な食材……牛乳・チーズなどの乳製品、卵など
ビタミンBが豊富な食材……豚肉や卵など
ビタミンCが豊富な食材……じゃがいも、みかんなどのかんきつ類など
ビタミンEが豊富な食材……かぼちゃ、大豆など
●抵抗力を高めるために早く帰宅しよう
ウイルスに対する抵抗力は、睡眠中に強化されます。また、睡眠中には疲労回復や細胞の再生が盛んに行われます。毎日十分な睡眠時間を確保することで、疲労をため込まず、免疫力の高い状態が維持されるので、この時期は極力定時で帰宅できるよう、職場で協力し合うように工夫してください。
うがい、手洗いの徹底、せきやくしゃみは覆う、マスクを装着する、生活習慣を整える……。どれも健康維持の基本ですが、1人ひとりが意識して徹底することで、初めて感染や拡大の予防につながります。職場や家庭などで今一度過ごし方を話し合い、お互いに感染を防ぎ合いましょう。もうしばらく続く寒さの日々を健康体で乗り切る工夫を、ぜひ実践してください。
手の洗い方やマスクでウイルス侵入を防ぐ方法など、感染症予防の方法についてより詳しく知りたい方には、『政府インターネットテレビ』(動画20分)の視聴が分かりやすくお勧めです。
執筆=Nao Kiyota(Self Training Café)
美容・健康ライター。ダイエットアドバイザー、リンパケアセラピスト、心理カウンセラーの資格を生かし、健康で美しくなるためのセルフトレーニング法を発信している。最近カメラを購入。写真で「もっとわかりやすく」伝えられるよう、日々修行に励んでいる。抹茶ラテ(豆乳・シロップ抜き)と足つぼマッサージが大好き。
【T】
疲れ解消★カンタン!アンチエイジング