
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
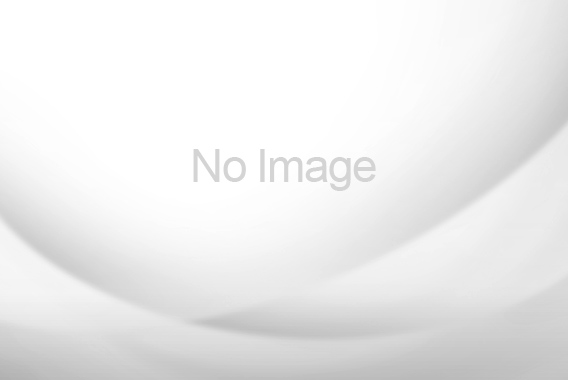 「頭」も、こるってご存じですか? 実は、肩や腰だけでなく「頭(頭皮)」もこりやすい部位なのです。やる気や集中力が低下して身体が重く感じてきたら、頭皮の体液循環が滞っているせいかもしれません。
「頭」も、こるってご存じですか? 実は、肩や腰だけでなく「頭(頭皮)」もこりやすい部位なのです。やる気や集中力が低下して身体が重く感じてきたら、頭皮の体液循環が滞っているせいかもしれません。
放っておくと、抜け毛や肌トラブルを招きやすくなってしまいます。毎日の入浴習慣に「ヘッドマッサージ」を取り入れて、疲労や老化の原因を汚れと一緒に洗い流してしまいましょう。
頭にもこりがあるというのは意外に思われるのではないでしょうか。血液やリンパ液の流れが滞ることで肩や腰のこりは発生しますが、頭皮も同じように体液循環の滞りによってこり固まってしまいます。
頭がこって酸素や栄養が行き渡りにくくなると、頭皮や顔の皮膚に悪影響を及ぼします。白髪や抜け毛が多くなったり、乾燥肌・吹き出物などの肌トラブルやシワ、たるみが発生しやすくなったりと、老化を早めてしまうのです。疲労物質が排出されにくくなるため、疲労が抜けにくい体質になるなど良くないことばかり……! 疲労回復やアンチエイジングには、頭皮を柔らかくほぐして体液循環をよくするケアが大切です。
※こりによる不調やリンパケアの健康効果について詳しく知りたい方には一般社団法人 日本リンパ協会編著の『リンパケア検定2級 公式テキスト』(評言社)がおすすめです
疲労回復を促進して老化を防ぐためには、こり固まった頭皮を柔らかくほぐすことが重要です。こりをほぐすヘッドマッサージで、頭皮の老廃物の排出や栄養素の運搬がスムーズになります。
今回は、お風呂で髪を洗いながら手軽にできるヘッドマッサージ法をご紹介します。入浴時は血行がよくなるため、こりをほぐす絶好のチャンス。今日から早速始めてみましょう。
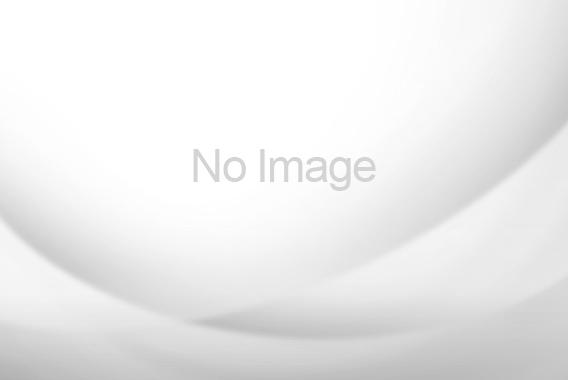 (1) 頭皮を押す
(1) 頭皮を押す
両手の指先(爪を立てないように注意しましょう)を頭皮に当てたら、指先に力を入れてぐーっと押します。スタンプを押すように、“いた気持ちいい“程度の圧力で、頭皮全体をまんべんなく押します。
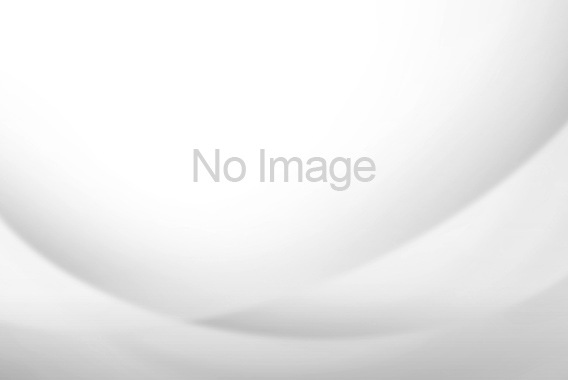 (2) 頭皮を押しながら髪をかきあげる
(2) 頭皮を押しながら髪をかきあげる
両方の指でこめかみ辺りを押さえ、少し圧をかけながら生え際から後頭部へと向かって髪をかき上げます。疲労や老廃物を後頭部へ押し流すようなイメージで、5~10回繰り返します。
(3) 頭皮をたたく
今度はこめかみ辺りから後頭部へ向けて、両手の指先で頭皮をポンポンたたきます。爪を立ててゴシゴシやると頭皮を傷めてしまうので、あくまで優しくたたくのがポイントです。頭皮全体一通りたたくのを1セットとし、2~3セット繰り返します。
入浴中の頭皮への優しいマッサージは髪や皮膚の健康を保ち、その日の疲れを明日に残しません。時間を掛けずにできるので、入浴でのぼせることもなく安心です。
入浴以外でもできるヘッドマッサージとしては、ツボ押しがおすすめです。頭のツボ刺激は手軽に体液循環を促すため、時間や場所を問わずにできて便利です。ツボの位置や効能を知っておくと、気になる症状を改善するのに役立ちます。頭の不調に関係するツボとして次の2つを押さえておきましょう。
※より詳しくツボを勉強したい方には『いちばんわかりやすい東洋医学の基本講座』(成美堂出版)がおすすめです
 (1) 頭痛や疲れ目に効く「百会(ひゃくえ)」
(1) 頭痛や疲れ目に効く「百会(ひゃくえ)」
頭痛の症状を和らげたり、疲れ目を解消したりする効果が期待できる「百会」のツボ。両耳をつないだ線と、身体の中央を縦に走る線とが交差する部分(頭のてっぺん)にあります。疲れがひどい日には重点的に刺激しましょう。
 (2) 熱中症かなと思ったら「顖会(しんえ)」
(2) 熱中症かなと思ったら「顖会(しんえ)」
「顖会」のツボへの刺激は、身体の熱をとって精神を落ち着かせる効果が期待できます。鼻筋をおでこの方向へ延長し、前髪の生え際から親指2本分ほど後ろにいったところにあります。めまいや立ちくらみ、のぼせなどを感じたら刺激してみましょう。
ヘッドマッサージや頭のツボ押しは、疲労回復と老化防止に役立ちます。快適なビジネスライフと若々しさを保つための習慣として、取り入れてみてはいかがでしょうか。
執筆=Nao Kiyota(Self Training Café)
美容・健康ライター。ダイエットアドバイザー、リンパケアセラピスト、心理カウンセラーの資格を生かし、健康で美しくなるためのセルフトレーニング法を発信している。最近カメラを購入。写真で「もっとわかりやすく」伝えられるよう、日々修行に励んでいる。抹茶ラテ(豆乳・シロップ抜き)と足つぼマッサージが大好き。
【T】
疲れ解消★カンタン!アンチエイジング