
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
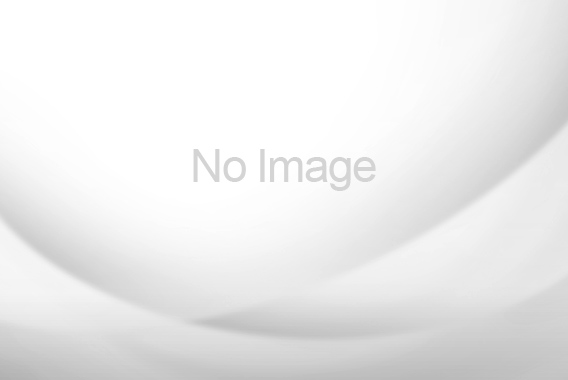
福利厚生の一環として、社宅を社長や役員、従業員に提供する場合がよくありますが、会社の経理処理は、会社が賃貸物件を借りて貸主に賃料を支払い「地代家賃等」として経費にします。そして、入居者である社長や役員、従業員から受取賃貸料として一定の賃料を受け取ります。この方法は、会社が支払った賃料と、役員や従業員から受け取った賃料の差額を会社の経費にできるので、節税効果があります。
社宅を購入した場合には、その建物について減価償却費を計上できます。しかし、役員や従業員に無償または低い家賃で貸与していると、その賃貸料相当額または賃貸料相当額と実際に徴収している家賃の差額に相当する金額が、“現物給与” として課税される場合があります。そうなると、入居者には所得税が、法人には支払家賃が給与になったため消費税の追徴課税がされます。
税務署に認めてもらえる「家賃相当額」の計算方法は「住宅の種類」「役員か従業員か」によって異なりますが、世間一般賃料の10%から20%程度です。以下に、税務調査で指摘されない社宅家賃の計算方法を具体的に説明します。
●従業員の社宅家賃の法定家賃(リーガルレント)の計算方法
従業員の社宅家賃の計算方法は、固定資産税の課税標準額が分かる場合と分からない場合とで、計算方法が異なります。
①固定資産税の課税標準額が分かる場合
次の(1)から(3)の合計額で計算します。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/ 3.3 (平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
②固定資産税の課税標準額が分からない場合
賃貸物件を社宅にして、固定資産税の課税標準額が分からない場合には、支払家賃が賃貸料相当額となり50%以上受け取っていれば給与として課税されません。現金で支給する住宅手当や、入居者が直接契約している場合は社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
●役員の社宅家賃の法定家賃(リーガルレント)の計算方法
会社が住宅を購入したり借りたりして、その住宅を役員に社宅として貸与すれば「支払家賃」を経費にできます。また、購入した住宅であれば減価償却費を計上できます。減価償却費だけでなく、固定資産税や維持費も経費にできます。
役員に対する賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。
小規模住宅とは、建物の床面積が132平方メートル(マンションなどの場合は、99平方メートル)以下であるものをいいます。
①役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃料相当額になります。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
②役員に貸与する住宅が小規模な住宅でない場合
役員に貸与する住宅が小規模住宅に該当しない場合には、その住宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅などを役員に貸与しているかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1)自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし法定耐用年30年を超える建物(マンションなど)の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
社長の自宅を会社が購入して、それを社長に貸すわけですから、会社は不動産賃貸業となり、事業のためにかかった「不動産購入費用ローン金利」「固定資産税」などは、会社の経費になります。
社長は会社に家賃を支払うわけですが、小規模住宅および小規模住宅以外でも通常相場よりもずっと安くなる場合が多いようです。社宅ですから、不動産の名義は会社です。将来、社長を退任した場合には、その住宅を会社に返さなければいけなくなります。ただ、退職金で不動産を受け取れるように役員退職金規定を定めておけば、社長退任後も自分のものとして住み続けられます。
(2)他から借り受けた住宅などを貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額との、いずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
③役員に貸与する社宅が「豪華な社宅」の場合
建物の床面積が240平方メートルを超え、かつ内外装などの状況が豪華な社宅は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃料相当額になります。床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅に設置されていないプールなどの設備や役員個人のし好を著しく反映した設備などを有するものについては、いわゆる「豪華社宅」に該当します。
以上の通り、役員社宅によってかなり節税ができそうですが、注意すべき点を整理すると次のようになります。
1.社内規定の整備
役員社宅として適用する場合は、別途、内規を定める。税務調査で問題視されないようにする。
2.会社名義で契約
契約時に敷金や手数料の費用負担があるが、契約当事者が法人でなければ社宅にならない。
3.家賃以外の負担は役員報酬(従業員であれば)給与
家賃以外の水道代、電気ガスなどの光熱費駐車場代などは役員(従業員)本人が負担する。
4.家賃の一部を役員(従業員)が負担
本人が負担する家賃は法定家賃以上とする。本人負担が法定家賃以下であれば家賃相当分の給与支給があったとみなされ、役員(従業員)に所得税が課税される。
執筆=米山英一
税理士・一般社団法人租税調査研究会 主任研究員。
米山英一税理士事務所所長。税務大学校の教育官をはじめ、東京国税局の調査部門で大規模法人(銀行、不動産、食品、外国法人、特別調査)の調査を担当。初代の連結納税部門の実務責任者(総括主査)として、現在の調査手法などの基礎を築く。都内税務署では法人税調査や相続税調査などの責任者として活躍。2013年7月 退職 、同年8月 税理士登録。
監修=宮口貴志
一般社団法人租税調査研究会 専務理事・事務局長。
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、TAXジャーナリスト、会計事務所ウオッチャーとして活動。元税金専門紙・税理士業界紙の編集長。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ