
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
2018年12月21日、2019年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。その目玉の1つが中小企業の事業承継に関する円滑化対策です。具体的には「個人版事業承継税制」の創設が盛り込まれたのです。その具体化のために財務省は2019年2月5日、個人事業者の事業承継税制の法律案を国会へ提出しました。
法律案が可決されれば、2018年の税制改正により拡充された法人版事業承継税制の特例制度と同様に10年間限定ですが、個人事業者の事業用資産にかかる贈与税または相続税の全額が納税猶予されることとなります。納税猶予とは、一定の要件を充足する場合において、本来納付すべき贈与税または相続税の納付を猶予されるものです。
現在、政府は中小企業の廃業増加に非常に危機感を持っています。その対策として、平成30年の税制改正において、以前からあった法人版事業承継税制を拡充する特例措置を創設しました。これによって、前年まで年間400件程度だった認定申請が年間4000件に迫る件数になりました。このように効果が上がったことから、2019年度税制改正では、その適用範囲を個人事業者に広げることにしたのです。今回は、この個人版事業者版事業承継税制の概要について説明します。
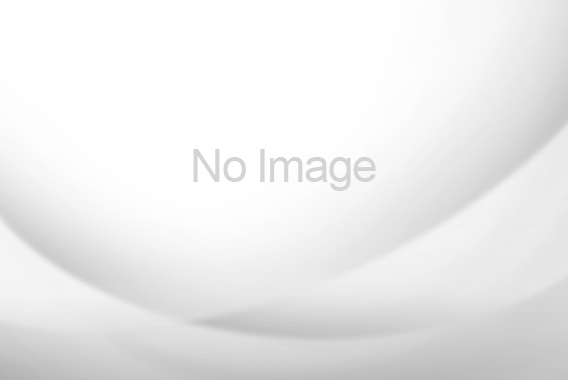 個人版事業者版事業承継税制は、2019年1月1日から2028年12月31の間に贈与または相続により個人事業者の事業用資産の全てを取得した事業承継者が、担保の提供を条件に、その者の事業用資産にかかる贈与税または相続税の全額を納税猶予することで事業承継を支援するものです。
個人版事業者版事業承継税制は、2019年1月1日から2028年12月31の間に贈与または相続により個人事業者の事業用資産の全てを取得した事業承継者が、担保の提供を条件に、その者の事業用資産にかかる贈与税または相続税の全額を納税猶予することで事業承継を支援するものです。
現行制度には、個人事業者の事業承継を支援するものとして、事業用小規模宅地等の特例措置があります。これは、相続により事業用の宅地等を取得した事業承継者の相続税の負担を軽減する制度です。
新しく創設される個人版事業者版事業承継税制は、土地以外の事業用資産も対象とされています。また、生前贈与などにより事業用資産を取得した事業承継者の贈与税も納税猶予制度の対象とされます。この対象資産の範囲の拡充と贈与による承継も適用対象となったことが、個人事業者の事業承継を大きく支援しているところです(「事業用小規模宅地等の特例措置」との併用はできず、どちらかを選択する必要があります)
贈与税・相続税の納税猶予制度の対象となる事業用資産とは、贈与者または被相続人の青色決算書の貸借対照表に記載されている事業に使用された資産のことで、次のものをいいます。
・ 土地(面積400平方メートルまでの部分)
・ 建物(床面積800平方メートルまでの部分)
・ 固定資産税の対象となっている減価償却資産
・ 自動車税または軽自動車税の課税対象となっている営業用の車両等
・ 上記に準ずる減価償却資産で財務省令で定めるもの
この個人版事業者の事業承継税制の法律案が可決すれば、工作機械や診療機器、乳牛や果樹、無形固定資産である特許権などの多種多様な事業用資産が対象となるのです。宅地等以外の事業資産を多く有する個人事業者にとって、円滑な事業承継を支援するものと期待されています。
ただ今回、不動産貸付業は適用対象から外されていますから注意しましょう。
事業承継者が納税猶予制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく認定が必要です。制度を活用するための手続きは、法人版事業承継税制の特例に準じます。法人版に続き約1年遅れの法律案であるため、承継計画書の提出期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までです。この間に認定経営革新等支援機関の指導などを受けて承継計画を策定し、都道府県知事に提出する必要があります。
前提として、贈与の場合は贈与の翌年の1月15日まで、相続税の場合は相続開始の日から8カ月以内が認定の申請期限です。認定を受けた後は、認定通知書を添付した贈与税申告書または相続税申告書を、それぞれの申告期限までに税務署へ提出しなければなりません。その後も、都道府県への継続報告書の提出や、税務署への届出書の提出が必要です。納税猶予制度の適用を検討するのであれば、承継計画書を提出期間内に都道府県知事に提出し、確認を受けておきましょう。
また、納税猶予制度の適用を受けるためには、後継者である受贈者は、贈与の日まで引き続き3年以上事業用資産にかかる事業に従事していたこと、後継者である相続人は、相続の直前において事業に従事していたことが要件とされています。また、両者ともに相続税または贈与税の申告期限までに開業届の提出をしていること、青色申告の承認を受けていることが必要です。
前述の通り、個人事業者の納税猶予制度は、事業用小規模宅地等の特例措置との選択適用となっています。この特例措置の制度は、被相続人が事業用に使用していた宅地等(400平方メートルまで)について、相続税の課税価格を80%減額するものです。その結果、事業承継者の相続税額が軽減されるため、事業用資産のうち宅地等の占める割合が多い個人事業者は、納税猶予制度と、どちらのメリットが大きいのか比較検討をする必要があります。
また、この事業用小規模宅地等の特例措置は、相続税の課税価格を減額するものであるため、事業承継者に配分される前の全体の相続税額を軽減する効果があります。事業承継者以外の他の相続人の相続税額も軽減されることから、選択適用については他の相続人との兼ね合いも検討する必要があるでしょう。
事業用小規模宅地等の特例措置の適用については、2019年度の税制改正により、相続開始前3年以内に新たに事業用に使用された宅地等は適用対象外とされます。ただし、一定の規模で事業を行っていたと認められる場合はこの規定は適用されません。
個人事業者で、将来は事業を法人化する「法人成り」を想定している人もいるでしょう。法人成り以前に個人事業者が事業承継税制の適用を受けていた場合、納税猶予された贈与税や相続税はどういった扱いになるのでしょうか。贈与税または相続税の申告期限から5年を経過した後に、その贈与または相続により取得した事業用資産の全てを現物出資して法人成りした場合には、一定の要件を設けて納税猶予を継続するとされています。
今回の法律案が可決されれば、個人事業者が事業用に使用している資産の種類に応じて、以前からある事業用小規模宅地等の特例措置の適用か創設される納税猶予制度の適用のいずれかを選択できるようになります。また、相続税ばかりでなく贈与税も納税猶予の対象となることから、早い時期からより計画的な事業承継を行えるようになります。
経営者は日々事業を運営していくだけでなく、次世代へ事業を承継していく役割もあります。経営者にとって事業承継税制の知識は、円滑な事業の承継に役立つものです。事業承継税制の今後の動向にもぜひ着目してください。
※掲載している情報は、2019年2月28日のものです
執筆=山岡 美葉
税理士、株式会社アールテロワール代表(https://rody-t.jp/)。 会計事務所勤務を経て2018年1月に税理士登録。現在、千代田区平河町にて開業し、法人税・資産税を中心に税理士業務に取り組んでいる。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ