
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
所得拡大促進税制は、アベノミクスの「3本の矢」の成長戦略を推し進める施策の1つとして、2013年度税制改正で創設されました。デフレを脱却するには消費の拡大が求められます。そのためには国民の所得を増やす必要があるので、企業が従業員の賃上げを行うモチベーションとなることを狙った税制を設けたのです。
創設から5年目にあたる2018年4月1日以降に開始する事業年度からは、要件を大幅に見直した新たな所得拡大促進税制が適用となります。今回は所得拡大促進税制とはどのような制度かを説明した上で、前年である2017年度税制改正から2018年度税制改正への変更点について解説したいと思います。
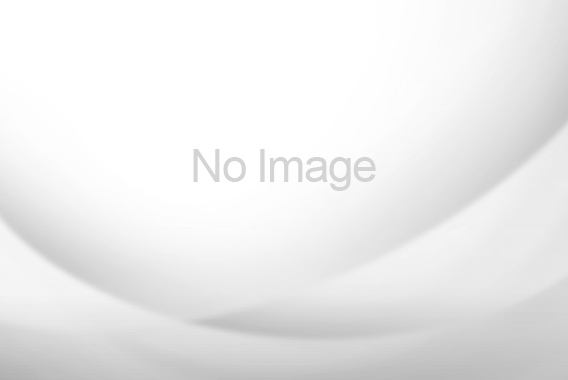 所得拡大促進税制を簡潔に説明すると、企業が従業員の給料をアップすると税額控除が受けられる制度です。具体的には、一定の要件を満たした場合、基準となる年度と比較して給与の支給額が増えた分の10%を税額控除できます。
所得拡大促進税制を簡潔に説明すると、企業が従業員の給料をアップすると税額控除が受けられる制度です。具体的には、一定の要件を満たした場合、基準となる年度と比較して給与の支給額が増えた分の10%を税額控除できます。
税額控除というのは、法人税などの金額を直接減額してもらえることを意味します。税制上の優遇策には税額控除のほかにも、一定の額を損金に算入できるというパターンがあります。一定の額が損金に算入されると、その分だけ課税される所得が減少し、それに税率を掛けた額に相当する税金が安くなります。
税額控除は、税率を掛けた後の税額から直接差し引かれるものですので、同じ金額であれば損金に算入されるよりも税金の減額効果は大きくなります。
創設時の所得拡大促進税制は、(1)給与等支給額が基準年度(2012年度)と比べて一定割合以上増加(2)給与等支給額の総額が前事業年度以上(3)平均給与等支給額が前事業年度を上回るという3つの要件を満たすことで、給与等支給額の増加額の10%(ただし、大企業では法人税額の10%、中小企業者※では法人税額の20%が限度)を税額控除できることとなっていました。
なお、所得拡大促進税制などを含む租税特別措置法における中小企業者とは、資本金または出資金が1億円以下の法人、資本金または出資金を有していない場合には常時使用する従業員の数が1000人以下の法人を指します。
要件の(1)にある「一定割合」は当初5%となっていましたが、ハードルが高いことから導入翌年の2014年度税制改正で早々に緩和が図られました。その結果、2014年度までは2%、2015年度は3%、2016年度は4%(中小企業者では3%)、2017年度は5%(中小企業者では3%)となりました。
所得拡大促進税制の創設は一定の効果を上げましたが、中小企業では大企業と比べて労働分配率が高く、賃上げ余力に乏しいので適用要件を満たすのが難しいなどの理由で活用が進まないという問題がありました。労働分配率というのは企業が生み出した付加価値のうち人件費に回される割合を意味します。
財務省が公表する「法人企業統計調査(平成27年度)」によると、資本金が1億円以上の大企業では、2000年台は70%前後で推移していた労働分配率が、2015(平成27)年には57.7%まで低下しましたが、資本金1億円未満の中小企業では労働分配率が77.1%と高止まりの状態となっています。
こうした中小企業に、付加価値のうち、さらに多くの部分を人件費に振り向けてもらうためには、より強いインセンティブが必要なことから、2017年度税制改正で、かなり大きな見直しが行われました。具体的には、上記(3)の要件において、平均給与等支給額が前年度比2%増加した場合には、大企業では税額控除を2%上乗せして12%に、中小企業者では税額控除を12%上乗せして22%にするという大幅アップの優遇を盛り込んだのです。
日本労働組合総連合会「2017春季生活闘争回答集計結果について」によると、従業員300人未満の企業における2017年の賃上げ率は1.87%となり、2013年の1.53%と比べると、0.34ポイント伸びています。しかし、従業員300人以上の企業における2017年の賃上げ率は1.99%であり、規模による格差は依然として存在します。
労働生産性に目を向けると、「法人企業統計調査(平成28年度)」における大企業の労働生産性が1074万円であるのに対して、中小企業の労働生産性は556万円と隔たりがあります。このことから中小企業において継続的に賃上げを実施していくためには生産性自体を向上させていくことが必要です。
そこで、2018年度税制改正では、従来の税額控除のベースである10%を15%に引き上げるとともに、人材投資や生産性向上に積極的に取り組む中小企業により大胆な支援を実施することとなりました。
具体的な要件として従来の3要件に代えて、中小企業者は、(1)給与等支給額の総額が前事業年度以上(2)平均給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増加という2要件、また大企業では(1)給与等支給額の総額が前事業年度以上(2)平均給与等支給額が前事業年度より3%以上増加(3)設備投資割合が90%以上という3要件を満たすことで、給与等支給額の増加額15%の税額控除が可能となります。
さらに中小企業者では、上記の要件に加え、一定の認定を受けていることを前提に平均給与等支給額の増加割合が2.5%以上かつ教育訓練費の増加割合が10%以上であることを要件として、給与等支給増加額の25%の税額控除が認められます。
なお、大企業においても人材投資や生産性向上を図るべきということで、上記の要件に加え、教育訓練費の増加割合が20%以上であることを要件として、給与等支給増加額の20%の税額控除が認められます
2018年度税制改正は2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。また、所得拡大促進税制は青色申告法人が対象となるものです。
上記の要件のうち「教育訓練費」、「設備投資割合」、「一定の認定」などの詳細な内容については十分に確認する必要があるものの、要件さえ満たせば、事前申請などを必要とせずに適用できる制度です。
所得拡大促進税制は、2017年および2018年の相次ぐ見直しによって、大企業はもちろん、特に中小企業において従業員の意欲向上を図りながら税務メリットを享受できる魅力的な制度になりました。自社においても適用を受けることができないか検討してみてはいかがでしょうか。
執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ