
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
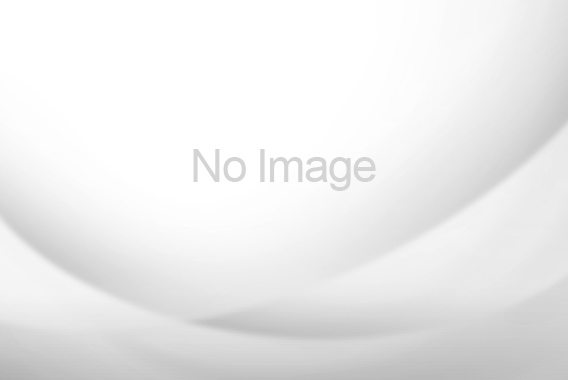
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資金調達に悩む経営者は少なくありません。銀行融資や公的融資制度など活用する手はありますが、審査で一定の時間がかかるため、「早急に資金を用意したい」という切迫した状況では活用しにくいという問題があります。そこで注目したいのが、経営者あるいは法人で契約している生命保険会社からスピーディーに資金調達が行える「契約者貸付制度」の活用です。
ただし、契約者貸付制度を利用することにより、生命保険の本来の目的である「万が一の際の補償」に影響が生じる可能性がある点については、注意しなければなりません。今回は、契約者貸付制度の仕組みやメリット・デメリット、注意点について解説していきます。
生命保険の中には、解約した際に「解約返戻金」と呼ばれるお金が返ってくる商品があります。生命保険の保険料は、死亡した際に支払われる保険金の財源となる「死亡保険料」、加入者が生存時に受け取れる保険金の財源となる「生存保険料」、手数料などの「付加保険料」の3つで構成されています。保険料に生存保険料が含まれている積立型の生命保険(終身保険、養老保険など)や解約した際に支払われるのが、解約返戻金です。
契約者貸付制度は、そうした生命保険の解約返戻金を担保として、一定の範囲で保険会社から資金の借り入れが受けられる制度です。借り入れ可能な金額は、契約内容や保険会社によって違いがありますが、解約返戻金のおおよそ7~9割です。借り入れ可能額の範囲内であれば何回でも借り入れができ、原則として保証人は不要です。
契約者貸付制度の申し込み方法は、郵送のほか窓口での申し込み、コールセンター、ウェブサイト、スマートフォンアプリなど、保険会社によりさまざまです。必要事項を入力するとともに、本人確認書類など必要な書類を提出する必要があります。
契約者貸付制度では、インターネットからの申し込みの場合は当日~2営業日後程度、郵送の場合は1週間程度で借り入れができます。銀行融資などと比較すると、非常に短い期間で資金調達できる点が大きなメリットといえるでしょう。
また、契約者貸付制度は、銀行融資や消費者金融のように毎月一定額を返済する、という決まりはありません。保険の契約期間満了までに完済すればいいのです。返済方法も一括返済や分割返済、一定期間の返済の据え置きなど、いろいろな方法から選択可能なこともメリットといえるでしょう。
契約者貸付制度では、生命保険を解約せずに借り入れが行える点もメリットです。仮に、保険を解約して解約返戻金を受け取って資金調達をしたとしましょう。確かに資金は調達できますが、今後は生命保険のメリットである「万が一の補償」がなくなってしまいます。生命保険に再度加入することはできますが、以前の申込時と比べて年齢が高くなるぶん、高額になる可能性があります。このようなリスクを避けて資金が調達できる点も、契約者貸付制度のメリットです。
また、「資金の用途について問われることがなく、保証人も不要」「審査を必要とせずに借り入れが行える」という点や、同じくスピーディーな資金調達手段であるカードローンの活用と比較すると、金利が低いのもメリットと考えられます。
契約者貸付制度には、以上のようなたくさんのメリットがある一方で、デメリットもあることを理解しておきましょう。
メリットの説明では、契約者貸付制度は契約期間満了までに返済すればいいことを挙げました。しかし、だからといって返済を先延ばししていると金利負担が大きくなり、返済総額が膨らんでしまいます。元金と利息の合計が解約返戻金を超えると、保険契約が失効となる可能性もあります。
また、契約者貸付制度を利用して借り入れを行った後、返済を行わず、そのまま満期を迎えたり、保険を解約したりした場合、満期返戻金や解約返戻金から借り入れた元金と利息の合計額が相殺され、残額が戻ってきます。その場合は当然、当初予定していた金額が受け取れないので、老後の生活資金や遺産に影響が生じます。生命保険の本来の目的を達成するためにも、きちんと返済計画を立てて早期に返済することが、よりよい方法といえるでしょう。
上述の通り、契約者貸付制度は保証人や審査が不要で、スピーディーに借り入れを受けることができる便利な資金調達手段ですが、借り入れの際には、しっかり返済計画を立て、自己管理することがより重要となります。
したがって、契約者貸付制度を利用するのは、一時的にまとまったお金が必要ですぐに返せる場合や、銀行融資の審査を待っていたのでは間に合わない場合など、緊急の場合のみに限定することが望ましいでしょう。
生命保険をかける目的は、老後や万一の際の保障にあります。一時的な資金不足により生命保険の目的を達成できなくなれば、本末転倒です。繰り返しとなりますが、契約者貸付制度を利用する場合は、生命保険本来の役割を考慮し、慎重に検討するようにしてください。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2020年10月22日)のものです。
執筆=河野 雅人
公認会計士・税理士 新宿区に事務所を構えている。主に中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援中。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ