
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
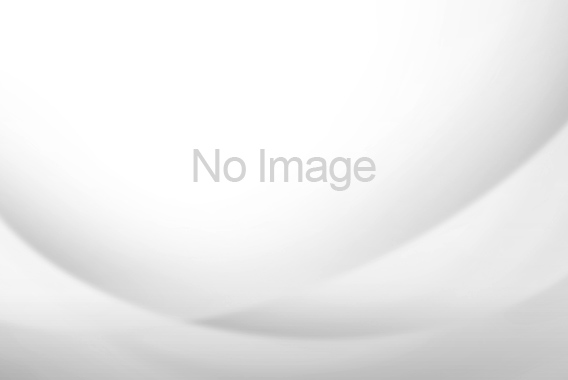
日々、自社の資金繰りや財務内容に頭を悩ませている中小企業経営者も少なくないでしょう。資金繰り対策や財務内容改善、さらに役員個人の税負担軽減にもつながる可能性があるのが役員報酬の見直しです。役員報酬を決定する場合、その手続きや変更方法についてはいろいろと決まり事があり、一度決定すると、原則として事業年度途中で変更することはできません。しかし、業績悪化のような改定事由が生じた場合などは改定可能なので、その限りではありません。
これらを踏まえて今回は、役員報酬と関連税制について解説します。その前提として、法人税法上の役員について確認しておきます。次の2つが役員およびみなし役員になります。
1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2. 1以外の者で次のいずれかに当たるもの(みなし役員)
(A)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
(B)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)のうち、株式保有要件を満たす者(特定株主)でその会社の経営に従事しているもの
社員の給与は、歩合給など月々に変動があるものを含めている経営者もいることでしょう。役員の場合は、原則として定期同額給与については毎回(月々や毎週など、1カ月以内の頻度で)一定額を支払わなければ、損金不算入になるので注意してください。給与額改定は、事業年度開始日から3カ月経過より前(事業開始が4月1日なら、6月30日まで)にしなければなりません。
業務上で合理的な面はあります。定期同額給与は事前に税務署に届け出る必要がなく、原則として決算時の定時株主総会を開催(議事録を作成)して、承認などを得ることによって改定できます。1人社長などの小規模な企業は、会社法で株主全員がメールや書面などで同意すれば、株主総会は不要で、決議があったものと見なされます(みなし決議)。その上で、株主総会議事録を「決議があったものと見なされた」ということで作成すればいいのです。
また役員報酬は金銭の授受だけではなく、企業が役員に物品などを贈与した場合や債務免除などの経済的利益を含みますので、例えば企業が役員に対して月々の家賃を負担している場合などは、定期同額給与扱いにできます。
役員に年1回や2回払いのような形で支給した給与は、定期同額給与にできませんが、こういった形で役員に賞与を支給したいときには、事前確定届出給与が利用できます。これは所定の時期だけに確定額を支給するもので、全額を損金算入することができます。流れとしては、株主総会などの決議により、支払期日と金額を事前に税務署へ届け出し、届出書通りの金額を支払います。そのため、原則として届出書に記載した支給額と実際の支給額が異なる場合は損金不算入となってしまいます。
気を付けていただきたいことは、税務署への届け出を職務執行開始日または株主総会などの決議日のいずれか早い日から1カ月以内、あるいは事業年度開始日から4カ月を経過する日のうち、いずれか早い日までに届け出る必要があるところです。
基本的に事業年度途中の定期同額給与は増減できませんが、経営状況が著しく悪化したときなどは減額ができます(業績悪化改定事由)。もちろん減額改定後の給与も毎回一定額での支払いが必要ですので、改定額を策定する際には留意しましょう。
※業績悪化改定事由による改定の該当例
(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
(3)業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先などの利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合で、利害関係者からの開示要求に応じるもの。
事前確定届出給与についても、業績悪化改定事由が生じた場合には、内容変更に関する株主総会などの決議をした日から1カ月以内に、事前確定届出給与に関する変更届出書を税務署に提出すれば減額ができます。
また、役員給与には、利益に連動して役員報酬を支払い、その金額を経費とすることができる利益連動給与もあります。ただし、利益連動給与の支払いには非常に厳しい条件があり、まず同族会社には認められず、さらに支給金額算定を事前に設定する必要があります。事務手続きの負担が大きいことから、中小企業ではあまり利用されていませんが、該当する企業は検討してみるのもいいかもしれません。
2020年から給与所得控除額の上限が下がります。年収850万円超の給与所得控除額は195万円が上限となります。給与所得控除による節税効果は減少しますので、自社の利益と役員報酬のバランスを考慮し、定期同額給与と事前確定届出給与の割合など、財務を鑑みて検討してみてはいかがでしょうか。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2020年4月6日)のものです
【関連記事・参考資料】
国税庁「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
国税庁「役員給与等」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm
国税庁「役員給与に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
国税庁「定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/03.htm
宝達 峰雄『役員給与等の税務』(税務研究会出版局・令和元年)
執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。 https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ