
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
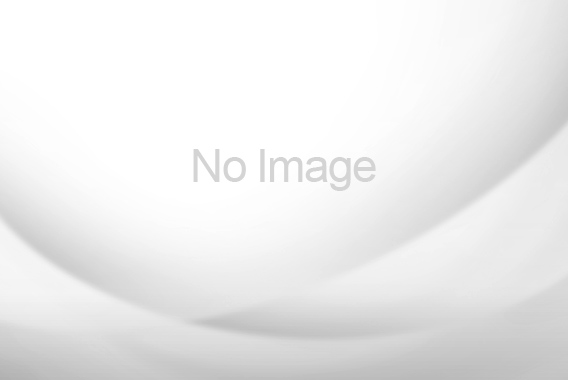
税務調査の場面では、最終的に税務署側と納税者側の“落としどころ”の探り合いになることが少なくありません。税務署側の内部事情と、早く調査を終わらせたいという納税者側の気持ちが“落としどころ”という、何ともふわっとした決着につながっていきます。税務署の内部事情とそこから見える問題点について考えたいと思います。
税務調査について調査担当者・部門という視点から見てみます。
税務署の調査部門で一般部門といわれるところは、基本的には、部門統括官(特官)が事案選定をしています。そして、調査予告後に、通常は1人で税務調査にやって来ます。大規模法人を調査する特官の場合も、調査予告の後に付職員との組調査で税務調査が行われます。また、大規模な税務署に設置されている特別国税調査官(総合調査担当)、いわゆる総合特官、特別管理部門、繁華街担当部門(機能別担当部門)の職員は特に調査能力が高いとされており、売り上げ除外などの不正計算を想定して、調査予告をせずに厳しい調査を行います。
税務署 法人課税部門(法人税、消費税、印紙税、酒税等)の組織図
そのため、さまざまな資料などから多額の不正が想定されるような事案については、総合特官などが管理しています。特別国税調査官(総合調査担当)、いわゆる総合特官、特別管理部門、繁華街担当部門(機能別担当部門)の職員の中から特に優秀な職員は国税局の資料調査課、調査部、査察部などに異動します。調査予告の有無、担当部門、調査指揮を執る統括官・調査担当者の経歴・調査経験年数、調査初日の人数などで、調査内容・調査深度が大きく違ってきます。調査予告がなく複数で来たなら、取引銀行、代表者自宅へも臨場している場合が多く、また、相当確度の高い資料を持っており、厳しく、深度ある調査が実施される可能性が高いのです。調査担当者によりどのような非違を想定してどのくらいの調査になるのか予想できます。まさに、孫子の兵法にいう「敵を知り、己を知れば、百戦殆うからず」です。税務署をよく知ることが税務調査対策として重要です。
具体的にどのように税務調査が行われるのでしょうか。調査担当者によっては、会社事務所内の机の引き出し、金庫、ロッカーの中、自宅にある金庫などに保管されているものを確認したいと言ってきます。税務調査の基本は、原始記録などの把握にあります。入出金、口座などを記載した社長のメモ、手帳などは原始記録となりますし、印鑑、ゴム印などは請求書、領収証の作成に使用されます。メモなどが経理処理と異なっていないか、請求書・領収証に不審なものはないか検討するのです。この原始記録などを把握するための調査技法を現物確認調査といいます。経験上、それらは、代表者のかばん、ロッカー、引き出しなどから発見される場合が多いのです。税務調査は査察と異なり任意調査ですから、もちろん断ることはできます。「断ったら、何か隠していると思われるかもしれない」などと考える必要はありません。
調査担当者は、例えばこんな風に言ってきます。「使い切った領収証などはどこにありますか」。「金庫の中です」と答えれば、「持ってきてもらえますか」と。そして経理担当者が金庫に行くのについて行き、「ついでに金庫の中を確認させてください」と言って金庫の中を確認します。また、机の引き出し、ロッカーも同様です。当然のことですが、調査担当者は中身には触れません。すべて会社側に出してもらいます。「私物が入っていますから」と言っても、調査担当者からは、「私物とそうでないかは私が判断します」と言われてしまいます。私も何度か社長の手帳に記載されたメモから不正計算を把握したことがあります。これは綿々と引き継がれている調査ノウハウです。
税務署では、法定化された調査手続きにより、調査担当者が、統括官の指示の下調査を進めます。事案により統括官までの決裁、副署長までの決裁、署長までの決裁を了して、納税者に対する調査結果の説明、修正申告の勧奨を経て調査終了となります。不正事案となれば途中から署長、副署長が関与してきます。署長の考え方で調査の方向性が決まります。このとき、法人の審理担当から、不正事案として重加算税を賦課するために具体的にどのような証拠を収集する必要があるか指示されます。金融機関調査・反面調査などの補完調査の必要性、質問応答記録書の作成項目などです。統括官・担当者は、その指示に従いながら調査をさらに進めます。最終的には署長、担当副署長、第1統括官、統括官、担当者、審理担当がメンバーとなって事案の処理について協議します。これを重要審議会、略して重審といいます。最終的にその場で不正事案として重加算税を賦課するのかなどが決まります。この重審は人事評価の大きな要素となりますが、反面、この一連の流れは、実は調査担当者にとってさまざまな資料の作成が必要となるなど税務調査の長期化の一因になっています。
税務署内部にいて感じたのは、まず、調査手続きの法定化により、作成書類と決裁終了までの手続きが増えて調査期間が長期化したということです。特に重加算税賦課事案では、3で説明した内部手続きを経て事案の検討がなされます。長期化に伴う納税者への直接の影響は、精神的な負担はもちろん、延滞税の増額です。このため、納税者側の調査を早く終了させたいという事情から、納得しないままに税務署の言い分を飲んでしまうことがあるのではないかと危惧します。税務調査に当たって納税者側は、税務調査の長期化を避けつつ、立証責任は税務署にあるのですから、税務署からは納得のいく説明を受けなければなりません。
執筆=横田 光幸(よこた みつゆき)
横田光幸税理士事務所 税理士、一般社団法人租税調査研究会主任研究員。東京国税局課税第二部法人税課係長、同部消費税課係長、同部法人課税課係長、麻布税務署法人統括国税調査官(公益法人等担当)、税務大学校東京研修所主任教育官、東京国税局主任税務相談官、庄原税務署長(広島国税局)、江東西税務署長、令和元年7月退職、同年7月、一般社団法人租税調査研究会・主任研究員。同年10月税理士登録。
監修=宮口貴志
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、一般社団法人租税調査研究会常務理事。元税金専門紙編集長。会計事務所ウオッチャーとして活動。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ