
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
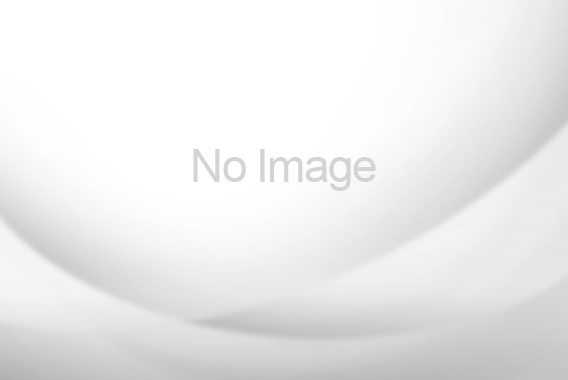
税務署の資産税部門には、調査を担当する女性職員が複数人配置されていますが、昭和60年代にはとても珍しい存在でした。そんな時代に筆者は、税務署の資産課税部門などで相続税調査に従事していました。税務調査時には、税理士から「女性調査官の調査は初めてだよ…」と大変珍しがられ、ひとしきり私の経歴が話題となっていたようです。
平成10年代になると、関与税理士から「女性調査官の調査は苦手だなぁ」と言われるようになりました。これは、女性特有の丁寧な調査にてこずった苦い経験から…?とも思いますが、これとは別に、男性調査官が容易に同意を得られなかった未亡人に係る現物確認調査が可能となった点が、大きな理由だと思われます。まさに資産課税部門の女性調査官の育成を図ったのも、そうした狙いからです。現に、筆者が担当した調査事案の8割強は、未亡人が相続人の事案でした。
筆者の現職時代の経験を踏まえ、相続税調査の選定ポイントと実地調査の流れを見ていきましょう。
申告をしても調査官が自宅などに臨場(相続税調査では「臨宅」といいます)する調査を受ける確率は高くはありません。次のようなポイントで、申告誤りや不正が想定される事案を実地調査に選び、例年8割強の事案で申告漏れを指摘し、1割強に重加算税(税金の重いペナルティー)を賦課しています。
・高額(1億円超)な相続財産
・被相続人の生前中の収入に比べて相続財産が少額
・直近の譲渡代金の化体財産が不明
・過去に受けた法人税や所得税の調査で重加算税が賦課されている
これら申告書提出事案のほか、部内資料により無申告と想定される事案も選考し、優先順位を付けた上で、7月10日の人事異動後から全国の税務署で新規の実地調査を実施します。法人税や消費税、所得税の実地調査は2~4日、長いもので10日間の予定で実施されますが、相続税の臨宅の際は、相続人全員の集合を依頼し、基本的には1日で終了します。実地調査の流れとしては、2~3人の調査官が午前9時以降に被相続人の自宅に臨宅し、午前中は相続人から被相続人について聴き取りをします。
聴取内容はマニュアル化されており、相続人のほうから質問以外の事柄について話す必要はありません。ただし、調査官はいくつかの矛盾を突いて独自の問いかけをする場合があります。筆者は、家計を守ってきた未亡人に対し、妻として、嫁として、母としての同じ目線で話を聞き、被相続人の生い立ちや趣味、家族との関わり方などから被相続人の人となりをイメージした上で、被相続人の通院歴や病状、死亡原因、相続人の渡航歴など具体的な事項を基に、生前および死亡後の財産管理の状況などを検証、また相続人同士の何気ない会話からも調査事項を把握していました。
午後からは、預貯金の通帳など申告の原資記録から相続財産の確認を行います。税務署では、預貯金の取引状況について各金融機関へ照会し把握しますが、通帳に記入されているメモ書きなどを確認するため、被相続人名義のものだけでなく、同居している相続人や孫の通帳の提示も依頼します。
その際、「古い通帳はすべて廃棄した」「相続人名義の通帳は見せられない」などと協力を拒むと、「何か隠しているのではないか」とあらぬ疑いをかけられてしまうので、古い通帳の廃棄などには注意しましょう。また、この原資記録の確認調査と並行して、他の調査官は通帳や印鑑などの保管場所の確認のため、相続人の同意を得て他の部屋などで現物確認調査を行うのが原則となっています。
この現物確認調査をスムーズに行うため、冒頭でお話しした通り、未亡人に対する調査の場合は女性調査官と組んで調査を行います。つまり、この現物確認の実施が実地調査のポイントとなるわけです。筆者も、この現物確認調査によって得た公表外の金融機関や証券会社、押し入れの奥の紙袋に入った現金などを見つけて重加算税の賦課に結び付けました。このように、相続人からの聴き取りを確実に行い、その後の現物確認調査によって不正の有無を明らかにするのが実地調査の目的なのです。
最後に、妻名義の預貯金をいわゆる「名義預金」として夫の相続財産にすべきかどうかの判断のポイントをお伝えしましょう。
その預貯金の原資が、妻の給与や専従者給与であれば問題なく、夫の財産とはなりません。夫から生活費として渡されていたお金を、妻が自由に使うために自分名義でためていた場合は、名義預金として申告が必要となります。この、生活費を巡る考え方については贈与税の判定の際にもよく質問され、生活費に贈与税は課税されないとの認識を持っている方は多いと思います。
しかし、生活費として渡された金銭は、食料品や衣服などの購入代金として使われて(費消して)初めて生活費となるので、使われずにたまっている金銭は生活費とはいえません。また、配偶者名義に限らず、子や孫名義の預貯金については、その原資や管理の状況を確認し、贈与によるもの以外は名義預金として相続財産に加算する必要があるので、注意が必要です。
筆者=坂本 明美
国税庁勤務の後、東京局管内税務署で資産税事務に従事。同局課税一部機動課初の女性主査として多くの相続税調査を手掛け、資産税課実務指導専門官、監察官、副署長、資産税調査特官、局主任相談官、関東信越国税局桐生税務署長等歴任。平成30年退官。同年8月税理士登録。一般社団法人租税調査研究会主任研究員。現在は、租税調査研究会の会員会計事務所向け相談委員(資産税担当)をはじめ、多くの相続税申告などを手掛ける。
監修=宮口貴志
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、一般社団法人租税調査研究会常務理事。元税金専門紙編集長。会計事務所ウオッチャーとして活動。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ