
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
コロナ禍における在宅勤務の影響などもあり、社員の副業を認める企業が増えました。副業といってもアルバイトではなく、ガッツリ自ら事業としてはじめるケースもあれば、この機会に個人事業主として起業(開業)する人もいるでしょう。
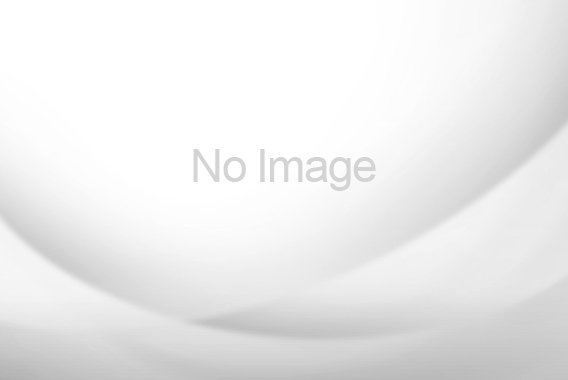
こうした場合、毎年税務署に確定申告をする必要があります。確定申告は、1月1日から12月31日までの間に所得のあった人が、所得税と復興特別所得税の額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税と復興特別所得税の「還付申告」をする手続きです。確定申告の手続きは原則、翌年の2月16日~3月15日に行います。
確定申告では、事業の収支を自分で計算して、税金計算の基となる所得金額を計算します。所得金額の計算においては、稼いだ金額から、稼ぐためにかかった経費(必要経費)を差し引けるので、どこまで必要経費として落とせるのか、節税のためにも十分に理解しておく必要があります。
税務調査では、この部分が一番のチェックポイントになります。例えば、お店などを借りて料理セミナーなどを開催している場合、経費として落とせるのは、セミナー会場代や事前の打ち合わせなどで使った会議費、交通費、資料作成の印刷費、勉強のために購入した書籍などが該当します。
一方で、自宅の一室で料理セミナーを開催する人も少なくないと思います。この場合は、経費として落とせるものが少しややこしくなるので注意してください。専門用語では「家事関連費」といいます。
家事関連費の中でも、とりわけ税務署のチェックが厳しいのが、自宅を仕事場として収入を得ているケースです。例えば、自宅が賃貸住宅である場合、または住宅ローンを毎月返済している場合、一室を完全に講習会用の部屋として使用している場合など、ケースによって経費にできる金額の計算方法が違ってきます。
では、個人事業主の必要経費の考え方を法律上から見ていきたいと思います。
【所得税法第37条】には、収入から引くことのできる必要経費の金額は、収入を得るために直接かかった費用、利益を得るためにかかった費用の額とあります。
一方で【所得税法第45条】には、家事上の経費及びこれに関連する経費は必要経費にできないとあります。この家事上の経費とは、個人事業主が事業としてではなく、生活者として消費する支出額(家事費)のことをいい、これに関連する経費とは家事関連費ともいわれ、家事費(生活上の支出額)と必要経費の両方の性質を併せ持つ支出のことをいいます。つまり、所得税法37条において必要経費になるものを示し、所得税法45条では必要経費にできないものをあげているのです。
ところが、家事関連費がややこしいのは、【所得税法施行令第96条】では、家事関連費であっても以下の要件に該当すれば必要経費として認めているのです。
どのような要件かというと、「主たる部分」が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合です。つまり、ビジネスで使っている部分なのか、プライベートで使っている部分なのか、「明らかに区分」できれば、ビジネスで使っている部分は家事関連費として必要経費にできるというのです。ただ、この「明らかに区分することができる場合」の判断については、法令などで具体的に示されていません。客観的に第三者の観点から妥当であるか否かで判断することになります。
例えば、セミナーを開催する個人事業主が、賃貸している自宅の一部を事業用として使用している場合、ビジネスで使っている部分は、支払っている地代家賃の一部から必要経費として落とせます。この「一部」の計算方法は、業務内容や利用状況などを総合的に判定して金額を算出します。
ここで重要になるのが、「主たる部分」の判定です。税理士の間ではよく「50%ルール」などといいますが、それは、【所得税法基本通達45-2】にある、業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するという規定からです。ただ、その後のただし書きには、必要な部分の金額が50%以下であっても業務に必要となる部分を明らかに区分できるのであれば、必要経費に計上して差し支えないとしています。
以上のとおり、家事関連費は、業務上必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分に限って、必要経費に計上できます。ただ、ここで注意が必要なのが、区分計算などの根拠を明確にしておく必要がある点です。
先の例で考えたとき、自宅の一室を講習会やセミナー専用の部屋として使うため、改装などを行い、生活用として使用せずに専らビジネスで使用しているなら、自宅建物の延べ床面積に占める事業として使用する面積の割合に応じた費用の額を必要経費にできると考えられます。建物を購入していれば、減価償却費、固定資産税、火災保険料、借入金の支払利息額なども、案分した額を必要経費として計上できます。賃借なら、支払家賃や管理費などが必要経費にでき、その金額は案分した額までとなります。つまり、両方とも支払総額に占める事業で使用する割合は必要経費にできます。
具体的な数字をあげて説明すると、延べ床面積が82.5㎡で、事業専用分が16.5㎡だったとします。この場合、事業専用部分は全体の20%。支払家賃総額が1年間で360万円の場合なら、72万円が必要経費ということになります。前述した「明らかに区分することができる」部分は、このケースでは全体の20%。所得税基本通達の「業務の遂行上必要な部分が50%を超える」には該当しませんが、50%以下であっても明らかに区分されていれば経費に計上して差し支えないとしていますので、この20%が必要経費になります。
個人事業主の確定申告状況を見ると、申告されている必要経費の中には、食費や光熱費、住居費など生活者としての消費支出分を混入されているケースが散見されます。税務署では確定申告された内容を確認しています。特に、申告された経費の各科目の中で生活上の支払額が混入されやすい科目(租税公課・水道光熱費・支払保険料・減価償却費・地代家賃など)がいくら計上されているのか、同じ事業で申告している他の納税者に比べて額が多い科目はないかなどを検討し、確認が必要となる納税者に対しては税務調査を実施したり書面で回答を求めたりします。業務に必要のない経費や明らかに区分されていない家事関連費が申告されていた場合には、申告された税金の額の是正を求めます。
不足した税金に加えて、正しい申告をしなかった罰金の要素の強い加算税と期限まで納税されなかった利息である延滞税も納税しなければなりません。個人事業者の方が確定申告する際には、「法律を知らなかった」は理由にはなりません。くれぐれも、「家事費は必要経費に算入できない」「家事関連費については業務に必要な部分は必要経費に算入できるが、必要な部分を明らかに区分できる場合に限られる」と十分に理解した上で申告してください。
筆者=笹崎 浩孝(ささざき ひろたか)
東京国税局管内の税務署で個人課税および総務事務に従事。その後、同局課税一部資料調査課において多くの調査事務を経験し、税理士専門官、課税一部個人課税課課長補佐、税務署総務課長、副署長、特別国税調査官(開発・総合担当)、査察部統括官、巻税務署長、調査三部統括官、平塚税務署長を歴任し、2021年7月退官。同年8月税理士登録。一般社団法人租税調査研究会主任研究員。
監修=宮口 貴志
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、一般社団法人租税調査研究会常務理事。元税金専門紙編集長。会計事務所ウオッチャーとして活動。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ